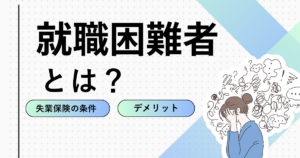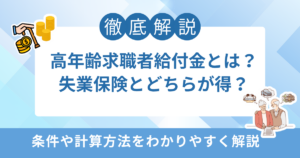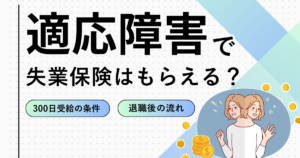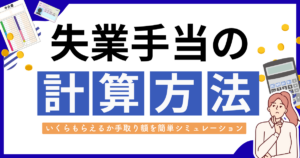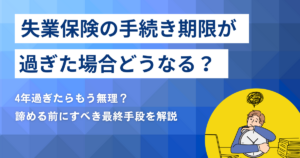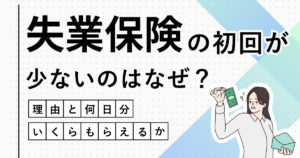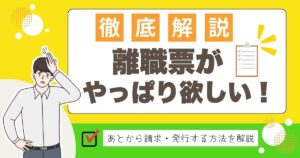特定理由離職者は診断書がいらない?必要・不要なケースや退職後の必要書類も解説
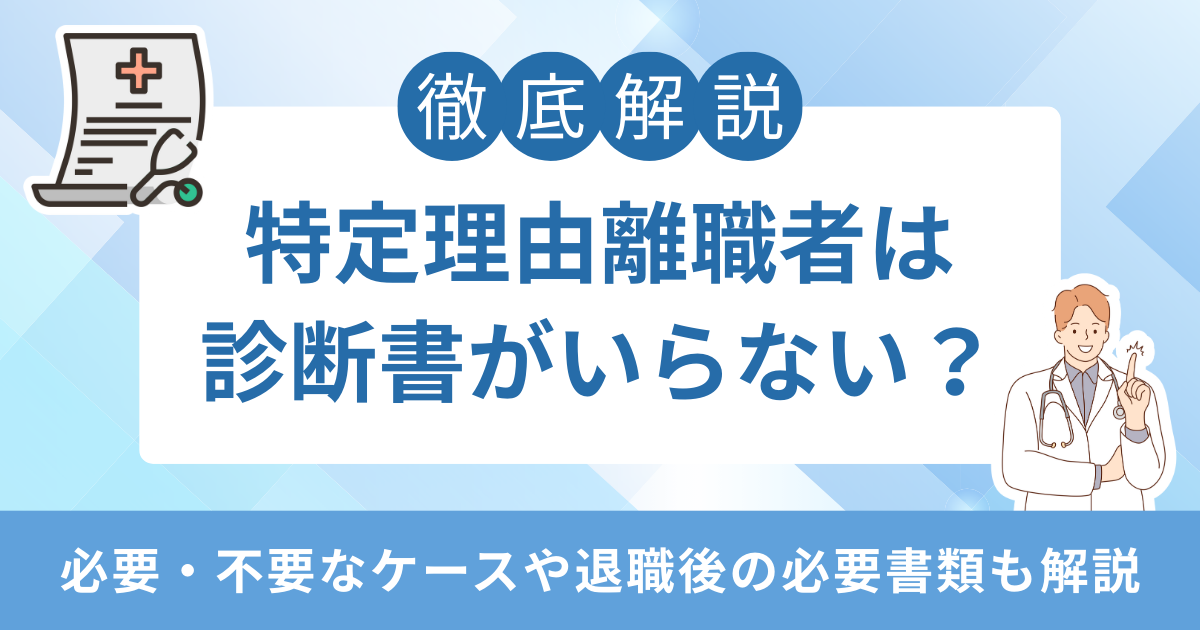
失業保険は、退職後の生活を支える大切な制度です。
とくに体調不良などを理由に退職した場合、「特定理由離職者」として有利な条件で受給したいと考える方も多いでしょう。
しかし「そのために診断書は必須なのか」「費用や手間をかけずに手続きできないか」といった不安を持つ方は少なくありません。
結論として、特定理由離職者の認定に診断書は必ずしも必須ではありませんが、退職した理由を客観的に証明することが非常に重要です。
本記事では、診断書が不要なケースと推奨されるケース、診断書の代わりになる証明書類の具体例を詳しく解説します。
また、退職後に診断書を取得する方法も紹介するため、自身の状況にあわせた最適な準備の進め方がわかります。
失業保険の手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
あなたの場合は診断書が必要?
簡単セルフチェック
- 体調不良が退職理由だが、上司との相談メールや勤怠記録など客観的な書類がない。
- 職場の人間関係やパワハラなど、記録に残りにくい精神的ストレスで辞めたい。
- うつ病や適応障害と診断されてはいないが、心身の不調で働くのが限界だと感じている。
【結論】特定理由離職者の認定に診断書は必須ではない

特定理由離職者として認定を受けるために、医師の診断書は必ずしも必須というわけではありません。
一方で、退職理由によっては診断書があった方が有利に、そしてスムーズに手続きが進むケースがあるのも事実です。
ここでは、それぞれの項目について解説します。
- 診断書がなくても特定理由離職者と認められるケース
- ハローワークが重視する客観的な証明の重要性
- 診断書の代わりになる有効な証明書類の具体例
- 診断書があった方が有利に進むケース
特定理由離職者に認められて、有利な条件で失業保険を受給したいと考えている方は、参考にしてください。
診断書がなくても特定理由離職者と認められるケース
診断書がなくても特定理由離職者と認められるのは、離職理由が客観的な事実に基づいており、他の公的な書類などで証明できる場合です。
たとえば、事業所の移転により通勤が困難になった場合は会社の移転通知や辞令が有効な書類です。
他にも家族の介護が必要になった場合は住民票、介護対象家族の要介護認定通知書などが証明書類となります。
また、体調不良が理由であっても、上司や人事部との面談記録、業務に関する相談メールなども、証明書類として認められる可能性があります。
このように、退職せざるを得なかった状況を第三者が納得できる形で証明できれば、診断書は必ずしも必要ではありません。
ハローワークが重視する客観的な証明の重要性
失業保険の認定手続きにおいて、ハローワークは個人の主観的な主張よりも、第三者が見て納得できる客観的な証拠を最も重視します。
なぜなら失業保険は公的な制度であり、その公平性を保つために、退職理由が正当なものであるかを客観的な事実に基づいて判断する必要があるからです。
これは、不正受給を防止するという大切な目的も担っています。
たとえば、「仕事が辛かった」という口頭での説明のみでは、その深刻さを判断することは困難です。
しかし、時間外労働の時間を示す勤怠記録や、業務内容の改善を求めたメールなどがあれば、それは客観的な証拠として扱われます。
そのため、自身の状況を的確に伝えるためには、主張を裏付ける客観的な資料を準備することが非常に重要になるのです。
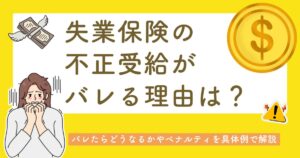
診断書の代わりになる有効な証明書類の具体例
診断書がない場合でも、退職理由を証明できる可能性のある書類はいくつか存在します。
自身の状況にあわせて、次のような書類を準備することを検討しましょう。
証明書類の具体例
- 体調不良が理由の場合
- 上司や人事部との面談記録や相談したメールの履歴
- 勤怠記録(体調不良による欠勤や早退がわかるもの)
- 産業医との面談記録
- 具体的な症状と業務への支障を明記した退職届の写し
- 介護や家庭の事情が理由の場合
- 住民票や戸籍謄本(介護対象の家族との関係を証明)
- 介護対象の家族の要介護認定通知書や医師の診断書
- 会社の転勤命令書や辞令(配偶者の転勤に帯同する場合)
上記のような退職理由を証明できる種類があれば、特定理由離職者として認められるため、必ずしも診断書が必要なわけではありません。
診断書があった方が有利に進むケース
退職理由が客観的な証拠として残りにくい場合は、医師の診断書が手続きを有利に進めるための有効な手段となります。
たとえば、職場での精神的なストレスや、客観的な記録には現れない業務上のプレッシャーなどが退職の原因の場合、第三者に証明するのは困難です。
このような状況では、専門家である医師の見解が、就労困難な状態であったことを示す客観的な証明として大きな役割を果たします。
証明が難しいケースほど、診断書があれば認定されやすくなるため、時間や心理的な負担を軽減できるでしょう。
そのため、自身の状況に応じて診断書の取得を検討することをおすすめします。
【ケース別】自身の退職理由は診断書なしで証明可能か確認する

特定理由離職者として認定されるためには、退職理由に応じた適切な証明が必要です。
ここでは、代表的な退職理由ごとに、診断書の必要性や代わりに有効となる書類について解説します。
自身の状況と照らしあわせながら確認しましょう。
体調不良(うつ病・適応障害など)で退職する場合
うつ病や適応障害といった精神的な不調が原因で退職する場合、客観的な証明が難しいため、医師の診断書が有効な証明書類となるケースが多いでしょう。
診断書があれば、就労が困難なほどの健康状態であったことを医学的根拠に基づいて示すことが可能です。
もし診断書がない場合は、自身の主張を裏付けるための代替書類を慎重に準備する必要があります。
たとえば、精神的不調によって遅刻や欠勤が増えたことを示す勤怠記録や、上司に業務の負担について相談したメールの履歴などが有効な場合があります。
ただし、これらの書類だけで必ずしも認められるとは限らないため、準備には注意が必要です。
体力の不足を理由に退職する場合
「体力の不足」が正当な離職理由として認められるかは、年齢や具体的な職務内容、個別の状況などを総合的に考慮して判断されます。
たとえば、高齢の労働者が長年従事してきた肉体労働を続けることが困難になった場合などは、正当な理由と判断されやすいでしょう。
この場合、医師の診断書を提出する必要はありません。
自身の体力の限界を客観的に示すためには、診断書以外の方法も考えられます。
具体的には、上司との面談で体調面を理由に業務内容の変更や配置転換を相談した記録などです。
体力的に業務の継続が困難であったことを示す書類や履歴があれば、状況証拠として有効になる可能性があります。
家族の介護や看護で退職する場合
家族の介護や看護を理由に退職する場合は、その事実を公的な書類で証明できるため、医師の診断書が不要なケースがほとんどです。
介護の事実を証明するためには、主に次のような書類が必要となります。
介護で必要となる公的書類の例
- 要介護認定通知書:介護対象の家族が要介護認定を受けている場合に発行
- 住民票や戸籍謄本:介護対象の家族との関係を証明するために必要
これらの書類は、お住まいの市区町村の役場や、地域包括支援センターなどで取得や相談が可能です。
手続きの前に、どの書類が必要になるかを確認し、準備を進めましょう。
結婚や配偶者の転勤に伴い退職する場合
結婚や配偶者の転勤に伴う引っ越しで、現在の職場への通勤が困難になった場合も、特定理由離職者に該当する可能性があります。
このケースでは、医師の診断書は必要ありません。
重要になるのは、物理的に通勤が困難であることを客観的な資料で証明することです。
厚生労働省によると、公共交通機関を利用して往復でおおむね4時間以上かかる場合などが「通勤困難」の一つの目安とされています。
その証明のためには、次のような書類を準備しましょう。
通勤困難を証明する書類の例
- 配偶者の転勤を示す会社の辞令や証明書
- 新居の住所がわかる住民票や賃貸契約書
- 通勤経路と所要時間がわかるサイトの印刷物
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【退職後でも大丈夫】診断書が必要になった場合の入手方法と注意点

もし診断書が必要になった場合でも、退職後に準備を進めることは可能です。
いざというときに慌てないよう、診断書の入手方法や依頼する際のポイント、費用などについて事前に確認しておきましょう。
退職後でも診断書はもらえるのか
原則として、退職後であっても医師に診断書を発行してもらうことは可能です。
ただし、診断書には「在職中にどのような症状があり、その結果として就労が困難になった」という内容を記載してもらう必要があります。
そのため、退職してから時間が経ちすぎると、在職中の状況との因果関係を証明するのが難しくなる可能性があります。
実際に退職後に診断書を取得した方の体験談でも、「もっと早く受診すればよかった」という声は少なくありません。
退職を決意した、あるいは退職した時点で、少しでも体調に不安がある場合は、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
診断書はどこで発行してもらうべきか
診断書の発行を依頼する病院は、まず在職中に通院していた医療機関があれば、そこが第一候補となります。
カルテの記録に基づいて、スムーズに診断書を作成してもらえる可能性が高いでしょう。
新たに病院を探す場合は、自身の症状にあった診療科を選ぶことが重要です。
たとえば、精神的なストレスが原因であれば心療内科や精神科、身体的な痛みや不調であれば内科や整形外科などが考えられます。
かかりつけ医がいない場合や、どの診療科にいけばよいかわからない場合は、オンラインの病院検索サービスを活用して探すのも一つの方法です。
医師に依頼する際の伝え方のポイント
医師に診断書を依頼する際は、要点をまとめて的確に状況を伝えることが大切です。
事前に準備をしておくことで、診察がスムーズに進み、より正確な診断書を作成してもらいやすくなります。
まず、診断書の使用目的が「ハローワークに提出するため」であることを正直に伝えましょう。
これにより、医師もどのような内容を記載すべきか判断しやすくなります。
さらに、「いつから、どのような症状があり、その症状によって仕事のどのような場面で支障が出たか」を時系列で整理したメモを持参することをおすすめします。
口頭での説明が苦手な方でも、正確に状況を伝える助けとなるでしょう。
診断書の費用相場と発行までの期間
診断書の発行にかかる費用は、公的医療保険が適用されない自費診療となるため、全額自己負担です。
金額は医療機関によって異なりますが、一般的な相場としては4,000円から1万5,000円程度で、記載する内容によって金額が異なります。
発行までにかかる期間も病院によってさまざまですが、早ければ診察当日に、長くても4週間程度で受け取れることが多いでしょう。
診断書は失業保険の申請に必要となる大切な書類のため、費用や期間については、事前に医療機関の受付などで確認しておくと安心です。
書類準備や手続きが不安な方は専門家への相談が近道

ここまで、特定理由離職者の認定における診断書の必要性や代替書類について解説してきました。
しかし、自身のケースがどれにあてはまるか判断したり、煩雑な書類を不備なく準備したりするのは、簡単なことではないかもしれません。
失業保険の手続きで不安を感じる方向けに、おすすめなサービスを紹介します。
自身一人で手続きを進めることの難しさ
失業保険の手続きは、はじめての経験で心配になる方もいるでしょう。
必要書類の種類が多く、またハローワークの担当者によって、判断のニュアンスが異なる可能性もゼロではありません。
もし書類に不備があれば、認定が遅れてしまうリスクも考えられます。
とくに、心身の不調を抱えている中で、これらの複雑な手続きをすべて一人でおこなうことは、大きな精神的負担となるのではないでしょうか。
SNSなどでも、「手続きが思ったより大変だった」「何度もハローワークに通うことになった」といった声が見受けられます。
無理をせず専門家に頼れる選択肢を知っておけば、失業保険の手続き時の精神的な負担を軽減できます。
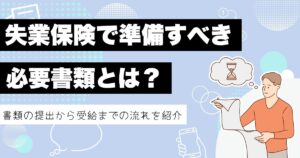
専門家がサポートする失業保険申請代行サービスとは
失業保険の申請サポートサービスとは、社会保険労務士やサポートなどの専門家が、失業保険に関する手続きを全面的に支援するサービスです。
専門家が一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、特定理由離職者として認められるための最適な申請方法をアドバイスします。
また、必要書類の準備や作成のサポートを受けられ、自身で手続きするよりもスムーズに、そして有利な条件で失業保険を受給できる可能性が高まります。
サービスを利用することで、受給できる総額を増やしたり、受給開始までの期間を短縮したりといった金銭的・時間的なメリットも期待できるでしょう。
LINEで無料診断からはじめられる「退職バンク」の紹介
「退職バンク」は、失業保険の申請を専門家がオンラインでサポートするサービスです。
全国どこにお住まいの方でも、外出せずに自宅から気軽に相談できます。
「自身の場合はいくらくらい失業保険をもらえるのだろう?」と考える方は、まずはLINEですぐにできる「無料診断」をお試しください。
いくつかの簡単な質問に答えるだけで、受給できる金額の目安をすぐに確認できます。
相談料は無料のため、手続きに少しでも不安を感じている方は、まずはお気軽に自身の状況を伝えて相談してみましょう。
専門家によるサポートで得られる3つの安心
専門家のサポートを活用することで、単に手続きが楽になるだけでなく、退職後の生活に不可欠な「安心」を得ることができます。
サポートで得られる3つの安心
| 安心のポイント | 詳細 |
|---|---|
| 書類の不備や申請ミスを防止 | 専門家が内容をチェックするため書類の不備による手続きの遅延を防ぐ |
| 受給条件の最大化 | 法的知識に基づき受給額や期間を最大化する最適な申請方法を提案 |
| 手続きを任せて回復に専念 | 煩雑な手続きを任せられるため、心身の回復や転職活動に専念できる |
実際に「退職バンク」を利用された方からも、「一人ではわからなかったことを丁寧に教えてもらい、安心して任せられた」と高く評価されています。
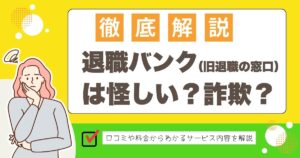
特定理由離職者と診断書に関するよくある質問

最後に、特定理由離職者や診断書に関して、多くの方が抱える疑問についてQ&A形式で解説します。
- 特定理由離職者になるメリット・デメリットは?
- 会社都合退職との違いは?
- 診断書を提出するタイミングはいつがベストですか?
- ハローワークの職員にはどう説明すれば納得してもらえますか?
- ハローワークでの初回手続きに必要な持ち物は何ですか?
気になる質問や疑問を抱く点があれば、ぜひ参考にしてください。
特定理由離職者になるメリット・デメリットは?
特定理由離職者になるメリットは、自己都合退職の場合に設けられる1か月間の給付制限期間がなくなるため、失業保険を早く受け取れる点です。
また、被保険者期間によっては、所定給付日数、つまり失業保険をもらえる日数が長くなる場合があります。
一方、デメリットとしては、退職理由によってはその証明書類を準備するのに手間がかかる点が挙げられます。
会社都合退職との違いは?
失業保険の給付条件に関して、特定理由離職者は倒産や解雇といった「会社都合退職」とほぼ同等の有利な扱いを受けます。
給付制限期間がない点は同じですが、所定給付日数が特定理由離職者のほうが、短くなる可能性があります。両者の根本的な違いは、離職理由の性質にあります。
会社都合退職が倒産や解雇など、会社側が原因なのに対し、特定理由離職者は自身の体調不良や家庭の事情など、やむを得ない理由での離職を指します。
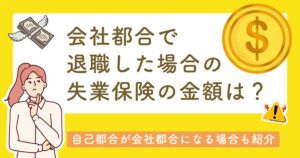
診断書を提出するタイミングはいつがベストですか?
【図解】失業保険手続きと診断書提出のタイミング
-
会社を退職
離職票など、必要な書類を会社から受け取ります。
-
ハローワークで求職申込み
お住まいの地域を管轄するハローワークで、失業保険の受給資格決定手続きを行います。
診断書提出のベストタイミング!
この最初の申請時に、他の必要書類と一緒に診断書を提出するのが最もスムーズです。
-
待期期間(7日間)
受給資格が決定してから7日間は、失業保険が支給されない待期期間となります。
-
失業保険の給付開始
特定理由離職者の場合、待期期間満了後から給付が開始されます。(自己都合の場合は通常2ヶ月の給付制限あり)
診断書を提出する最もよいタイミングは、ハローワークで最初に相談する際や失業保険の申告をするときです。
このときに、離職票や本人確認書類など、他の必要書類とあわせて提出することで、その後の手続きが最もスムーズに進みます。
もし、このタイミングに間に合わなかった場合でも、あとから提出することは可能ですが、認定手続きに時間がかかる可能性も考えられます。
できるだけ最初の段階ですべての書類を揃えて提出することをおすすめします。
ハローワークの職員にはどう説明すれば納得してもらえますか?
ハローワークの職員に退職理由を説明する際は、感情的に訴えるのではなく、準備した客観的な書類に基づいて事実を伝えることが重要です。
まず、なぜ退職せざるを得なかったのか、その具体的な理由と経緯を簡潔に説明しましょう。
そして、その説明を裏付けるものとして、準備した証明書類を提示します。
事前に伝えるべきポイントをメモなどに整理しておくと、落ち着いて的確に状況を説明しやすいでしょう。
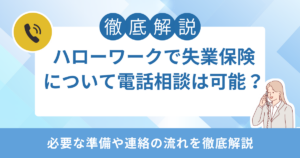
ハローワークでの初回手続きに必要な持ち物は何ですか?
特定理由離職者の証明書類とは別に、ハローワークで失業保険の初回手続きをおこなう際には、基本的に次の持ち物が必要となります。
初回手続きの基本的な持ち物リスト
- 離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真(マイナンバーカードを提示する方は不要)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
書類の不備があると認定が遅れる原因にもなるため、事前に準備してからハローワークで手続きをしてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
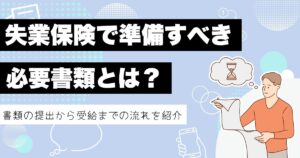
まとめ

本記事では、特定理由離職者の認定における診断書の必要性について、不要なケースや代替書類、退職後の入手方法などを解説しました。
特定理由離職者の認定に診断書は必須ではありませんが、自身の退職理由を客観的な資料で証明することが極めて重要です。
どの書類が有効で、どのように手続きを進めるべきかの判断は、ときに難しい場合もあるでしょう。
失業保険の手続きに関して不安な点があれば、当サイトのような専門的な情報を参考に、自身にとって最適な選択をしてください。
より確実なサポートを求める場合は、専門サービスである「退職バンク」への相談も有効な選択肢の一つです。
もう一人で悩まない!
専門家のサポートで、
安心の退職準備を始めませんか?
「退職バンク」なら、複雑な手続きもお任せ。
あなたの退職後を徹底的にサポートします。
- 受給額の最大化をサポート
- 最短1ヶ月でのスピード受給
- 面倒な手続きから解放