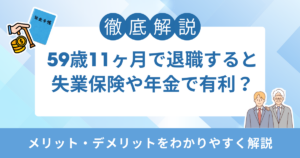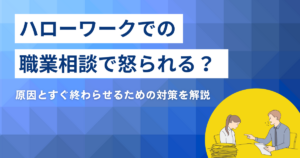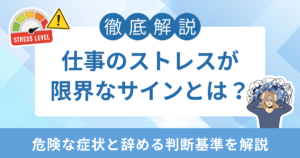賢い退職の仕方とは?お金と手続きで後悔しない方法を解説
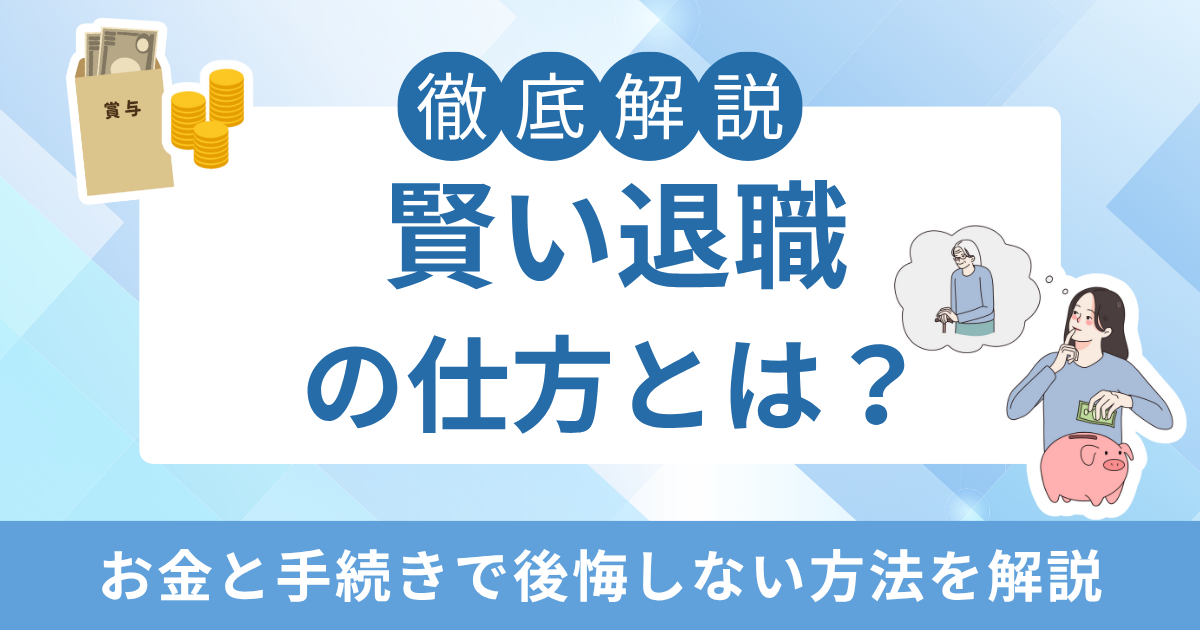
退職は、キャリアにおける重要な転機の一つです。
しかし、多くの方が退職後の生活費や複雑な手続き、会社との関係性について、「どう進めれば損をしないのだろうか」との不安を抱えています。
結論として、賢い退職は正しい知識を持てば十分に可能です。
重要なのは、お金の制度を最大限活用し、最適なタイミングを見極め、円満なコミュニケーションを心がけることにあります。
本記事では、失業保険の最大化から税金・社会保険の手続き、上司への最適な伝え方まで、退職にまつわる不安を解消するための知識を解説します。
最後まで読めば、自身の状況に合わせた最善の行動計画がわかり、自信を持って新たな一歩を踏み出せるようになります。
退職を少しでも考えている方は、今後のためにぜひ参考にしてください。
「退職後のお金」は主に2種類!
あなたはどちらを調べるべき?
A
会社の制度
(退職金など)
勤続年数や功労に報いるため、会社が独自に定めるお金。
制度があるかどうかは会社次第です。
B
公的な制度
(失業保険など)
失業中の生活を支え、再就職を助けるためのお金。正社員以外も対象で、多くの人に関係します。
【最重要】賢い退職はお金の知識から|損をしないための3つのポイント

賢い退職を実現するために最も重要なのは、退職後のお金に関する知識です。
ここでは、退職時に損をしないために押えておくべき、次の3つの重要なポイントを解説します。
- 失業保険(雇用保険)を最大限に活用する方法
- 退職後の税金・社会保険で損をしない手続き
- 病気やケガで退職する場合に利用できる制度
それぞれの内容を具体的に解説します。
失業保険を最大限活用する方法
失業保険とは、厚生労働省が管轄する雇用保険の基本手当のことで、会社を辞めて次の仕事を探す間の生活を支える大切な制度です。
受給できる金額や期間は、退職前の給与や雇用保険に加入していた期間によって決まります。
そのため、受給額を最大化するためには、失業保険を最大限活用する方法を理解しておくことが重要です。
また、自己都合で退職した場合、通常は給付をもらうまでに待期期間がありますが、例外もあります。
たとえば、病気やハラスメントなどのやむを得ない「正当な理由」があるとハローワークに認められた場合は、有利な条件で受給できる可能性があります。
このような制度を正しく理解し活用できれば、賢い退職の第一歩となるでしょう。
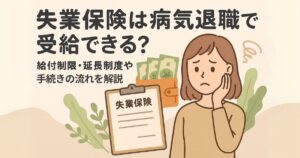
退職後の税金・社会保険で損をしない手続き
退職後は、これまで会社が代行していた税金や社会保険の手続きを、自身でおこなう必要があります。
具体的には、住民税や所得税の支払いのほか、健康保険や年金の手続きが挙げられます。
とくに健康保険には、次の3つの選択肢があり、どれを選ぶかによって月々の保険料が大きく変わるため注意が必要です。
健康保険の選択肢比較
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 任意継続 | 在職時と同じ保険内容を継続できる | 原則2年間、保険料が全額自己負担になる |
| 国民健康保険 | 前年の所得によっては保険料が安くなる場合がある | 自治体や所得によって保険料が大きく変動する |
| 家族の扶養 | 自身の保険料負担がなくなる | 収入などの加入条件が厳しい |
これらの手続きを怠ったり、自身にとって損な選択をしたりすると、あとから大きな出費につながる可能性があります。
退職前にどの手続きが必要で、どの選択肢が自身にとって最も有利なのかを確認しておきましょう。
病気やケガで退職する場合に利用できる制度
病気やケガが原因で退職を考えている場合には、「傷病手当金」と呼ばれる制度を活用できる可能性があります。
傷病手当金とは、健康保険の制度の一つで、病気やケガで働けなくなった場合に生活を保障するためのお金です。
在職中に病気やケガで働けなくなり、一定の条件を満たせば、退職後も継続してもらえます。
ただし、注意点として、失業保険と傷病手当金を同時に受給することはできません。
そのため、自身の体調や今後の回復の見通しを考慮し、どちらの制度を優先して申請するかを慎重に判断する必要があります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
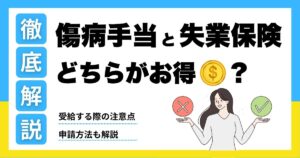
退職に最適なタイミングは存在する|ボーナスや税金を考慮した時期

「いつ退職するか」のタイミングは、もらえる金額や円満な退職の実現に大きく関わる重要な判断です。
ここでは、退職のタイミングを考えるうえで重要な、次の3つの観点を解説します。
- ボーナスをもらってから円満に辞めるタイミング
- 税金や社会保険の負担が軽くなる退職日の設定
- 会社の繁忙期や引き継ぎを考慮した円満な時期
それぞれのポイントを確認します。
ボーナスをもらってから円満に辞めるタイミング
ボーナスを十分にもらってから退職したいと考える方は多いでしょう。
多くの企業では、就業規則に「ボーナスの支給日に在籍していること」を支給条件として定めています。
そのため、ボーナスをもらう前に退職の意思を伝えると、減額や不支給となる可能性があるため注意が必要です。
【図解】ボーナスをもらってから円満に辞めるタイミング
円満に進めやすいタイミング
タイミング①
ボーナス支給
タイミング②
退職の意思を伝える
タイミング③
退職日
減額・不支給の可能性があるタイミング
タイミング①
退職の意思を伝える
タイミング②
ボーナス支給
タイミング③
退職日
最も確実なのは、ボーナスが支給されたあとに、退職の意思を伝えることです。
ボーナスをもらってすぐに退職を切り出すと心証がよくない場合もあるため、支給日から1〜2週間ほど期間を空けると、より円満に進めやすいでしょう。
税金や社会保険の負担が軽くなる退職日の設定
退職日をいつにするかによって、社会保険料や住民税の負担額が変わることがあります。
社会保険料は、月末に在籍しているかどうかでその月の支払い義務が決まります。
日割り計算はされないため、月の途中で辞めるよりも「月末」に退職日を設定する方が、1か月分の保険料を節約できるため有利です。
また、住民税の支払いを考慮すると、年末の12月に退職するか、年始の1月に退職するかで翌年の負担が変わる場合があります。
自身が住んでいる自治体の制度を確認し、最も負担の少ないタイミングを検討しましょう。
会社の繁忙期や引き継ぎを考慮した円満な時期
金銭的な面だけでなく、会社への配慮も円満退職には欠かせません。会社の繁忙期に退職を申し出るのは、できるだけ避けるのがマナーです。
業務が忙しい時期は、上司も退職交渉の時間を十分に取れず、引き継ぎもスムーズに進まない可能性があります。
自身の担当業務の引き継ぎに必要な期間を逆算し、後任者が困らないよう余裕を持ったスケジュールで退職日を設定するのが重要です。
お世話になった会社や同僚へ配慮すれば、結果的に自身の信頼を守り、気持ちよく次のステップへ進めます。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
円満退職を実現する伝え方|上司を納得させる理由と切り出し方

退職の意思を固めても、「どうやって上司に伝えればよいか」と悩む方は少なくありません。
ここでは、円満退職を実現するための伝え方のポイントを3つ解説します。
- 退職の意思を伝える最適な相手とタイミング
- トラブルを避けるための退職理由の伝え方
- これだけは避けたい退職時のNG行動
順番に詳しく解説します。
退職の意思を伝える最適な相手とタイミング
退職の意思は、まず「直属の上司」に直接伝えるのが社会人としてのマナーです。民法では、退職の2週間前までに申し出ればよいとされています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-Gov法令検索
しかし、多くの会社では就業規則で「退職の1〜3か月前」を期限としているため、まずは自身の会社の規則を確認しましょう。
上司に話を切り出す際は、メールや口頭などで「相談したいことがあるのですが、お時間をいただけないでしょうか」とアポイントを取るのが丁寧です。
そして、会議室をはじめとした他の人に聞かれない場所で、退職の意思をはっきりと丁寧な言葉で伝えましょう。
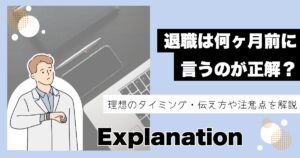
トラブルを避けるための退職理由の伝え方
退職理由は、伝え方を間違えると、強い引き止めやトラブルの原因になることがあります。
給与や人間関係など、会社への不満が本当の理由であっても、それをストレートに伝えるのは避けるのが賢明です。
ネガティブな理由は、改善を提案されて引き止められやすくなるだけでなく、職場の雰囲気を悪くする可能性もあります。
基本的には「一身上の都合」で問題ありませんが、もし詳しく聞かれた場合は、前向きで個人的な理由を伝えると、上司も納得しやすく、応援してもらいやすいでしょう。
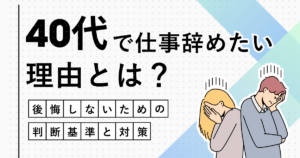
これだけは避けたい退職時のNG行動
円満な退職のためには、避けるべき行動があります。
最も注意すべきなのは、直属の上司に伝える前に、同僚や他部署の方に退職の話をしてしまうことです。
噂が先に上司の耳に入ってしまうと、管理能力を問われることになり、心証を大きく損ねます。
また、十分な引き継ぎをおこなわずに辞めることも絶対に避けましょう。会社に損害を与えたと判断された場合、トラブルに発展するリスクもあります。
会社の備品や機密情報を持ち出さないといった、基本的なルールを守ることも重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
退職を決意してから完了までのロードマップ|具体的な手順とスケジュール

退職を決意してから、実際にすべての手続きが完了するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
ここでは、退職の意思決定から退職後の手続きまでを5つのステップに分けて解説します。
【図解】退職を決意してから完了までのロードマップ
-
意思決定と上司への報告
退職の意思を固め、就業規則を確認。直属の上司にアポイントを取り、退職の意思を伝えます。
-
退職日の決定と退職届の提出
上司と相談の上、正式な退職日を決定。会社の規定に従って「退職届」を提出します。
-
業務の引き継ぎと挨拶回り
後任者が困らないよう、スケジュールを立てて丁寧に業務を引き継ぎ。お世話になった方への挨拶も行います。
-
最終出社日と書類の受け取り
備品を返却し、会社から離職票や源泉徴収票など、退職後の手続きに必要な重要書類を受け取ります。
-
退職後の各種手続き
役所で健康保険・年金の手続きを行います。失業保険を受給する場合はハローワークで申請します。
ステップ1:退職意思の決定と上司への報告
まずは、退職の意思を固め、就業規則を確認したうえで直属の上司に報告します。
これは会社のルールを守り、無用な混乱や憶測を防ぐための重要なマナーです。
退職希望日は、引き継ぎ期間などを考慮して2〜3か月先を目安に設定するとよいでしょう。
コツとしては、事前に「キャリアプランについてご相談したいのですが」とアポイントを取っておくと、上司も心の準備ができスムーズです。
ステップ2:退職日の決定と退職届の提出
次に上司との面談で、正式な退職日を決定します。退職日が確定したら、会社の規定に従って「退職届」を提出します。
これは、退職する明確な意思を記録として残し、「言った言わない」のトラブルを避けるために重要です。
口頭での合意だけでなく書面で提出すれば、手続きが正式なものとしてスムーズに進みます。
ステップ3:業務の引き継ぎと挨拶回り
後任者や関係部署に迷惑がかからないよう、責任を持って業務の引き継ぎをおこないます。
丁寧な引き継ぎは、円満退職の鍵であり、自身の社会人としての信頼性を担保するものです。
引き継ぎのスケジュールを作成し、誰が見ても分かるような資料を準備しておくと、非常に親切です。
最終出社日が近づいたら、お世話になった方々への挨拶も忘れずにおこないましょう。
ステップ4:最終出社日と書類の受け取り
最終出社日には、健康保険証や社員証、制服などを会社に返却します。
また、退職後の手続きなどに必要な「離職票」や「源泉徴収票」といった重要書類がいつ頃届くのか確認しておくと安心です。
離職票や源泉徴収票は退職してから、自宅に郵送されるケースが一般的です。
これらの書類は退職後の生活に不可欠なため、受け取り漏れがないよう必ず確認してください。
ステップ5:退職後の各種手続き
退職後は、速やかに市区町村の役所で健康保険や年金の手続きをおこないます。
これらの手続きには期限が設けられているものが多く、遅れると不利益を被る可能性があります。
失業保険を受給する場合は、住所を管轄するハローワークで申請手続きを進めます。
退職前に必要書類や手続きの場所をリストアップしておくと、スムーズに行動できるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
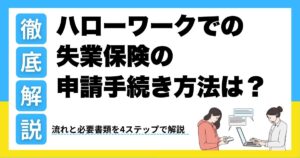
退職手続きの不安を解消するなら専門家の活用がおすすめ
ここまで賢い退職の仕方について解説してきましたが、制度が複雑で、一人ですべてを完璧に進めるのは難しいと感じる方もいるのではないでしょうか。
そのようなときに頼りになるのが、退職給付金申請の専門家です。
専門家のサポートを活用するメリットを具体的に紹介します。
「退職バンク」なら失業保険の受給額を最大化できる
専門家のサポートを受ける最大のメリットは、失業保険の受給額を最大化できる可能性があることです。
退職給付金申請サポートサービスの「退職バンク」では、専門的な知見を活かして、自身の状況に最も有利な申請方法を提案します。
通常の申請では数十万円程度だった受給額が、サポートによって最大200万円まで増額した事例もあります。
自身では気づかなかった「正当な理由」を見つけ出し、給付制限なくスムーズに受給を開始できる可能性もあるでしょう。
たとえば、30代の事務職の女性が「退職バンク」のサポートを利用し、180万円の給付金を10か月にわたって受給したケースも報告されています。
面倒な手続きも専門家が徹底サポート
「退職バンク」は、退職時に発生する複雑で面倒な手続きを、専門家が徹底的にサポートします。
社会保険労務士が監修する体制で、ハローワークでの複雑な申請手続きや、会社との書類のやり取りまで、スムーズに進むよう支援します。
退職後の生活に不安を抱えている方からの豊富な相談実績があり、安心して任せる点が魅力です。
やり取りはすべてオンラインで完結するため、全国どこに住んでいる方でも利用できます。
また、チャットでいつでも気軽に相談できるため、退職に関する知識がまったくない方でも、不安なく手続きを進められるでしょう。
まずはLINEで無料の受給額診断からはじめる
専門家のサポートに興味はあるけれど、費用が心配と考える方もいるでしょう。
「退職バンク」では、実際に自身がいくら受給できる可能性があるのかを、LINEで簡単に無料診断できます。
友だち追加後、いくつかの質問に答えるだけで、最短30秒で受給額の目安がわかり、診断やその後の相談はすべて無料です。
無理な勧誘も一切ないため、まずは自身の可能性を知るために、気軽に試してみてはいかがでしょうか。
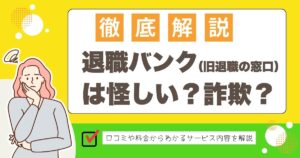
賢い退職に関するQ&A

ここでは、賢い退職に関して多くの方が抱える疑問について、Q&A形式で回答します。
細かい疑問を解消し、安心して退職準備を進めましょう。
有給休暇が残っている場合はどうすればよいですか?
残っている有給休暇を消化するのは、労働基準法で認められた労働者の権利です。
そのため、会社は原則として有給休暇の取得を拒否できません。
退職日までの出勤日数を考慮し、業務の引き継ぎ期間と調整しながら、計画的に消化するスケジュールを上司に相談しましょう。
最終出社日以降に有給休暇を充て、退職日を先延ばしにする方法が一般的です。
会社によっては買い取りに応じてくれる場合もありますが、義務ではないため、まずは就業規則を確認し、上司に相談するのをおすすめします。
退職届と退職願の違いや書き方を教えてください
「退職願」と「退職届」は、提出する目的とタイミングが異なります。
「退職願」は、「退職させてください」とお願いを会社に申し出るための書類で、会社が受理するまでは撤回が可能です。
一方、「退職届」は、退職する意思を通知する書類であり、一度提出すると原則として撤回できません。
書き方に厳密なルールはありませんが、必要な項目を記載したシンプルなテンプレートに沿って作成すれば問題ありません。
どうしても退職を認めてもらえない場合はどうすればよいですか?
退職は労働者の自由であり、会社の承認がなくても、民法では退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定められています。
強い引き止めや、退職を認めないといった対応をされた場合は、内容証明郵便で「退職届」を会社に送付する方法が有効です。
これは、退職の意思を明確に伝えた法的な証拠になります。
それでも解決しない場合は、退職代行サービスを利用したり、各都道府県の労働局など、公的な相談窓口に相談したりするのも検討しましょう。
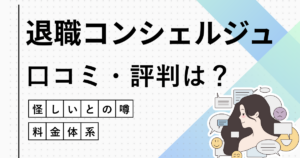
在職中の転職活動はどのくらい進めておくべきですか?
在職中の転職活動は、自身の状況や精神的な余裕によりますが、退職後の生活を考えると、ある程度進めておくと安心です。
理想は、退職前に次の就職先から内定を得ていることです。しかし、現職が忙しく転職活動に時間を割けない方もいるでしょう。
その場合は、無理に転職先を決めずに退職し、失業保険を活用しながらじっくりと活動するのも一つの賢い方法です。
退職代行サービスはどのように選べばよいですか?
退職代行を利用してトラブルなく確実に退職するためには、信頼できるサービスを選ぶことが非常に重要です。
サービスを選ぶ際は、弁護士が監修または運営しているか、料金体系が明確であるか、過去の実績が豊富であるか、といった点を確認しましょう。
詳しい選び方やおすすめのサービスについては、別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。
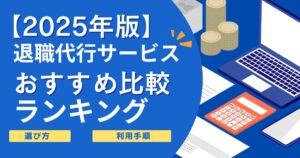
会社から受け取るべき書類は何ですか?
退職時には、その後の手続きに必要となる重要な書類を会社から受け取る必要があります。
退職時に受け取るべき書類リスト
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 年金手帳
これらの書類は、退職後の生活や次のキャリアへの移行をスムーズに進めるために不可欠です。
万が一、会社から交付されない場合は、速やかに発行を依頼しましょう。
もし対応してもらえない場合は、ハローワークや年金事務所に相談してください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ

本記事では、退職で後悔しないための「賢い退職の仕方」について、お金・タイミング・伝え方といった3つの重要な観点から網羅的に解説しました。
賢い退職の実現には、失業保険や税金などのお金の知識を身につけ、自身の状況にあわせて最適な行動を計画的に実行する必要があります。
退職にまつわる不安の多くは、正しい情報を知ることで解消できます。
退職に関する最終的な判断は、専門家である当サイトの情報を参考に、自身にとって最適な選択をしてください。
もし、一人での手続きに少しでも不安を感じる場合は、専門家のサポートを受けることも有力な選択肢です。
より詳細な情報は、退職給付金申請サポート「退職バンク」で検索し、無料診断から試してみてはいかがでしょうか。
もう一人で悩まない!
退職給付金のことはプロにお任せ
ここまで読んで「やっぱり制度が複雑で難しい…」と感じたあなたへ。
一番の近道は、専門家に相談することです。
-
受給額の
最大化を支援 -
面倒な手続きを
徹底サポート -
専門家にいつでも
チャットで相談