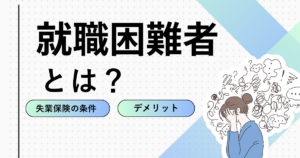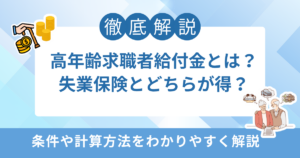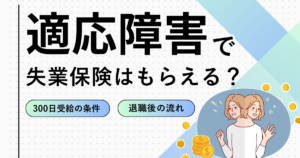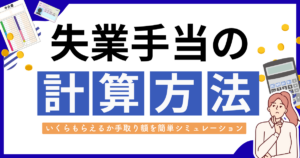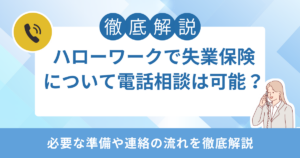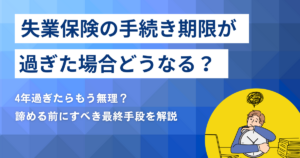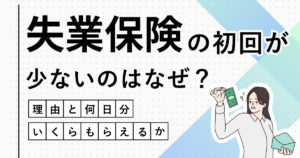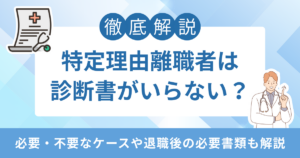65歳以上でも失業保険はもらえる?受給条件・計算方法・年金と同時に受け取れるか解説
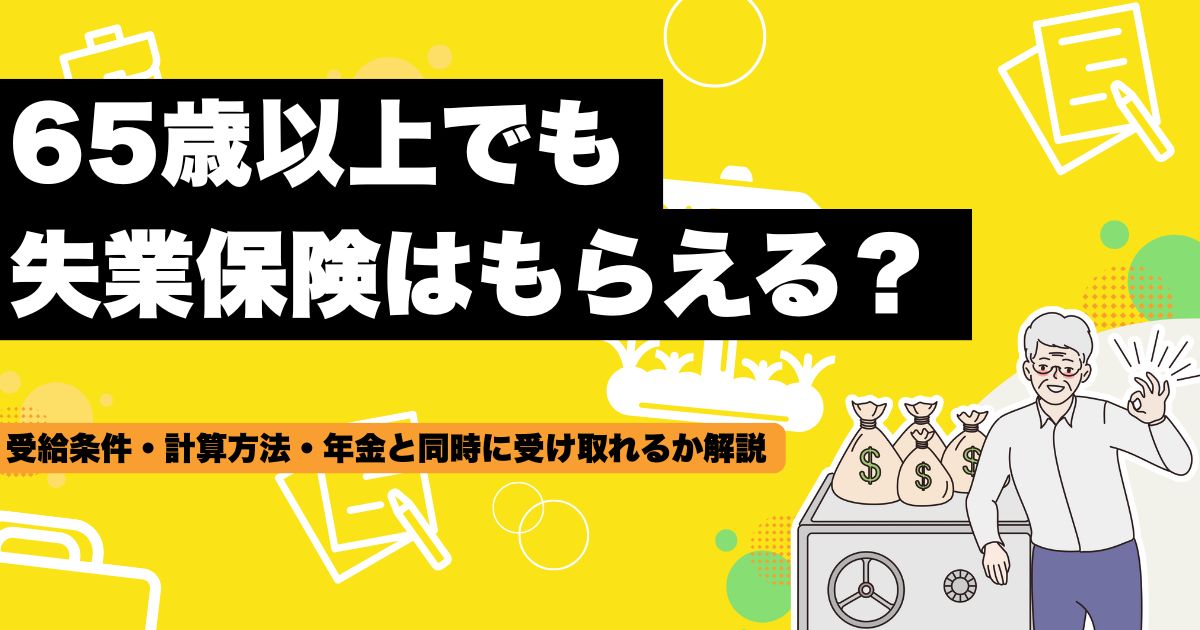
65歳を迎え定年退職などを控えたとき、「退職後の生活費は大丈夫だろうか」「失業保険はもらえるのか」といった経済的な不安を感じる方は少なくありません。
とくに、65歳を境に制度がどう変わるのか、年金と同時に受け取れるのかは、多くの方が抱く疑問です。
結論として、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」を年金と同時に受け取ることが可能です。
この記事では、65歳以上で受け取れる給付金の受給条件や具体的な計算方法、64歳で退職した場合との違いをわかりやすく解説します。
【結論】65歳以上の失業保険は年金と同時にもらえる「一時金」

65歳を過ぎて退職を考えたとき、「失業後の生活費はどうなるのだろう」という不安は誰にでもあるものです。
実は、65歳以上で退職した場合でも、雇用保険から生活を支える給付金を受け取ることが可能です。
これは一般的に知られる失業保険とは少し性質が異なりますが、退職後の経済的な安心につながる大切な制度です。
ここでは、65歳以上の方が受け取れる給付金の基本と、年金との関係性について詳しく解説します。
65歳以上で退職した場合にもらえる「高年齢求職者給付金」とは
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険の被保険者が退職した場合に受け取れる手当のことです。
一般的に「失業保険」といわれるものは64歳までの方が対象の「基本手当」を指しますが、この給付金は実質的に65歳以上の方のための失業手当と考えるとよいでしょう。
この制度の目的は、退職された方の生活を安定させ、安心して次の仕事を探すための準備期間を経済的に支えることにあります。
長年雇用保険に加入してきた方が、その権利として活用できる心強い支援制度となります。
64歳までの失業保険(基本手当)との明確な違い
65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金と、64歳までが対象の基本手当には明確な違いがあります。
最も大きな違いは支給方法です。
基本手当が再就職が決まるまで原則月1回ずつ分割で支払われるのに対し、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されます。
また、給付される日数も異なります。
基本手当は雇用保険の加入期間に応じて最大150日分ですが、高年齢求職者給付金は最大でも50日分となります。
そのため、再就職が決まった際に支給される再就職手当の対象にはならない点も覚えておきましょう。
年金と同時に受け取れるので安心
退職後の収入で最も気になるのが年金との関係でしょう。この点で、65歳以上で退職することには大きなメリットがあります。
64歳までの方が受け取る基本手当は、特別支給の老齢厚生年金と同時に受け取ることはできず、年金の支給が調整されます。
しかし、65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金は、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同時に、満額ずつ受け取ることが可能です。
年金収入を減らすことなく、まとまった給付金を得られることは、退職後の生活設計において非常に大きな安心材料となるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
高年齢求職者給付金の受給額は賃金日額と給付率で決まる

高年齢求職者給付金を実際にいくら受け取れるのかは、退職後の生活設計を立てる上で最も重要な情報の一つです。
受給額は、退職前の給与額を基に計算される「賃金日額」と、それに応じて定められた「給付率」によって決まります。
ここでは、給付金を受け取るための具体的な条件から、自身の受給額を計算する方法、そして知っておくべき上限額までを一つひとつ丁寧に解説します。
受給するために満たすべき2つの条件
高年齢求職者給付金を受け取るためには、主に2つの条件を満たす必要があります。
満たすべき条件
- 離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること
- 働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない「失業の状態」にあること
一つ目の条件は、雇用保険に一定期間加入していた実績です。二つ目は、現在仕事を探している状態であることの証明となります。
たとえば、定年退職後、心身の休養のためにしばらく休んでから求職活動をはじめようと考えている場合でも、ハローワークで求職の申し込みをすれば「失業の状態」と認められ、対象となります。
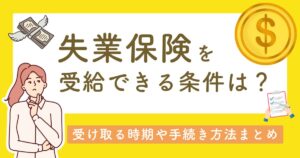
給付金の具体的な計算方法とシミュレーション
自身の受給額を知るための計算は、以下の3つのステップで進められます。
- ステップ1:賃金日額を算出する
└ 離職前6か月間に支払われた賃金の合計を180で割り「賃金日額」を求める - ステップ2:基本手当日額を決定する
└賃金日額に年齢に応じた給付率(約50〜80%)を掛けて「基本手当日額」を算出する - ステップ3:受給総額を計算する
└ 基本手当日額に「所定給付日数」を掛けて受け取れる給付金の総額を計算する
たとえば、退職前6か月の月収が平均30万円だった場合、総額でおよそ20万円から25万円程度が支給される計算となるでしょう。
受給額の上限と下限について
高年齢求職者給付金の計算の基礎となる賃金日額と、1日あたりの支給額である基本手当日額には、それぞれ上限額と下限額が法律で定められています。
これは、給与が低い方の給付額が少なくなりすぎないように、また高収入だった方の給付額が際限なく増えないようにするための仕組みです。
この上限額と下限額は、毎年8月1日に「毎月勤労統計」という国の調査結果に基づいて見直されます。
そのため、最新の情報を確認することが大切です。
自身の給与が高かった場合でも、必ずしもそれに比例して給付額が増え続けるわけではない点を理解しておきましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
64歳・65歳で退職するなら「総受給額」で有利な方を選ぶ
退職のタイミングは、その後の人生設計に大きな影響を与えます。
とくに65歳を目前に控えている方にとって、「64歳のうちに辞めるべきか、65歳になってから辞めるべきか」は非常に悩ましい問題でしょう。
それぞれの選択肢にはメリットとデメリットが存在します。
自身の状況や退職後のプランにあわせて、どちらがより有利な選択となるのかを慎重に比較検討することが重要です。
| 比較項目 | 64歳で退職 (基本手当) | 65歳で退職 (高年齢求職者給付金) |
|---|---|---|
| 支給方法 | 分割払い(月1回など) | 一時金(一括) |
| 給付日数 | 最大150日分 | 最大50日分 |
| 年金との関係 | 併給調整あり(年金が停止) | 併給調整なし(両方満額) |
| 給付制限 | 自己都合は約1〜3か月の待機期間あり | 自己都合でも待機期間なし |
64歳で退職するメリットとデメリット
64歳で退職し、基本手当を受給する選択には、メリットとデメリットの両方があります。
最大のメリットは、給付日数が最大150日と長く、総受給額が高くなる可能性があることです。
月々の安定した収入を得ながら、じっくりと次のキャリアを探す時間的な余裕が生まれます。
一方でデメリットは、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる年齢の場合、基本手当の受給中は年金の支給が停止される点です。
手厚い失業給付を受けながら時間をかけて再就職活動をしたい方にとっては、有利な選択肢となるでしょう。
65歳で退職するメリットとデメリット
65歳で退職し、高年齢求職者給付金を受け取る場合にも、メリットとデメリットが存在します。
こちらの最大のメリットは、老齢年金を満額受け取りながら、給付金も同時に受給できる点です。
また、給付金は一時金として一括で振り込まれるため、まとまった資金を早期に確保できます。
一方、デメリットとしては、給付日数が最大50日と短く、64歳退職の場合と比較して総受給額が少なくなる可能性が挙げられます。
年金収入を確保しつつ、速やかにまとまったお金を受け取って次のステップへ進みたい方に適した選択肢といえるでしょう。
参考記事)
定年後におすすめの資格を解説!│正直キャリアコンサルタント・パオ助のブログ
どちらが得か判断するためのチェックポイント
最終的にどちらのタイミングで退職するのが得策か、判断に迷う方も多いでしょう。その際は、自身の状況をいくつかの視点から整理することをおすすめします。
まず、雇用保険の加入期間は十分にあるかを確認しましょう。
次に、退職後にすぐ再就職したいのか、あるいは少し休んでから活動したいのか、自身の希望を明確にすることが大切です。
また、年金と失業手当の総受給額がどうなるかをシミュレーションしてみるのも有効です。
しかし、これらの点を総合的に考慮しても判断が難しいものです。
とくに年金との総額比較は複雑な計算が必要なため、一人で悩むと「気づかずに損をする」可能性も否定できません。
後悔しない選択をするためにも、「退職バンク」のような専門家に相談し、自身の状況で最も有利になるプランを立ててもらうのが賢明な選択です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
高年齢求職者給付金の申請方法と必要書類

高年齢求職者給付金を受け取るための手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークでおこないます。
複雑そうに感じるかもしれませんが、事前に必要書類と全体の流れを把握しておけば、スムーズに進めることが可能です。
ここでは、申請に必要なものから、手続きの具体的なステップ、そして自己都合で退職した場合の注意点までをわかりやすく解説します。
申請手続きに必要な書類一覧
ハローワークで手続きをおこなう際には、事前にいくつか準備すべき書類があります。
主な必要書類
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)
- マイナンバーカード(または通知カードと運転免許証など)
- 証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 印鑑
この中で最も重要なのが、退職した会社から受け取る「雇用保険被保険者離職票」です。
通常、退職後10日ほどで自宅に郵送されます。もし届かない場合は、会社に確認しましょう。
その他の書類も、あらかじめ手元に揃えておくことで、ハローワークでの手続きを一度で円滑に終えることができます。
【3ステップで解説】申請から受給までの具体的な流れ
高年齢求職者給付金の申請から受給までは、大きく3つのステップで進みます。
- ハローワークで申し込みと書類提出
- 待機期間の終了後、失業認定を受ける
- 認定後、給付金が一括で振り込まれる
まずは、必要書類を持って、住所地を管轄するハローワークで求職の申し込みと書類の提出を行います。
続いて、7日間の待機期間が終わったら、指定された日にハローワークで失業認定を受けます。これは、働く意思があることを確認するための手続きです。
認定されると、1週間ほどで指定口座に給付金が一括で振り込まれます。
自己都合退職の場合の注意点
自己都合で退職した場合、給付金の扱いに違いがあるのか気になる方もいるでしょう。
64歳までの基本手当の場合、自己都合で退職すると7日間の待機期間に加えて、さらに約1か月または3か月の給付制限期間が設けられ、すぐには手当を受け取れません。
しかし、65歳以上で受け取る高年齢求職者給付金には、この給付制限がありません。
これは大きなメリットといえます。
つまり、定年や会社都合だけでなく、自身の意思で退職した場合でも、7日間の待機期間が明ければ速やかに給付金を受け取ることが可能です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【専門家に相談】退職バンクなら失業保険の受給を徹底サポート
ここまで解説してきたように、65歳以上の失業保険制度は複雑で、自身の状況によって最適な選択は異なります。
「自身にとって一番有利な方法はどれだろう」「手続きで損をしたくない」と感じる方も少なくないでしょう。
そのようなときに頼りになるのが、退職と失業保険の専門家です。
専門サービスを活用することで、不安を解消し、よりよい条件で次のステップへ進むことが可能です。
退職の専門家が最適な受給プランを提案
「退職バンク」は、失業保険の申請を専門家がサポートするサービスです。
社会保険労務士といった退職手続きのプロが、利用者一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングします。
退職理由や勤続年数、過去の給与額といった情報に基づき、最も有利に給付金を受け取れるようなプランを個別に提案します。
これは、一般的な情報提供が中心の公的機関ではなかなか得られない、パーソナルなサポートです。
専門家の知見を借りることで、自身では気づかなかったような最適な選択肢を見つけられる可能性があります。
複雑な手続きの手間を省き受給額の最大化を目指せる
退職バンクを利用する大きなメリットは、複雑な制度の理解や面倒な書類準備といった手間を大幅に軽減できる点です。
専門家がハローワークとのやり取りを含めてサポートするため、利用者は安心して手続きを任せられます。
さらに、専門的なノウハウを活用して受給額の最大化を目指せるのも魅力です。
自身で手続きした場合の一般的な受給額が30万円から50万円程度であるのに対し、サポートを受けることで最大200万円という高額な受給を実現した実績もあります。
最短1か月での早期受給も可能になるため、経済的な安心をいち早く手に入れることにもつながります。
無料のLINE相談から始められる手軽さ
「専門家に相談するのはハードルが高い」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、「退職バンク」では、サービス利用の第一歩として、LINEを使って気軽に無料相談をはじめられます。
簡単な質問に答えるだけで、「自身がいくら失業保険をもらえそうか」という受給想定額を無料で診断してもらうことが可能です。
相談はすべてオンラインで完結するため、全国どこにお住まいの方でも利用できます。
まずは自身の可能性を知るために、この手軽な無料診断から試してみることをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
65歳以上の失業保険に関するよくある質問

65歳以上の失業保険、すなわち高年齢求職者給付金について、多くの方が抱く共通の疑問があります。
ここでは、とくに質問の多い点について、Q&A形式でわかりやすく回答します。
70歳以上で退職した場合はどうなりますか
70歳以上で退職された場合は、「高年齢求職者給付金」の対象とはなりません。
その代わり、「高年齢雇用継続被保険者」として雇用保険に加入していた方が対象となる「特例一時金」という制度があります。
この特例一時金は、65歳から69歳までの間に雇用保険の被保険者でなかった期間があるなど、一定の条件を満たした場合に支給されるものです。
高年齢求職者給付金とは受給要件や給付内容が異なりますので、自身が該当するかどうかは、ハローワークで確認することをおすすめします。
失業保険(給付金)に税金はかかりますか
高年齢求職者給付金をはじめ、雇用保険から支給されるすべての手当は非課税です。
これは、失業中の生活を保障するという制度の趣旨に基づいています。したがって、受け取った給付金に対して所得税や住民税が課されることはありません。
また、課税対象の所得ではないため、確定申告も不要です。これは、退職金や年金など他の収入とは扱いが異なる重要なポイントです。
パートやアルバイトでも受給できますか
高年齢求職者給付金は、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態の方でも受給可能です。
重要なのは雇用形態ではなく、「雇用保険に加入しているか」そして「受給資格を満たしているか」の2点です。
雇用保険の加入条件は、主に「1週間の所定労働時間が20時間以上である点」などが挙げられます。
自身がこれらの条件を満たしていれば、パートやアルバイトとして働いていた場合でも、退職後に給付金を受け取る権利があります。
まずは自身の雇用契約や給与明細で、雇用保険への加入状況を確認してみましょう。

65歳を過ぎて働き続ける場合雇用保険に入り続けるメリットは?
65歳を過ぎても働き続ける場合、雇用保険に加入し続けることにはメリットとデメリットの両方があります。
最大のメリットは、将来退職した際に「高年齢求職者給付金」を受け取る権利を維持できる点です。
また、万が一、家族の介護のために休業が必要になった場合には「介護休業給付金」の対象にもなります。
一方で、デメリットは、在職中は給与から雇用保険料が引かれ続けるという点です。
これらの点を考慮し、自身の働き方やライフプランにあわせて総合的に判断することが大切です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ:65歳からの失業保険は年金と併給可能|最適な選択で安心な老後へ
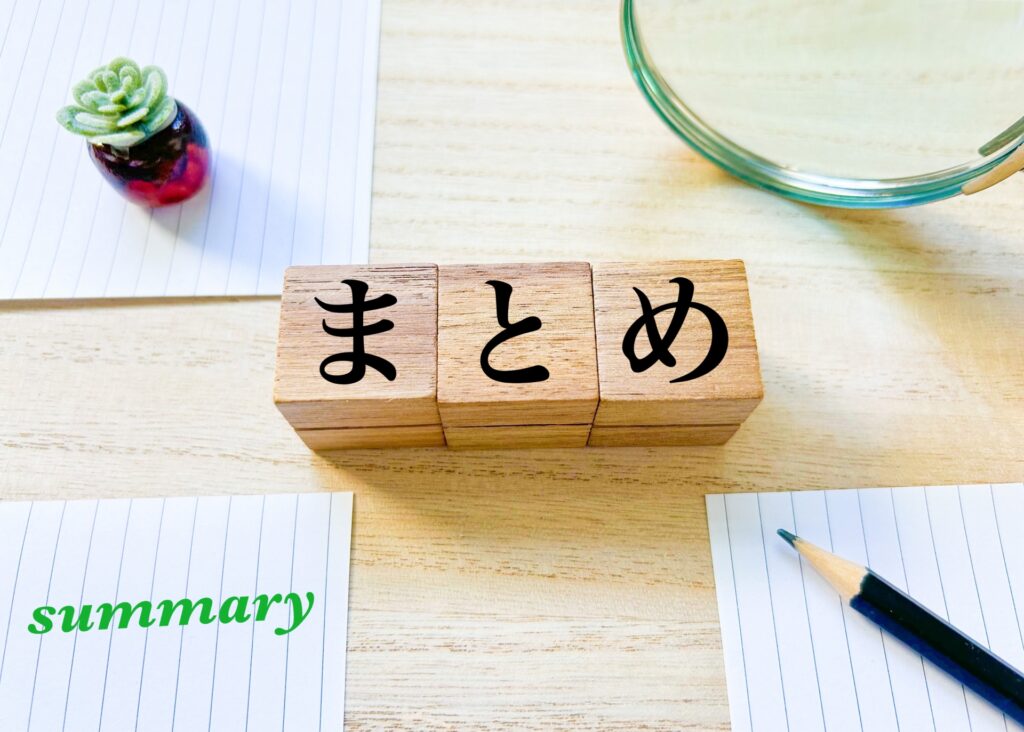
この記事では、65歳以上で退職した場合に受け取れる失業手当「高年齢求職者給付金」について、受給額の計算方法や年金との関係性を中心に解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 65歳以上で受け取る「高年齢求職者給付金」は年金と同時に満額受給できる
- 給付金は「一時金」として一括で支給され、支給日数は最大50日分となる
- 64歳までに退職した場合と比べてメリット・デメリットがあるため自身の状況にあわせた慎重な判断が求められる
退職のタイミングは、その後の生活に大きく影響します。
制度を正しく理解し、自身のライフプランにあった選択をすることが、経済的な不安を解消し、安心して次のステップへ進むための鍵となります。
判断に迷う場合は、「退職バンク」のような専門家に相談し、最適なプランを見つけるのも一つの有効な手段です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /