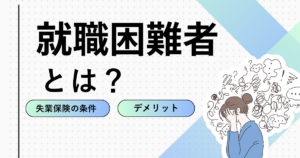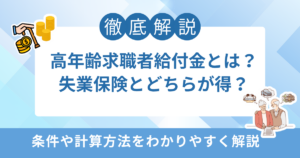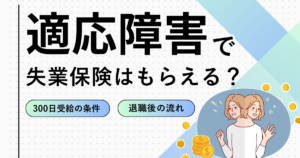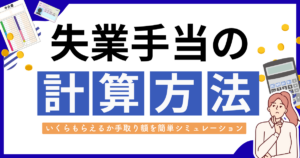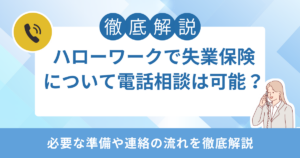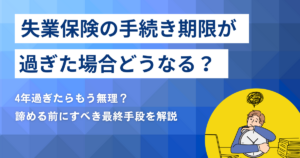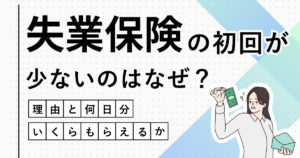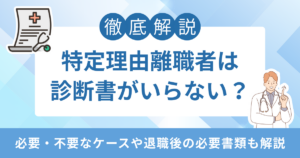ボーナスをもらって辞めることは可能?最適なタイミングと円満退職の注意点
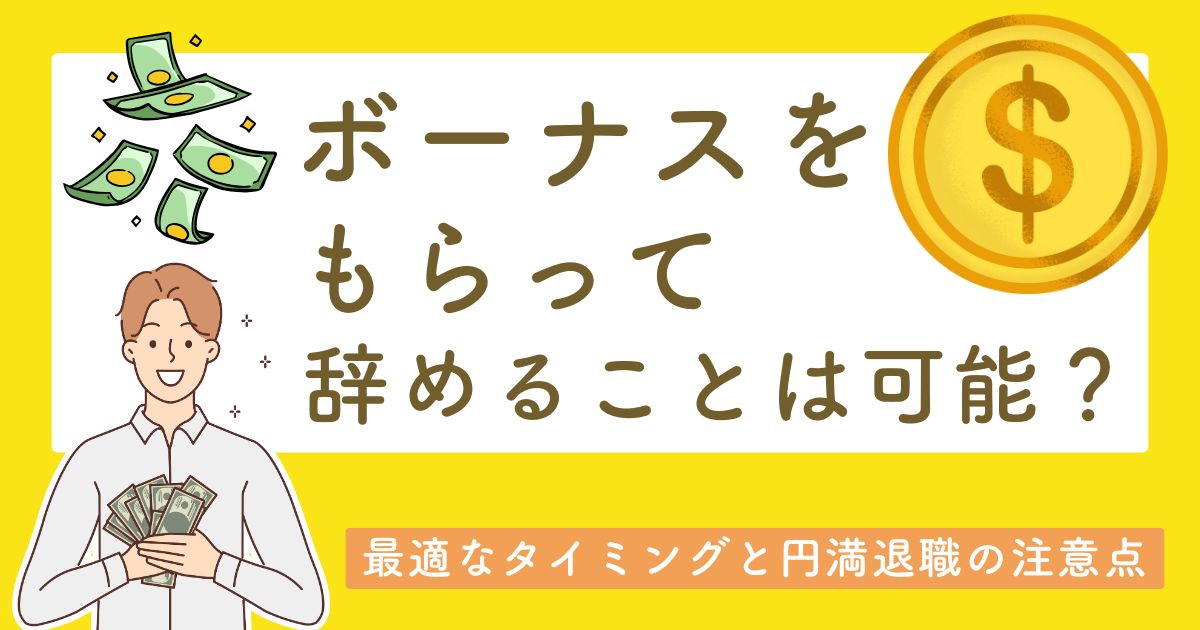
退職を考える際、ボーナスを一つの区切りとすることは自然な選択肢です。
しかし、実際にボーナスをもらってすぐに辞めても問題ないのか、いつ退職を伝えるとよいのかと疑問を抱く方も多いでしょう。
結論として、ボーナスを受け取ってから退職することは法的に可能です。しかし、損をせずに退職するためには、注意点を押さえることが大切です。
本記事では、ボーナスを確実に受け取るための法的な知識や就業規則の確認ポイントを解説します。
さらに、円満退職を実現するための具体的なスケジュールや上司への伝え方まで紹介します。
これから退職を考えている方、最適なタイミングを知りたい方は、記事を参考に手続きしてみてください。
最適なタイミングは支給日以降です
【結論】ボーナスをもらってから辞めることは可能!最適なタイミングは支給日以降
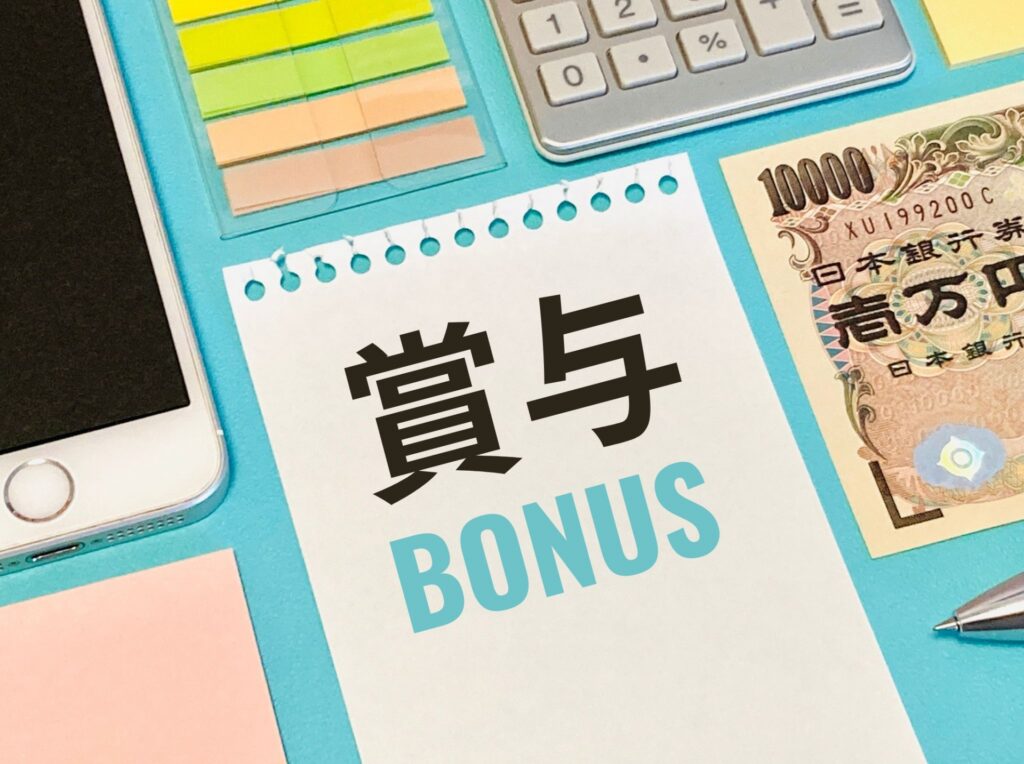
ボーナスをもらって退職したいと考えたとき、そもそも法的に問題ないのか、辞めるのはいつがよいのかといった疑問を抱くかもしれません。
結論からいうと、ボーナスをもらってから辞められます。
しかし、ボーナスをもらってから退職する場合、次の項目の理解が欠かせません。
- ボーナス支給後の退職に関する法的な見解
- 退職を伝える最適なタイミング
- ボーナスをもらって辞める際の基本的な流れ
ここからは、それぞれの項目について詳しく解説します。
ボーナスをもらって辞めても法的に問題ない理由
結論として、ボーナス、すなわち賞与を受け取った後に退職することは、法的に問題ありません。
なぜなら、ボーナスは一般的に過去の労働に対する対価と解釈されるためです。
したがって、すでに支払われたボーナスを会社に返す法的な義務は原則として発生しません。
参照元:e-Gov 労働基準法
最も確実なタイミングはボーナス支給日に振り込みを確認した直後
ボーナスを確実に受け取ってから退職を伝える最も安全なタイミングは、ボーナスの支給日に振り込みを確認した直後です。
支給日より前に退職の意思を伝えると、会社の評価制度や上司の判断によっては、査定に影響が出て減額されたり、最悪の場合は不支給になったりするリスクが考えられます。
実際に支給日の2週間前に退職を伝えたところ、ボーナスが想定より大幅に減額されてたケースがありました。
満額を受け取るためには、必ず口座への着金を確認してから次の行動に移すことが大切です。
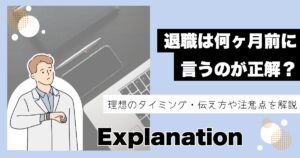
ボーナスをもらって円満退職するまでの基本的な4つのステップ
ボーナスを受け取って円満に退職するためには、計画的に手順を踏むことが重要です。
基本的な流れは、次の4つのステップで進めるとスムーズです。
全体の流れを把握すれば、焦らず落ち着いて退職準備を進められます。
ボーナスを満額もらうために退職前に必ず確認すべき3つの注意点

ボーナスを確実に満額受け取るためには、いくつかの注意点があります。
次の3つのポイントは、必ずチェックしておきましょう。
- 就業規則の「支給日在籍要件」の有無
- 退職を伝えるタイミングと減額リスク
- 自身のボーナスの査定期間
それでは、それぞれの注意点について具体的に解説します。
会社の就業規則にある支給日在籍要件の有無
ボーナスがもらえるかどうかを左右する最も重要なルールが、就業規則に定められた「支給日在籍要件」です。
支給日在籍要件とは、ボーナス支給日に会社に在籍している従業員に対してのみボーナスを支払うという決まりのことです。
要件がある場合、たとえ支給日の前日に退職しても、ボーナスを受け取る権利がなくなってしまいます。
退職計画を立てる前に、まず自社の就業規則を確認し、要件の有無を把握することが不可欠です。
退職を伝えるタイミングを間違えると減額される可能性
ボーナスを満額受け取るためには、退職を伝えるタイミングが重要になります。
ボーナス支給前に退職の意向を伝えた場合、その後の賞与査定で不利な評価を受け、結果として支給額が減額される可能性があります。
企業の評価制度や上司の裁量に左右される、現実的なリスクといえるでしょう。
退職予定者への評価が他の社員と同じ基準でおこなわれるとは限ません。
満額のボーナスを確実に受け取ることを最優先に考えるならば、退職の申し出はボーナス支給後におこなうとよいでしょう。
自身のボーナス査定期間はいつからいつまでか
ボーナスは、特定期間の働きぶりを評価して支給される賃金です。
査定期間に在籍していることが、支給の前提条件となります。
たとえば、夏のボーナスは前年の10月から当年3月までの働きが、冬のボーナスは当年4月から9月までの働きが評価対象となります。
査定期間の途中で入社したり、期間中に在籍していなかったりすると、支給対象外となったり減額されたりする場合があります。
自身のボーナス査定期間がいつなのか、就業規則を確認したり、人事に問い合わせたりするなどして正確に把握しておきましょう。
「やることリスト」
- 就業規則の「支給日在籍条項」を確認したか?
- 自分のボーナスの査定期間を把握しているか?
- 退職を伝えるのは、ボーナスの振込を確認した後か?
- 有給休暇の残日数を計算して、退職日を計画したか?
- 退職後の失業保険について、専門家への相談を検討したか?
円満退職を実現するボーナスをもらうための退職完全スケジュールと伝え方

ボーナスを確実に受け取って円満に退職するためには、計画的なスケジュール管理と適切なコミュニケーションが欠かせません。
ここでは、具体的なスケジュール例や上司への伝え方について解説します。
- 夏・冬のボーナス時期にあわせた退職スケジュール例
- 有給休暇をすべて消化するための退職日の設定方法
- 上司に納得してもらうための退職理由の伝え方
それぞれの内容を詳しく解説します。
夏と冬のボーナス時期から逆算する退職スケジュール例
計画的に退職を進めるためにも、ボーナスの支給時期から逆算してスケジュールを立てましょう。
夏のボーナスと冬のボーナス、それぞれの一般的なモデルケースを紹介します。
自身の会社の就業規則や引き継ぎにかかる期間を考慮して、余裕をもったスケジュールを立てましょう。
有給休暇の残日数から退職日を決める方法
退職時には、残っている有給休暇をすべて消化する権利があります。
退職日を決める際は、有給休暇の残日数を考慮することが大切です。
民法上、退職の申し出は退職日の2週間前までとされていますが、会社の就業規則では1か月前までなどと定められている場合があります。
まずは就業規則を確認し、必要な引き継ぎ期間を上司と相談した上で、残りの期間で有給休暇を消化できるよう退職日を設定しましょう。
たとえば、申し出から退職日までが1か月あり、引き継ぎに2週間、有給休暇が10日残っている場合、スムーズにすべての権利を行使できます。
参照元:e-Gov 民法
【例文あり】上司への退職の伝え方と円満退職のコツ
退職の意思を上司に伝える際は、伝え方一つでその後の関係性が大きく変わります。
円満退職を目指すためのポイントと具体的な例文を確認しておきましょう。
「相談したいことがあります」とアポイントを取り、会議室など他人に聞かれない場所で直接話しましょう。
退職理由は一身上の都合で問題ありませんが、もし尋ねられた場合は、会社の不満ではなく、ポジティブな理由を伝えるとよいでしょう。
【例文】
お時間をいただきありがとうございます。突然の連絡で申し訳ありませんが、一身上の都合により、来月末で退職させていただきたく、相談に参りました。新しい分野に挑戦したいと考えており、退職を決意いたしました。最終出社日まで責任をもって業務を全うし、引き継ぎをおこないます。
感謝の気持ちと最後まで責任を果たす姿勢を示すことが、円満退職のための大切なポイントです。
【次のステップへ】ボーナスと失業保険で退職後の生活を万全にする方法

ボーナスを無事に受け取れたとしても、退職後の生活に不安を感じる方は少なくないでしょう。
転職活動が長引けば、その間の生活費が大きな負担となる可能性があります。
負担を軽減するためには、ボーナスに加えて活用できる公的な制度を活用しましょう。
- 退職後の生活費の不安を解消する失業保険の重要性
- 失業保険の受給額を最大化する専門的なノウハウ
- 複雑な手続きをスムーズに進めるための選択肢
ここでは、退職後の経済的な安定を確保するための次のステップについて解説します。
ボーナスだけでは不十分?退職後の生活費と失業保険の役割
ボーナスは一時的な収入であり、転職活動中の生活費をすべて賄うのは困難です。
生活費の不安を取り除くためにも、国の公的な制度である失業保険を活用しましょう。
失業保険は、失業中の生活を支え、再就職を促進するための制度です。
制度を活用すれば、退職後の経済的な不安が軽減され、焦らずに自身にあった転職先をじっくり探すための精神的な余裕も生まれます。
安心して次のキャリアへ進むために、失業保険の役割を正しく理解することが大切です。
参照元:厚生労働省 雇用保険制度
知っているかどうかで大きく変わる失業保険の受給額
失業保険の制度は、申請方法や退職理由の伝え方一つで、受給がはじまるまでの期間や受け取れる総額が大きく変わることがあるため注意が必要です。
たとえば、自己都合で退職した場合でも、正当な理由があれば給付金を受け取るまでの待機期間が短縮されるケースがあります。
また、2025年4月1日からは法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が原則2か月から1か月へと短縮されるなど、制度は常に変化しています。
専門的な知識を知っているかどうかで、受け取れる金額に数十万円の差が生まれることも少なくありません。
失業保険の受取額を増やしたい場合は、専門家に相談したうえでハローワークを訪ねるとよいでしょう。
参照元:厚生労働省 令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について
複雑な手続きは専門家に相談するのが最も確実で安心
失業保険の申請手続きは、必要となる書類が多く、ハローワークでの手続きも複雑に感じるかもしれません。
自身で調べて手続きを進めることも可能ですが、最大限有利な条件で、かつスムーズに受給するためには、制度を熟知した専門家のサポートを受けましょう。
専門家に相談すれば、自身では気づかなかった受給のポイントを知ることができ、手続きの負担を減らして転職活動に集中できます。
「失業保険、もらえるなら最大限活用したい…」
でも、「手続きが複雑そう」「自分でやるのは不安」と感じていませんか?
そんなあなたの悩みを、退職のプロが解決します。
退職後の不安を解消するなら退職給付金申請サポートの退職バンクへ
退職後の経済的な不安を解消し、失業保険を最大限に活用したいとお考えなら、「退職バンク」の退職給付金申請サポートがおすすめです。
専門家の知見を活かし、あなたの退職後を力強くサポートします。
- 専門家による個別サポートで失業保険の受給額を最大化
- 全国どこからでもオンラインで相談可能
- LINEでできる無料の受給額診断
退職バンクが提供するサービスの具体的なメリットを解説します。
社会保険労務士などの専門家が自身の状況にあわせて徹底サポート
退職バンクでは、社会保険労務士をはじめとする専門家チームが、一人一人の状況にあわせた最適な申請方法を提案します。
失業保険の申請に必要な書類の準備から、ハローワークでの対応に関するアドバイスまで、専門家が一貫してサポートするため、知識がなくても安心して手続きを進められます。
自身にとって最も有利な条件で給付金を受け取れるよう、全力で支援しますので安心して相談してください。
全国対応のオンライン相談でいつでもどこでも相談できる
退職バンクのサポートは、オンラインでの面談とチャットツールでやり取りをおこなうため、全国どこにお住まいの方でも利用が可能です。
仕事が忙しい方や、近くに相談できる場所がない方でも、自身の都合のよい時間と場所で専門家のアドバイスを受けられます。
退職バンクの利用には地理的な制約なく、質の高いサポートを提供します。
まずは無料診断で自身がいくらもらえるか確認
自身が一体どの程度失業保険をもらえるのか知りたい方のために、「退職バンク」ではLINEで簡単にできる無料の受給額診断を提供しています。
友だち追加をして簡単な質問に答えていけば、受給額のイメージをつかめます。
受給額のイメージがつかめれば、転職活動時の金銭的な不安を解消できるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
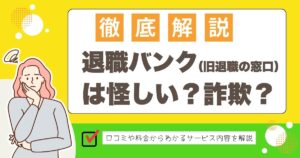
ボーナスをもらって辞める際によくある質問

ここでは、ボーナスをもらって退職する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
疑問や不安を解消し、自信をもって退職準備を進めましょう。
ボーナスをもらってすぐ辞めたら返還義務はありますか?
原則として支給されたボーナスを返還する法的な義務はありません。
ボーナスは過去の労働への対価と解釈されるため、支給が確定したものを後から返す必要はないとされています。
返還を強要された場合は、弁護士といった専門家に相談してから対応方法を決めましょう。
新入社員や公務員でもボーナスをもらって辞められますか?
新入社員や公務員の方でも、ボーナスをもらってからでも退職できます。
ただし、新入社員の場合、夏のボーナスは査定期間を満たしておらず、支給されないか、寸志程度のことが多いでしょう。
在籍日数の関係上、基本的には冬のボーナスからは査定対象となります。
公務員の場合も、民間企業と同様に支給日に在籍していれば問題ありませんが、所属先の規定を確認することが重要です。
退職を伝えた後のボーナス査定期間の勤務態度は影響しますか?
影響する可能性は十分にあると考えられます。
退職が決まっていても、ボーナスの査定期間中におこなった業務の実績や勤務態度は、評価の対象となります。
そのため、最後まで誠実に業務に取り組み、責任をもって引き継ぎをおこなうことが重要です。
円満退職を実現し、気持ちよく次のステップへ進むためにも、最後まで社会人としての責任を全うしましょう。
会社に迷惑をかけずに辞めるためにはどうすればよいですか?
円満退職のためには、会社への配慮が不可欠です。
就業規則で定められた期間を守り、可能な限り早めに退職の意思を伝えることが大切です。
次に、後任者が困らないよう、丁寧な引き継ぎ資料を作成し、業務内容を説明する時間を設けましょう。
そして、最終出社日まで責任感をもって自身の業務を全うする姿勢が、周囲の信頼につながります。
立つ鳥跡を濁さずの精神で、感謝の気持ちをもって退職準備を進めることが重要です。
ボーナスをもらった後の住民税の支払いはどうなりますか?
退職後に注意が必要な点として、住民税の納付があります。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、翌年の6月に納付しなければなりません。
在職中は給与から天引きされますが、退職後は自身で納付する必要があります。
退職する時期によっては、残りの住民税が一括で最後の給与から天引きされるか、後日送られてくる納付書で支払うことになります。
ボーナスを受け取った分も翌年の住民税額に反映されるため、納税資金を前もって準備することが大切です。
参照元:総務省 個人住民税
まとめ
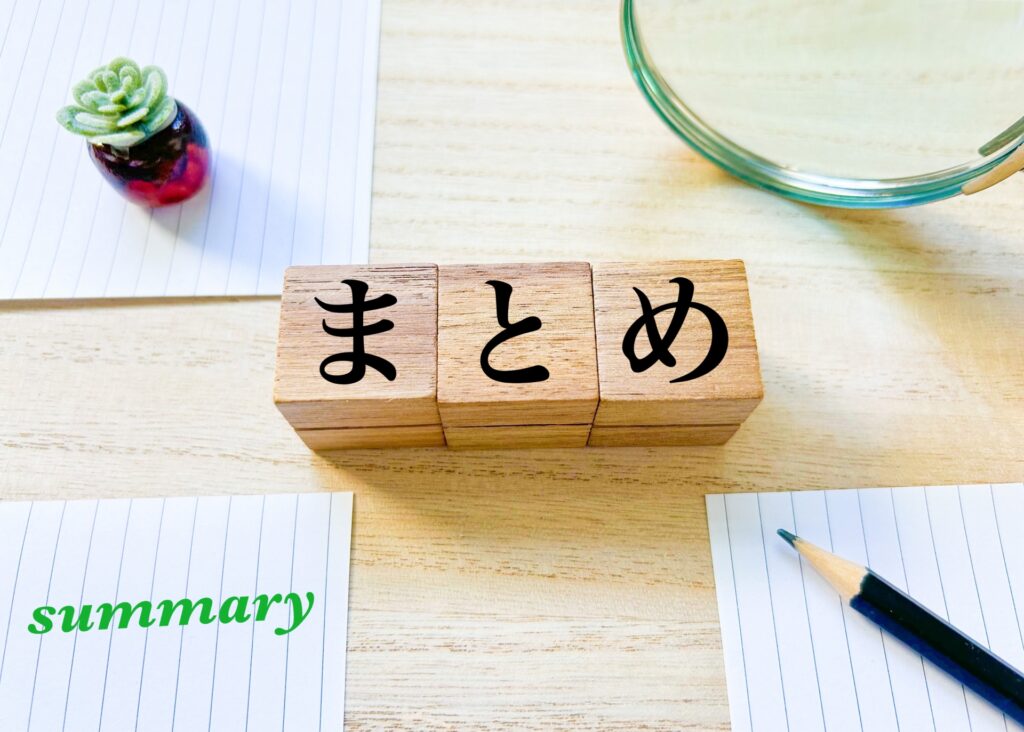
本記事では、ボーナスをもらって円満に退職するための最適なタイミングや具体的な注意点、円満退職に向けたスケジュールについて解説しました。
最も重要なのは、ボーナスの支給日に着金を確認してから退職の意思を伝えることです。
また、事前に就業規則の「支給日在籍要件」を確認すれば、不支給のリスクを確実に回避できます。
ボーナスや退職に関する判断は、専門家の知見を参考に、自身の状況にあわせて進めることが大切です。
退職後の生活や失業保険の受給に不安がある場合は、専門家がサポートする「退職バンク」の活用も検討してみてください。
- 受給額を最大化!経済的な余裕が生まれる
- 専門家が徹底サポート!面倒な手続きはお任せ
- 時間と心の余裕!焦らず次のキャリアへ
参考記事)