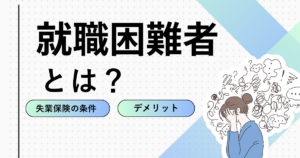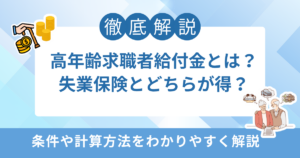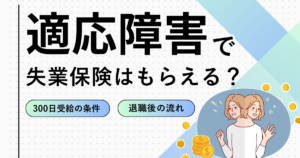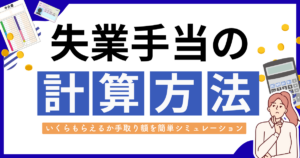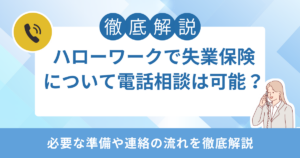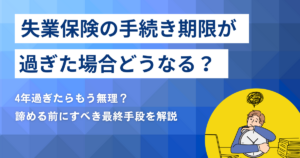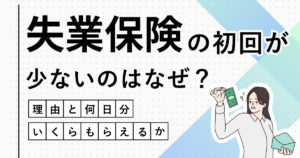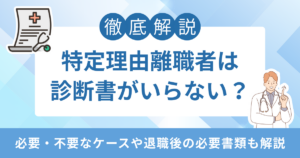離職票のもらい方は?いつ・どこでもらうかや届かない・遅い場合の対処法を解説
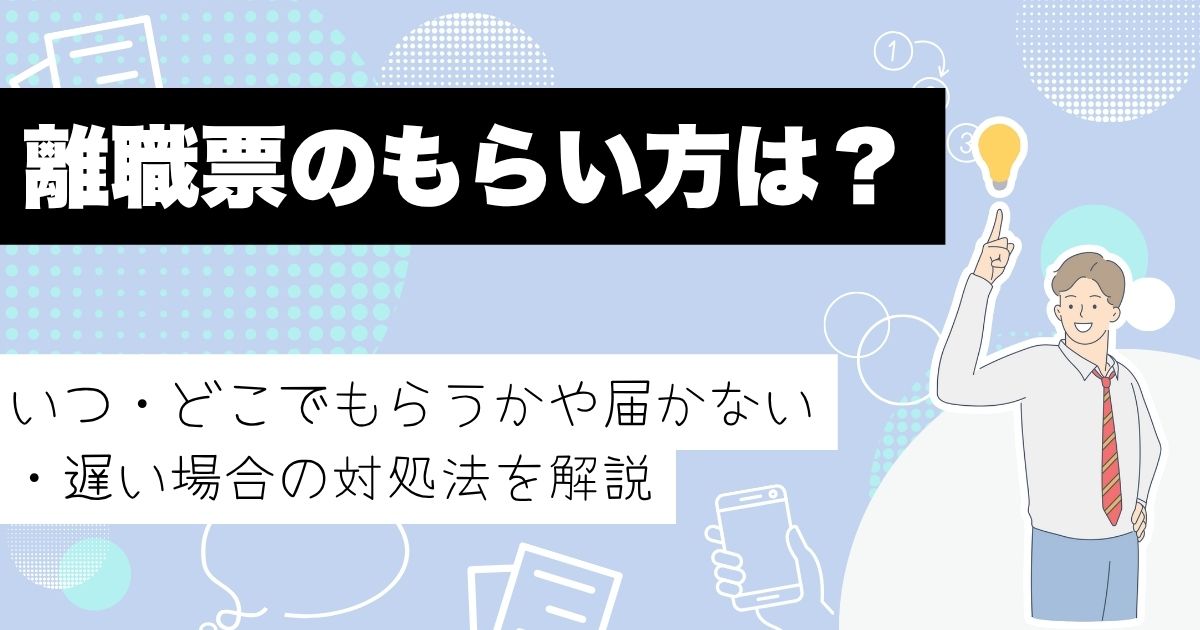
退職後の生活設計を考え、失業保険の受給を検討している方も多いでしょう。
その手続きに不可欠な離職票について、いつ、どこでもらえるのだろう、もし会社から届かない場合はどうすればよいのか、といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
結論として、離職票は基本的な流れを理解し、トラブル発生時も適切に対処すれば、確実に受け取ることができます。
本記事では、離職票の基本的なもらい方から、万が一届かない場合の具体的な対処法、そして関連するQ&Aまでをくわしく解説します。
手続きの全体像を把握し、安心して次のステップへ進みたい方はぜひ参考にしてください。
【まず知っておきたい】離職票は失業保険の受給に必須の重要書類
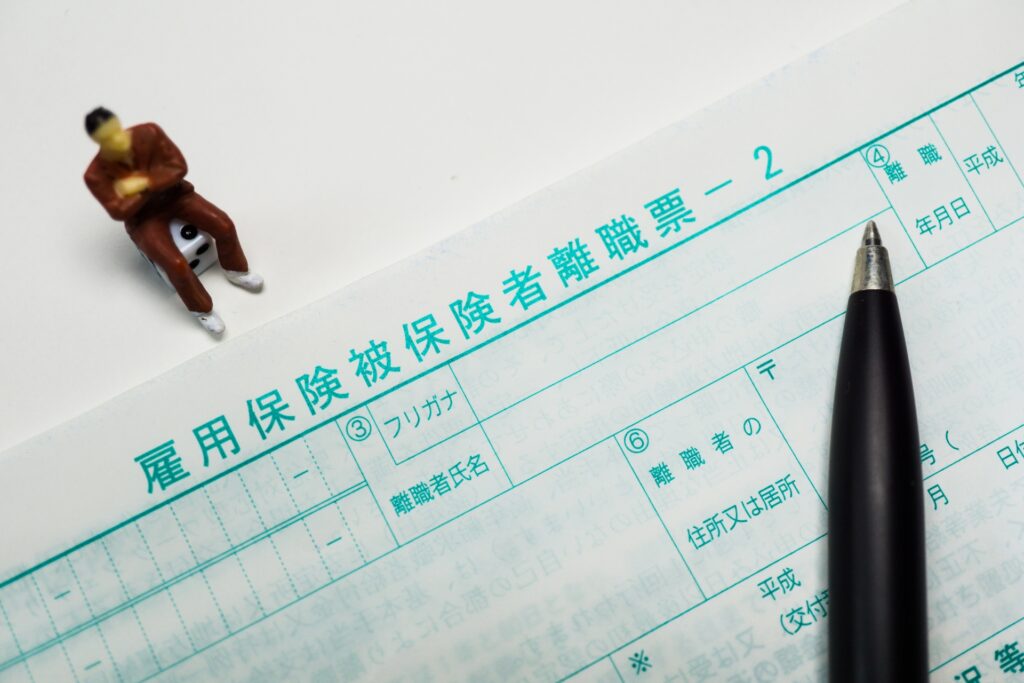
退職後の生活を支える失業保険ですが、その手続きには離職票という書類が不可欠です。
この書類がなければ、そもそも申請をはじめることができません。
ここでは、まず離職票の基本的な役割や、どのような方がもらえるのか、そして間違いやすい他の書類との違いについて確認します。
離職票とは?失業保険の申請に不可欠な役割
離職票とは、会社を辞めたことを証明し、失業保険、正式には雇用保険の基本手当の受給手続きをおこなうために必ず必要となる公的な書類です。
この書類は離職票-1と離職票-2の2種類で構成されています。
離職票-1は失業保険の振込先情報を記入する用紙で、離職票-2には離職理由や退職前の賃金支払い状況が詳しく記載されています。
これらの情報をもとに、ハローワークが受給資格や支給額を決定するため、退職後の生活設計においてきわめて重要な役割を担う書類といえるでしょう。
離職票をもらうための条件
離職票をもらうための最も基本的な条件は、退職した会社で雇用保険に加入していたことです。
これは正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態であっても、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあるなど、加入要件を満たしていれば対象となります。
自身が雇用保険に加入していたかどうかがわからない場合は、毎月の給与明細を確認してください。
雇用保険料という項目で天引きされていれば、加入している証拠です。
労働者は、この条件を満たしていれば離職票の交付を会社に請求する権利があります。
退職証明書や離職証明書との違い
書類の主な違い
| 書類名 | 概要 |
|---|---|
| 離職票 | 失業保険の受給手続きで本人がハローワークに提出する公的書類 |
| 退職証明書 | 会社が発行する退職証明の私的文書 転職や国保の手続きで使用 |
| 離職証明書 | 会社がハローワークへ提出する書類で、本人は直接扱わない |
退職時にはいくつかの書類を扱いますが、とくに退職証明書や離職証明書は離職票と混同されがちなので注意が必要です。
退職証明書は、あくまで会社が退職を証明するために発行する私的な文書となります。
一方、離職証明書は、会社がハローワークへ提出するための書類です。
私たちが失業保険の手続きでハローワークの窓口へ持参するのは離職票であると、正確に覚えておくことが重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【かんたん4STEP】離職票は退職後に会社から郵送で届くのが基本

離職票は、退職したら自動的にすぐもらえるもの、と思っている方もいるかもしれませんが、実際にはいくつかのステップを踏んで手元に届きます。
基本的な流れを理解しておけば、いつ頃届くのか見通しが立ち、安心して待つことができるでしょう。
ここでは、離職票が発行されてから手元に届くまでの、具体的な4つのステップを解説します。
STEP1:退職前に会社へ離職票の発行を依頼
離職票をスムーズに受け取るための最初のポイントは、退職前に会社へ発行の意思を明確に伝えておくことです。
原則として、会社は退職した従業員が希望した場合に離職票を発行する義務があります。
そのため、退職の意思を伝える際に、上司や人事・労務の担当者へ失業保険の手続きをしますので、離職票の発行をお願いしますと一言添えることをおすすめします。
口頭で伝えるだけでも問題ありませんが、後々のトラブルを避けるため、メールや退職届の書面で依頼した旨を記録として残しておくと、より安心です。
より確実に、そして最短で受け取るためには、正確な郵送先住所と最終的な退職日をあらためて伝える心遣いも有効です。
場合によっては、切手を貼った返信用封筒を事前に渡しておくといった配慮が、会社側の手続きを後押しすることもあります。
STEP2:会社がハローワークでおこなう手続き
退職した後、会社側で手続きが進められます。
具体的には、会社は従業員が退職した日の翌々日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書という2つの書類を、管轄のハローワークへ提出しなければなりません。
この提出は法律で定められた事業主の義務です。
ハローワークは提出された書類の内容を確認し、問題がなければ会社に対して離職票を交付します。
この段階は会社とハローワーク間のやり取りになるため、自身が直接何かをする必要はありません。
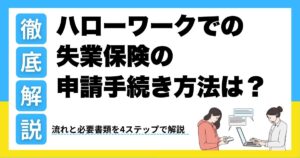
STEP3:会社から離職票が郵送で手元に届く
ハローワークから交付された離職票は、一度会社へ送られます。その後、会社から自身の元へ郵送されるのが一般的な流れです。
自身が退職してから離職票が手元に届くまでの期間は、会社の手続きの速さや郵送にかかる日数にもよりますが、通常は10日から2週間程度を見ておくとよいでしょう。
ただし、月末の退職者が多い時期や、会社の担当部署が繁忙期である場合は、手続きに時間がかかり、目安より少し遅れるケースもあります。
3週間を過ぎても届かない場合は、一度会社に確認することをおすすめします。
STEP4:記載内容を確認し署名・捺印
離職票が無事に手元に届いたら、すぐに封筒を開けて中身を確認することが重要です。
とくに離職票-2に記載されている離職理由と被保険者期間算定対象期間の賃金額は、失業保険の給付日数や1日あたりの支給額に直接影響するため、間違いがないか念入りにチェックしてください。
自身の認識と記載内容に相違がなければ、指定の箇所に署名・捺印をします。
もし内容に納得がいかない点がある場合は、安易に署名せず、ハローワークの窓口で相談するようにしてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【届かない?遅い?】離職票がもらえない場合の具体的な対処法

退職後、心待ちにしている離職票が予定を過ぎても届かないと、手続きを忘れられているのではと不安になるでしょう。
しかし、そのような時でも焦らず、冷静に対処する方法があります。
まずは状況を確認することからはじめ、段階的に対応を進めます。
ここでは、離職票が届かない、または遅いといった場合の具体的な対処法を3つのステップで解説します。
まずは会社の担当部署へ状況を確認
退職してから2週間以上経っても離職票が届かない場合、まずおこなうべきは、退職した会社の担当部署へ連絡し、手続きの進捗状況を確認することです。
感情的にならず、「お世話になっております。先日退職しました〇〇です。失業保険の手続きのため、離職票の送付状況についてお伺いしたくご連絡しました。」といった形で、丁寧に進捗を問い合わせてください。
単に担当者が手続きを忘れていたり、社内の処理が遅れていたり、郵送事故が起きていたりする可能性も考えられます。
電話やメールで状況を確認することが、解決への第一歩となります。
ハローワークで失業保険の仮手続きを進める
会社に連絡しても、すぐには離職票が届きそうにない場合でも、できることがあります。
それは、ハローワークで失業保険の仮手続きを進めておくことです。
実は、離職票が手元になくても、先にハローワークで求職の申し込みを済ませておくことが可能です。
この仮手続きをおこなっておけば、後日離職票が届いて本手続きをした際に、受給資格の決定日が仮手続きの日に遡るため、給付のはじまりが遅れるのを防ぐことができます。
仮手続きには、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類、写真などが必要になるので、事前に管轄のハローワークに確認しておいてください。
最終手段としてハローワークに発行を促してもらう
会社に何度も連絡しているのに対応してもらえない、あるいは退職後気まずくて連絡しづらい、といったケースもあるでしょう。
そのような場合は、最終手段としてハローワークに相談してください。
事情を説明すれば、ハローワークから会社に対して、法律に基づき離職票を発行するよう指導や督促をおこなってもらえます。
雇用保険法では、退職者から請求があった場合、会社は離職票を交付する義務があると定められています。
この制度を利用すれば、自身が直接会社と交渉する精神的な負担なく、問題の解決を図ることができます。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【専門家と解決】手続きの不安は「退職バンク」の無料相談がおすすめ
ここまで離職票のもらい方やトラブル対処法を解説してきましたが、自身一人で会社とやり取りするのは不安、手続きが複雑でよくわからないと感じる方もいるでしょう。
そのような時に頼りになるのが、専門家によるサポートです。
退職給付金申請サポートサービスの退職バンクなら、不安を解消し、スムーズな受給を実現するためのお手伝いができます。
専門家による申請サポートで安心
退職バンクは、社会保険労務士をはじめとする退職・失業保険の専門家チームが、給付金申請を徹底的にサポートするサービスです。
複雑でわかりにくい国の制度や申請方法も、専門アドバイザーがチャットでいつでも何度でも丁寧に教えてくれるため、知識がなくても安心して手続きを進めることができます。
ハローワークの一般的な案内だけでは得られない、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法を提案してもらえる点も、大きなメリットといえるでしょう。
全国どこからでもオンラインで相談可能
退職バンクのサポートは、オンライン面談とチャットツールで完結するため、日本全国どこにお住まいの方でも利用が可能です。
近くに相談できる場所がない地方在住の方や、日中は忙しくてハローワークの開庁時間内に行くのが難しい方でも、自身の都合のよい時間に、自宅から気軽に専門家へ相談できます。
時間や場所の制約を受けずに、質の高い専門的なサポートを受けられるのは、非常に心強いポイントです。
LINEで受給額の無料診断ができる
そもそも自身が失業保険をいくらもらえるのか、目安を知りたいという方も多いでしょう。
退職バンクでは、そうしたニーズに応えるため、公式LINEアカウントで受給額の無料診断を実施しています。
いくつかの簡単な質問に答えるだけで、受け取れる可能性のある給付金の目安を手軽に確認することが可能です。
サービスを利用するかどうかを判断する前に、まずはこの無料診断で、自身が受けられるメリットの大きさを具体的に把握してみることをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
離職票のもらい方に関するよくある質問
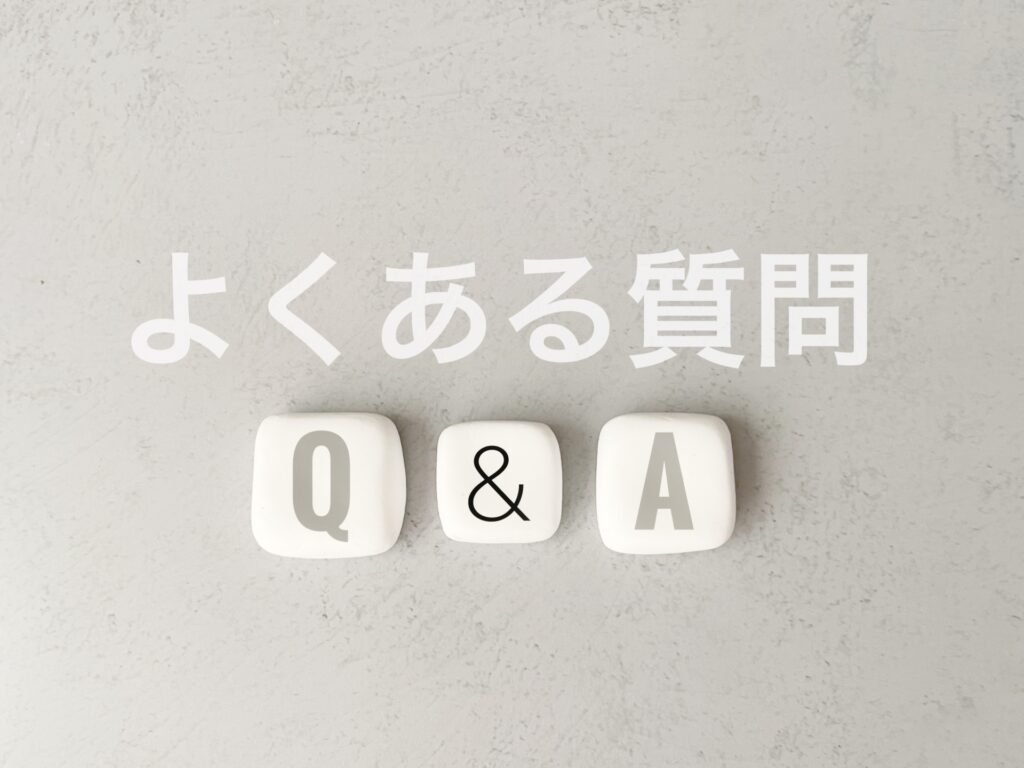
ここでは、離職票のもらい方に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。
いざという時に慌てないよう、細かい点までしっかり確認してください。
退職後、離職票はいつまでに届きますか?
離職票が手元に届くのは、一般的に退職してから10日〜2週間後が目安です。
法律では、会社は退職日の翌々日から10日以内にハローワークで資格喪失の手続きをおこなう義務があります。
その後、ハローワークから交付された離職票が会社を経由して本人へ郵送されるため、このくらいの期間がかかります。
ただし、会社の処理速度や郵送事情によっては、3週間近くかかる場合もあるため、あくまで目安として考えておくとよいでしょう。
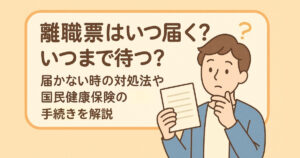
パートやアルバイトでも離職票はもらえますか?
もらえます。
離職票は、正社員や契約社員といった雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入していた方であれば請求する権利があります。
パートやアルバイトの方でも、週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあるなどの加入条件を満たしていれば、雇用保険の被保険者となります。
自身が加入していたか不明な場合は、給与明細に雇用保険料の記載があるか確認してみてください。
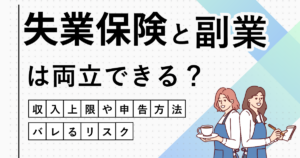
離職票を紛失した場合、再発行はできますか?
万が一離職票を紛失しても再発行が可能です。
再発行を申請する方法は、主に2つあります。
退職した会社に直接連絡して再発行を依頼する
自身の住所を管轄するハローワークの窓口へ行き、再発行の申請書を提出する
ハローワークで手続きする場合は、本人確認ができる身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑が必要になりますので、忘れずに持参してください。
退職して数か月経ちますが、今からでも離職票はもらえますか?
退職から期間が空いた場合でも、雇用保険に加入していた事実があれば離職票を発行してもらうことは可能です。
基本的な請求方法は、退職時と同じです。まずは、退職した会社の人事・労務担当部署に連絡を取り、離職票の発行を依頼してください。
もし会社と連絡が取りづらい、あるいは対応してもらえないといった事情がある場合は、自身の住所を管轄するハローワークに相談してください。
ハローワークから会社へ発行を促してもらうことができます。
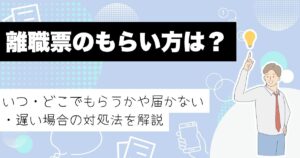
自己都合退職の場合、給付開始が遅くなるのですか?
原則として給付開始が遅くなります。
自己都合で退職した場合、7日間の待機期間が満了した後、さらに原則1か月間の給付制限期間が設けられています。
一方、倒産や解雇といった会社都合で退職した場合は、この給付制限期間がないため、待機期間が明ければすぐに給付が開始されます。
ただし、2025年4月1日からは制度が一部変更され、自己都合退職者であっても、離職後に自ら教育訓練などをおこなった場合には、この給付制限が解除される特例が設けられます。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
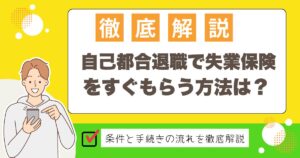
まとめ

本記事では、失業保険の受給に不可欠な離職票のもらい方について、基本的な流れから、会社から届かない・遅いといったトラブル時の具体的な対処法までを解説しました。
離職票は、退職後に会社から郵送で受け取るのが基本です。
万が一、2週間以上経っても届かない場合は、まず会社へ状況を確認し、それでも解決しなければハローワークへ相談することが重要です。
手続きの全体像と対処法を知っておくことで、退職後の不安は大きく軽減されるでしょう。
今回の内容を参考に、自身の状況にあわせて落ち着いて手続きを進め、安心して次のキャリアへと進んでください。
手続きに不安を感じる方は、専門家がサポートする退職バンクの無料相談を活用するのも一つの有効な手段です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /