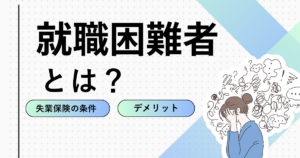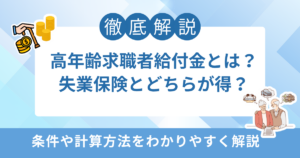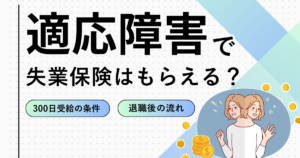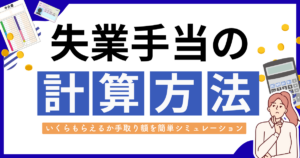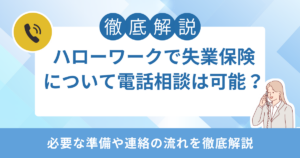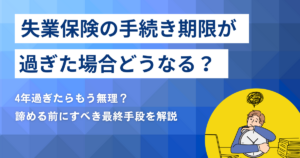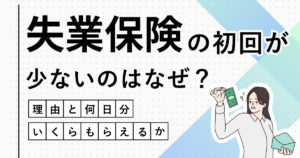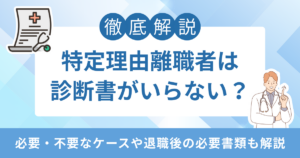失業保険は病気退職でも受給できる?給付制限・延長制度や手続きの流れを解説
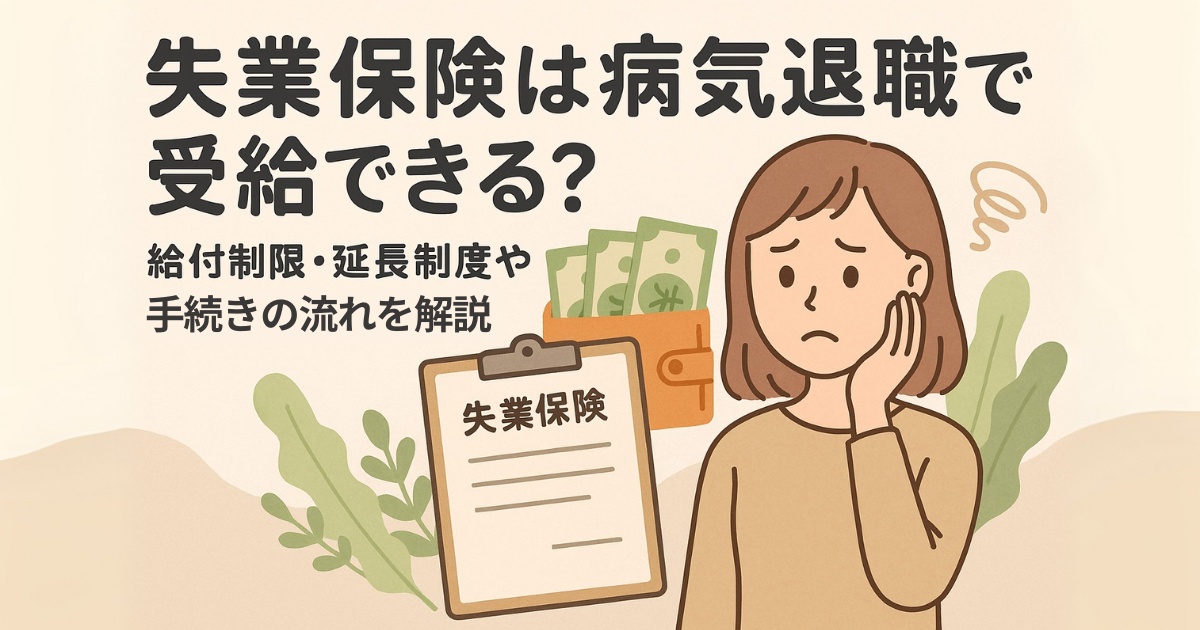
病気やケガが原因で退職を考えたとき、まず心配になるのが収入のことではないでしょうか。
「失業保険はもらえるのだろうか」「自己都合扱いになって給付制限があるのでは」「すぐに働けないけど大丈夫?」といった不安や疑問がよぎるかもしれません。
結論として、病気やケガによる退職であっても、正しい手続きを踏めば失業保険を受給できる可能性は十分にあり、場合によっては有利な条件で受給できることもあります。
この記事では、病気退職における失業保険の受給資格、給付制限を受けずに済む「特定理由離職者」の条件、すぐに働けない場合の「受給期間延長制度」、そして手続きの鍵となる「診断書」の役割や準備について、分かりやすく解説します。
記事を読むことで、制度への理解が深まり、手続きへの不安が軽減されます。本記事を安心して次のステップへ進むための一助としてください。
病気退職での失業保険サポートは
【結論】病気やケガでの退職でも失業保険は受給できる可能性あり
病気やケガが原因で退職を余儀なくされた場合、失業保険の受給を諦めてしまう方もいるでしょう。
しかし、実際には「特定理由離職者」や「特定受給資格者」として認定され、給付制限なしで早期に受給できる可能性があります。
また、すぐに働けない状態であっても、「受給期間の延長」という制度を利用できる場合もあります。
大切なのは、自身の状況に合った正しい手続きを知り、必要な準備を進めることです。
特定理由離職者/特定受給資格者とは?病気退職が該当するケース
失業保険の手続きにおいて、離職理由はいくつかの区分に分けられます。
自身の意思で退職する「自己都合退職」や、会社の倒産・解雇による「会社都合退職」などが一般的です。
病気やケガによる退職は、形式的には自己都合退職に含まれますが、「正当な理由のある自己都合退職」として扱われる場合があります。
これが「特定理由離職者」です。また、状況によっては解雇などに準ずる「特定受給資格者」と判断されることもあります。
医師の診断に基づき、病気やケガによって就労が困難な状況であったとハローワークが判断した場合、これらの区分に該当する可能性が高まります。
給付制限なしで受給できるメリットとは?
通常の自己都合退職の場合、失業保険の申請後、原則として1か月の「給付制限」期間が設けられます。
この期間中は、基本手当を受け取ることができません。
しかし、病気やケガが理由で「特定理由離職者」や「特定受給資格者」と認定されると、この給付制限が適用されなくなります。
つまり、7日間の待機期間満了後、すぐに基本手当の受給を開始できます。
治療費などで経済的な不安を抱えている方にとって、一日でも早く給付を受けられることは、生活の安定と安心につながる大きなメリットとなるでしょう。
【重要】すぐに働けない場合は「受給期間の延長」を申請可能
失業保険は、原則として働く意思と能力がある方が対象です。
しかし、病気やケガの治療のため、すぐに働けない状態にある方もいるでしょう。
そのような場合に利用できる制度が「受給期間の延長」制度です。
これは、本来1年間である失業保険の受給期間を、働けない日数分だけ、最長3年間まで延長できる制度です。
つまり、合計で最大4年間、受給資格を保持できます。
延長を希望する場合は、離職日の翌日から30日が経過した後、できるだけ早くハローワークへ申請書や医師の診断書などを提出する必要があります。
早めの申請が、有利な受給につながる可能性となるでしょう。
正しい知識と準備が不利なく受給するための鍵
病気やケガを理由に退職する場合、失業保険の手続きには通常の退職とは異なる注意点が存在します。
自身の状況を正確に伝え、利用できる制度を最大限活用するためには、正しい知識を身につけ、事前に十分に準備を進めることが重要です。
とくに、医師に依頼する診断書の内容や、ハローワークでの説明の仕方などが、手続きをスムーズに進め、給付制限の免除や受給期間の延長といった有利な条件を得るための鍵となります。
具体的な手続きや注意点を理解し、安心して申請に臨めるよう準備しましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
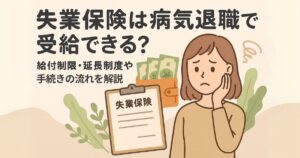
【手続きの要】診断書が失業保険の受給可否を左右する
病気やケガで退職し、失業保険を申請する際に非常に重要な書類となるのが診断書です。
この診断書の内容によって、特定理由離職者として認められるか、あるいは受給期間の延長が承認されるかなどが左右される可能性があります。
ここでは、診断書がなぜ必要なのか、どのような内容を記載してもらうべきか、そしていつ、どのように取得・提出すればよいのか、注意点と併せて詳しく解説します。
適切な診断書を用意することが、スムーズな受給への第一歩です。
なぜ診断書が必要?ハローワークでの役割
ハローワークで失業保険の手続きをおこなう際に、医師の診断書が必要になる理由を説明します。
それは、自身が病気やケガによって退職を余儀なくされたこと、そして場合によっては現在も就労が困難な状態にあることを、客観的に証明するためです。
口頭での説明だけでは、ハローワークは「正当な理由のある自己都合退職」であるか、あるいは受給期間の延長が必要な状態であるかを正確に判断できません。
診断書は、ハローワークが受給資格の区分を決定したり、延長の要否を判断したりする際の重要な根拠資料となります。
診断書がない場合、単なる自己都合退職と扱われ、不利な条件になる可能性があります。
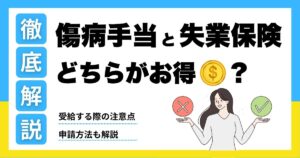
診断書には何を書いてもらう?記載必須の項目と依頼のコツ
失業保険の手続きに必要な診断書には、記載してもらうべき重要な項目があります。
【記載必須の項目例】
- 病名または傷病名
- 初診日および発病年月日
- 治療期間の見込み(療養が必要な期間)
- 就労の可否に関する医師の具体的な意見
とくに重要なのは、就労の可否に関する医師の意見です。
労務不能や就労困難といった記載があると、特定理由離職者や受給期間延長の判断につながりやすくなります。
医師に診断書作成を依頼する際は、単に診断書をお願いしますと伝えるだけでなく、失業保険の申請に使用するため、就労が困難である旨を記載してほしいと、具体的に目的と必要な情報を伝えることが大切です。
診断書はいつ/どこでもらう?提出先とタイミング
診断書は、自身の病状を把握している主治医に作成を依頼するのが一般的です。かかりつけの医療機関で相談しましょう。
診断書を取得するタイミングとしては、退職が決まった後、ハローワークで手続きをおこなう前が適切です。
早めに依頼しておくと、スムーズに手続きを進められます。作成された診断書は、自身の住所を管轄するハローワークに提出します。
提出するタイミングは、主に初回の失業保険申請手続きの際です。
また、受給期間の延長を申請する場合にも、あらためてその時点での状況を示す診断書が必要になることがあります。
診断書に関する注意点:費用や有効期限はある?
診断書の取得に関して、いくつか注意点があります。
まず、診断書の発行には費用がかかります。この費用は医療機関によって異なり、健康保険の適用外となるため全額自己負担です。
事前に料金を確認しておくとよいでしょう。
診断書に明確な有効期限は定められていないことが多いですが、ハローワークによっては「発行から〇か月以内のもの」といった指示がある場合もあります。
提出は原則として原本が必要です。コピーでよいかどうかも含め、不明な点は事前にハローワークに確認することをおすすめします。
傷病手当金など他の手続きでも診断書が必要な場合は、複数枚発行してもらうか、コピーの可否を確認しましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /

【働けない場合】失業保険の受給期間延長制度を詳しく解説
病気やケガの治療に専念するため、退職後すぐには働けないという方も少なくありません。
そのような場合に活用したい制度が、失業保険の受給期間延長制度です。
この制度を利用すれば、本来1年間の受給期間を、働けない期間分だけ先延ばしにできます。
ここでは、受給期間延長制度の詳しい内容、対象となる条件、延長できる期間と申請期限、そして具体的な手続き方法について解説します。
療養に専念しつつ、将来の再就職に備えるためにも、この制度を正しく理解しておきましょう。
受給期間延長制度とは?利用できる条件を確認
失業保険の受給期間延長制度は、病気、けが、妊娠、出産、育児、親族の介護など、やむを得ない理由で30日以上継続して働くことができない場合に、失業保険を受け取れる権利(受給期間)を保持できる制度です。
通常、受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、この制度を利用することで、働けない期間分だけ受給期間を先延ばしにできます。
具体的には、医師の診断により就労不能と判断された病気やケガなどが対象となります。
ただし、あくまで受給できる期間が延びるのであり、給付日数が増えるわけではない点に注意が必要です。
最大どれくらい延長できる?申請期限はいつまで?
受給期間の延長は、本来の受給期間である1年間に加えて、働けない理由がある期間について、最長で3年間まで可能です。
つまり、合計で最大4年間まで受給期間を延ばすことができます。ただし、非常に重要なのが申請期限です。
延長の申請は、働けない状態が30日以上続いた後、できるだけ速やかにおこなう必要があります。
具体的には、離職日の翌日から起算して30日経過した日の翌日から、1か月以内におこなうことが原則とされています。
申請が遅れると、延長自体は認められても、回復後に本来受け取れたはずの給付日数をすべて受け取れなくなる可能性があるため、注意が必要です。
延長申請の手続き:必要書類と提出方法
受給期間延長の申請手続きは、自身の住所を管轄するハローワークでおこないます。
【主な必要書類】
- 受給期間延長申請書
- 離職票-1、離職票-2
- 医師の診断書など、働けない理由を証明する書類
- 本人確認書類
- 印鑑
申請書はハローワークの窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードできる場合があります。
記入方法で不明な点があれば、窓口で確認しましょう。
提出方法は、ハローワークの窓口へ持参するのが基本ですが、病状などにより本人が手続きできない場合は、郵送や代理人による申請が可能な場合もあります。
事前に管轄のハローワークに問い合わせて確認することをおすすめします。
延長期間中に気をつけること:回復後の手続きは?
受給期間を延長している間は、失業保険(基本手当)の給付はおこなわれません。あくまで受給資格を保持している状態です。
療養に専念し、働ける状態に回復したら、速やかにハローワークにその旨を申し出なければなりません。
あらためて求職の申し込みをおこない、失業認定を受けることで、基本手当の受給手続きが開始されます。
延長期間中にアルバイトなどをおこなった場合、原則として収入を得る活動となり、失業状態とはみなされないため注意が必要です。
不明な点は必ずハローワークに確認しましょう。回復後のスムーズな受給開始のためにも、手続きを忘れないようにしてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
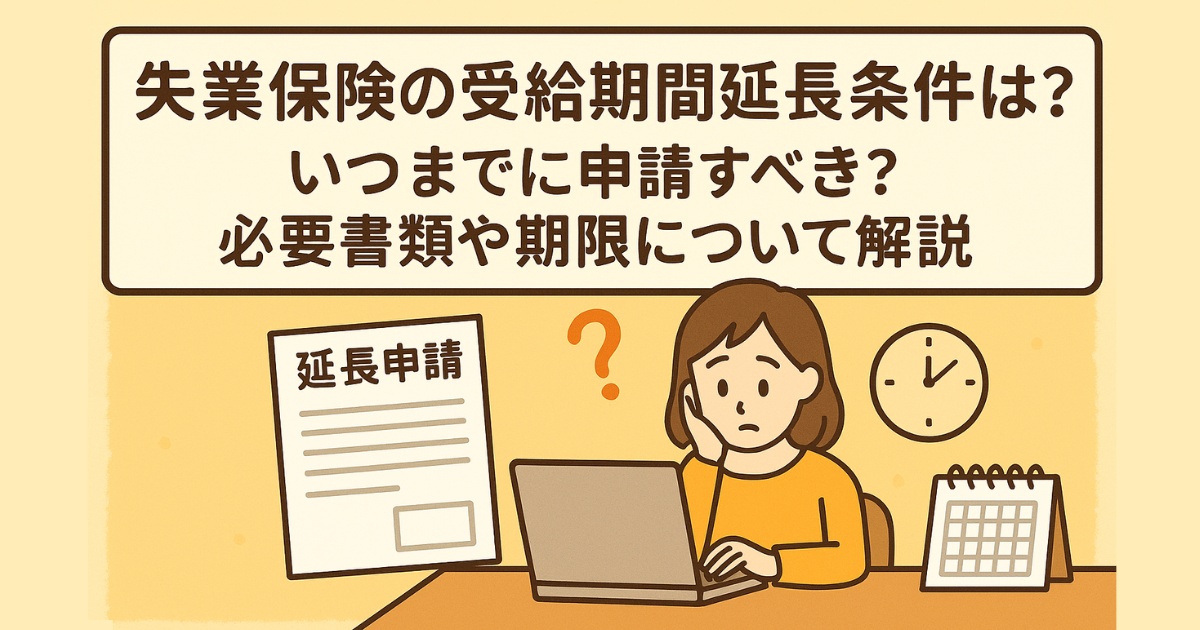
病気退職における失業保険の申請から受給までの流れ
病気やケガで退職した場合の失業保険申請は、通常の退職時と基本的な流れは同じですが、いくつか特有の注意点があります。
退職前の準備からハローワークでの手続き、そして実際の受給開始まで、一連の流れを把握しておくことで、不安なくスムーズに進めることができるでしょう。
ここでは、病気退職の場合に特有のポイントも踏まえながら、失業保険の申請から受給までの具体的なステップを解説します。
退職前に確認・準備すべきことリスト
失業保険の手続きを円滑に進めるためには、退職前からいくつかの点を確認し、準備しておくことが望ましいです。
【退職前のチェックリスト】
- 会社への退職理由の伝え方
└可能であれば病気が理由であることを伝え離職票にその旨が反映されるよう相談 - 離職票の受け取りと内容確認
└退職後に会社から交付される離職票-1と離職票-2を確実に受け取り確認 - 医師の診断書の手配
└退職が決まったら早めに主治医に相談し失業保険申請に必要な診断書の作成を依頼 - 雇用保険被保険者証の確認
└会社から受け取るか手元にあるかを確認
これらの準備を事前に行うことで、退職後の失業保険手続きがスムーズに進みます。早めに確認し、不明な点は会社やハローワーク、主治医に相談しましょう。
参考:厳選!おすすめの退職代行はこちら│キャリアバディマガジン
ハローワークでの初回手続き:持ち物と手順
退職後、離職票などの必要書類が揃ったら、自身の住所を管轄するハローワークで最初の手続きをおこないます。
【主な持ち物】
- 離職票-1、離職票-2
- 雇用保険被保険者証(ある場合)
- 医師の診断書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真(指定サイズあり)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
ハローワークでは、まず求職の申し込みをおこないます。その後、持参した書類を提出し、失業保険の受給資格の決定を受けます。
この際、病気で退職したこと、そしてすぐに働けない場合はその旨を伝え、診断書を提出しましょう。
ここで特定理由離職者に該当するか、受給期間延長が必要かなどが判断され、今後の手続き(雇用保険説明会の日程など)が案内される流れです。
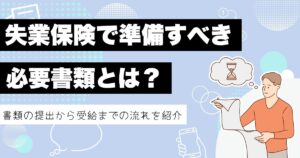
失業認定と受給:認定日の手続きと入金までの期間
失業保険を受給するためには、原則として4週間に1度、指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業状態にあることの確認を受ける必要があります。
失業認定日には、失業認定申告書に求職活動の実績などを記入して提出します。ただし、病気療養中で受給期間を延長している場合は、この手続きは不要です。
延長解除後、働ける状態になってから失業認定が開始されます。失業認定を受ければ、通常5営業日程度で指定した口座に基本手当が振り込まれます。
療養中の場合は、求職活動ができない旨を申告することになるでしょう。
【要注意】病気退職で特に気をつけるべきポイント
病気やケガによる退職で失業保険を申請する際には、とくに以下の点に注意が必要です。
まず、ハローワークには自身の病状や就労の可否について、正直かつ正確に申告することが重要です。
診断書の内容と齟齬がないようにしましょう。
また、主治医との連携を密にし、治療方針や診断書の内容についてよく相談しておくことが大切です。
働けない状態で無理に求職活動をおこなう必要はありません。自身の体調を最優先しましょう。
傷病手当金(健康保険)との関係も考慮し、どちらの制度を利用するのが適切か検討しましょう。
不明な点や不安なことがあれば、決して一人で抱え込まず、ハローワークや専門家に相談することが問題解決への近道です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険と傷病手当金どちらを使うべき?違いと併用の注意点
病気やケガで働けなくなった場合、公的な支援制度として失業保険(雇用保険の基本手当)の他に、傷病手当金(健康保険)があります。
どちらも経済的な支えとなる制度ですが、その目的や支給条件は異なります。
自身の状況にあわせて適切な制度を利用することが大切です。
ここでは、失業保険と傷病手当金の違い、併用に関する注意点、そしてどちらを優先すべきかの判断基準について解説します。
傷病手当金とはどんな制度?失業保険との違い
傷病手当金は、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)から支給される手当金です。
業務外の病気やケガで仕事を休み、その間の給与が支払われない場合に、被保険者とその家族の生活を保障することを目的としています。
一方、失業保険(基本手当)は雇用保険の制度であり、失業中の生活を支え、再就職を促すことを目的としています。
【主な違い】
| 項目 | 傷病手当金 | 失業保険(基本手当) |
|---|---|---|
| 目的 | 療養中の生活保障 | 失業中の生活保障と再就職支援 |
| 対象 | 働けない状態 | 働ける状態(働けない場合は延長申請) |
| 申請先 | 健康保険組合・協会けんぽ | ハローワーク |
支給期間や金額も異なります。
失業保険と傷病手当金は同時にもらえない?
失業保険と傷病手当金は、原則として同時に受け取ることはできません。
その理由は、失業保険は「働く意思と能力がある」ことが前提であり、求職活動をおこなう必要があります。
一方、傷病手当金は「病気やケガにより働くことができない(労務不能)」状態であることが支給の条件のためです。
つまり、両制度の対象となる状態が根本的に異なるため、同じ期間に両方を受給することは認められていません。
ただし、退職前に傷病手当金を受給し、退職後に回復して失業保険を申請する、といったケースは考えられます。
自分の状況に合わせてどちらを申請するか判断しよう
自身の状況でどちらの制度を利用するのが適切か、判断基準を解説します。
まず、退職後も療養が必要で、すぐに働くことができない場合は、傷病手当金の受給を検討するのが一般的です。
ただし、傷病手当金は在職中に連続して3日間休んだ後の4日目からが支給対象となるなど、受給には条件がありますので確認が必要です。
退職時にすでに働ける状態にある場合や、比較的短期間の療養で回復が見込める場合は、失業保険の申請を検討しましょう。
すぐに働けない場合でも、前述した受給期間の延長制度を利用し、療養に専念した後に失業保険を受給するという選択肢もあります。
判断に迷う場合は、ハローワークや加入している健康保険組合、あるいは専門家へ相談することをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
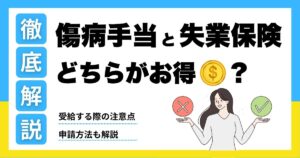
【無料診断あり】退職バンクなら専門家が失業保険申請をサポート
病気やケガでの退職に伴う失業保険の申請は、手続きが複雑で分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
自身の状況にあった適切な手続きを間違いなく進められるか、不安になることもあるでしょう。
そのようなとき、専門家のサポートを頼るのも有効な選択肢の一つです。
「退職バンク」は、まさにそうした失業保険や給付金の申請に特化したサポートを提供しています。
まずはLINEで簡単にできる無料の受給額診断から試してみることをおすすめします。
退職バンクのサービス内容
「退職バンク」の主なサービス内容は、失業保険や退職に伴う各種給付金の申請を専門的にサポートすることです。
とくに、病気やケガといった複雑な事情を抱えて退職される方の失業保険申請手続きにおいて、豊富な知識と経験に基づいたサポートを提供することに強みを持っています。
単に情報を提供するだけでなく、個々の状況をヒアリングし、必要な書類の準備や手続きの流れについて、具体的かつ的確なアドバイスや支援をおこなう点が特徴です。
利用者の不安に寄り添い、スムーズな受給実現をサポートします。
LINEで簡単!まずは無料の受給額シミュレーションから
自身が失業保険をいくらくらい受け取れるのか、目安だけでも知りたいと考える方もいるでしょう。
「退職バンク」では、そんなニーズに応えるLINEを使った無料の受給額診断サービスを提供しています。
スマートフォンからLINEで「退職バンク」のアカウントにアクセスし、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、失業保険の受給額の概算を手軽に知ることができます。
複雑な計算や面倒な手続きは不要です。
この無料診断を利用することで、自身の状況における経済的な見通しを立てる第一歩となり、今後の手続きを進めるうえでの参考になるでしょう。
相談は無料!専門家に話を聞いてもらうことから始めよう
失業保険の手続きに関して、疑問や不安があるけれど、いきなりサービス利用を申し込むのはハードルが高いと感じる方もいるでしょう。
「退職バンク」では、サービス利用前の相談は無料でおこなっています。
失業保険に関する一般的な質問から、自身の具体的な状況に関する悩みまで、まずは専門家である社労士に気軽に話を聞いてもらうことができます。
相談したうえで、サポートが必要だと感じればサービス利用を検討するとよいでしょう。
無理に契約を勧められることはありません。まずは無料相談を利用して、自身の不安を解消することからはじめてみることをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
病気退職と失業保険に関するQ&A
ここでは、病気で退職された方が失業保険に関して抱きやすい疑問について、Q&A形式で解説します。
うつ病などの精神疾患の場合や、会社に病気のことを伝えていなかった場合、受給中に病状が悪化した場合など、具体的なケースについて説明します。
うつ病などの精神疾患でも失業保険は受給できますか?
うつ病などの精神疾患が理由で退職した場合でも、他の身体的な病気やケガと同様に、条件を満たせば失業保険を受給することは可能です。
重要なのは、医師の診断に基づき、その病状によって就労が困難な状態であったとハローワークに認められることです。
適切な診断書を提出し、特定理由離職者として認定されれば、給付制限なしで早期に受給できる可能性があります。
また、療養が必要で、すぐに働くことが難しい場合には、受給期間の延長制度を利用することもできます。
精神疾患であることを理由に、諦める必要はありません。
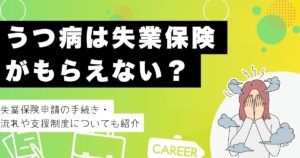
退職時に会社へ病気のことを伝えていなくても申請できますか?
退職時に会社へ病気が理由であることを伝えていなかったとしても、失業保険の申請自体は可能です。
ハローワークでの手続きの際に、医師の診断書を提出し、病気やケガによって就労が困難な状態で離職したことを客観的に証明できれば、特定理由離職者として認められる可能性があります。
ただし、会社から発行される離職票の離職理由欄が自己都合となっている場合は注意が必要です。
ハローワークの担当者に対して、病気が真の退職理由であることを丁寧に説明し、診断書によってそれを裏付けることがより重要になります。
正直に状況を伝えることが大切です。
失業保険の受給中に病状が悪化して働けなくなったら?
失業保険(基本手当)の受給中に、病気やケガが悪化するなどして再び働けない状態になった場合は、基本手当の支給は停止されます。
しかし、その代わりとして、雇用保険の制度である傷病手当を受給できる可能性があります。これは、健康保険の傷病手当金とは別の制度です。
働けない状態が15日以上(連続・断続問わず)続く見込みとなった場合は、速やかにハローワークに申し出て、傷病手当の支給申請手続きをおこなう必要があります。
放置すると受給資格を失う可能性もあるため、早めの相談と手続きが重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ
この記事では、病気やケガが原因で退職された(または検討中の)方に向けて、失業保険の受給に関する様々な疑問点について解説しました。
具体的には、特定理由離職者の条件、給付制限、受給期間の延長制度、診断書の重要性、申請手続きの流れ、そして傷病手当金との違いなど、多岐にわたる内容を取り上げました。
最も重要な点は、病気やケガによる退職であっても、諦める必要はないということです。
正しい知識を持ち、医師の診断書など必要な準備を整え、適切な手続きをおこなえば、「特定理由離職者」として給付制限なく早期に受給できる可能性があります。
また、すぐに働けない場合でも「受給期間の延長」制度を活用することで、療養に専念した後に受給を開始できます。
手続きに不安がある場合は、一人で抱え込まず、ハローワークや「退職バンク」のような専門家のサポートを活用することも有効な手段です。
この記事で得た情報を参考に、自身の状況に合わせて手続きを進めていきましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /