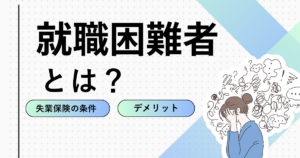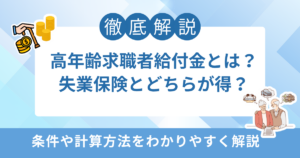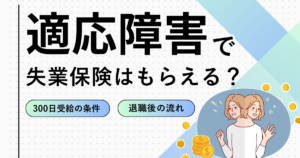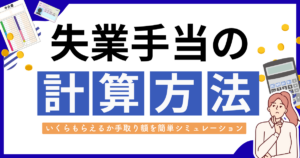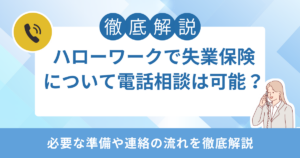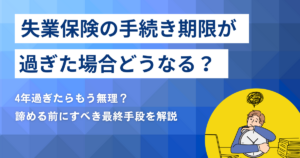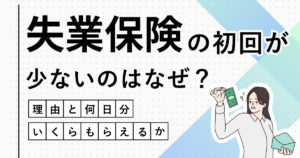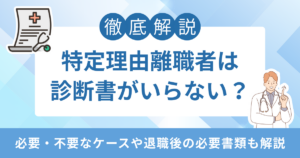【2025年最新】退職後にもらえるお金・給付金一覧|失業保険以外にもらえる手当や条件を解説
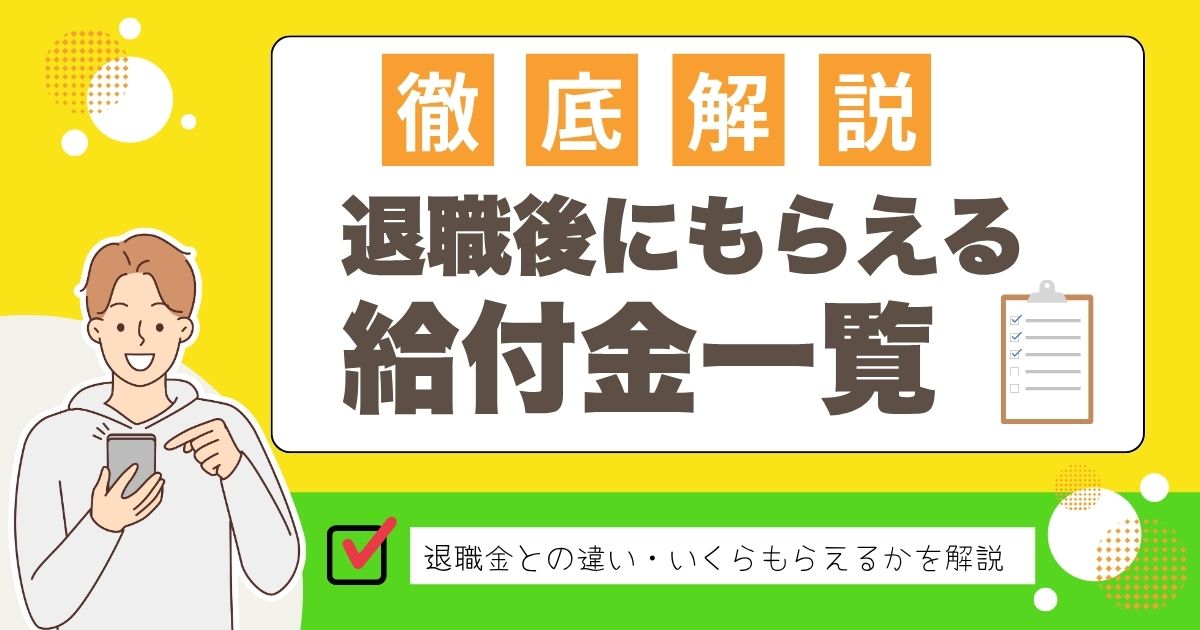
退職を考え始めると、まず頭に浮かぶのが「今後の生活費はどうしよう」という金銭的な不安ではないでしょうか。
退職したらもらえるお金は、一般的に知られる失業保険だけではありません。
しかし、退職後にもらえるお金があるといっても自分はいくらもらえるのか、制度が複雑でよくわからない方も多いでしょう。
結論から言うと、退職後に受け取れる公的なお金には様々な種類があり、知っているかどうかで受け取れる金額が大きく変わる可能性があります。
この記事では、2025年施行の最新情報に基づき、退職後の給付金の種類一覧や受給条件、損をしないための申請方法などを解説します。
ぜひ参考にして、退職後の自身の権利を最大限に活用してください。
「退職後にもらえるお金」は主に2種類!
あなたはどちらを調べるべき?
(退職金など)
勤続年数や功労に報いるため、会社が独自に定めるお金。
制度があるかどうかは会社次第です。
確認すべきこと
就業規則や退職金規定をチェック(失業保険など)
失業中の生活を支え、再就職を助けるためのお金。正社員以外も対象で、多くの人に受給の可能性があります。
もらえるか不安な方は…
専門家に無料相談するこの記事でわかること
退職後にもらえるお金(退職給付金)とは

退職後の生活を考える上で、まずは「退職給付金」の正しい意味と、「退職金」との違いを正確に理解する必要があります。
言葉の定義を整理することで、自身の状況を客観的に把握し、適切な計画を立てる第一歩となります。
退職給付金は国から支給される公的制度の総称
まず、「退職給付金」は、特定の制度を指す正式名称ではありません。
一般的に、退職した後に国から受け取れる公的なお金、特に雇用保険制度から支給される失業手当などの総称として使われています。
これらの制度は、失業中の生活の安定を図り、安心して再就職活動に専念できるよう支援するのを目的としています。
「退職給付金」と会社から支払われる「退職金」との違い
退職時にもらえるお金として、多くの人が混同しがちなのが「退職給付金」と「退職金」です。
この2つは、まったく別の制度なので、ここで明確に区別しておきましょう。
制度の違い
| 名称 | 誰から支払われるか | 根拠となる制度 |
|---|---|---|
| 退職給付金 | 国(ハローワーク) | 雇用保険法(公的制度) |
| 退職金 | 勤務していた会社 | 各企業の退職金規程 |
退職給付金は、雇用保険に加入していれば条件に応じて受け取れる公的な支援です。
一方、退職金は会社の制度であり、制度がなければ支払われません。条件を満たせば両方を受け取ることも可能です。
この違いを理解することが、自身の状況を正しく把握する前提となります。
退職したらもらえるお金・給付金の種類一覧
① 失業中の生活費を支えるお金
- 基本手当(失業保険)
- 傷病手当
- 特例一時金
- 求職者支援制度
- 未払賃金立替払制度
② 再就職を支援するお金
- 再就職手当
- 就業促進定着手当
- 広域求職活動費
- 高年齢雇用継続給付
③ スキルアップを後押しするお金
- 教育訓練給付金
退職後にもらえるお金は、目的によっていくつかの種類があります。まずは全体像を把握するために、どのような制度があるのか一覧で確認しましょう。
自身の状況に当てはまりそうなものを見つけて、読み進めてみてください。
目的別の給付金・手当一覧
| 主な給付金・手当 の名称 | 目的 |
|---|---|
| 基本手当(失業保険) | 失業中の生活を支えたい |
| 再就職手当 | 早く再就職したい |
| 就業促進定着手当 | 再就職後の収入減を補いたい |
| 広域求職活動費 | 遠方で就職活動したい |
| 傷病手当 | 病気やケガで働けない |
| 高年齢雇用継続給付 | 60歳以降も働き続けたい |
| 教育訓練給付金 | スキルアップしたい |
| 特例一時金 | 短期・季節の仕事をする |
| 求職者支援制度 | 雇用保険に入れない人が支援を受けたい |
| 未払賃金立替払制度 | 会社が倒産してしまった |
このように、退職後の状況に応じて様々な支援制度が用意されています。
自分がどの制度の対象になる可能性があるのか、この表で大まかな見当をつけておくと、この後の内容がより理解しやすくなるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【目的別】主な退職給付金の種類と受給できる条件

前述の通り、退職後にもらえるお金には様々な種類があります。
ここでは、それぞれの給付金について、具体的に「どのような人が」「どのような条件で」「いくらくらい」もらえるのかを詳しく見ていきましょう。
自身の状況と照らし合わせながら、どの制度を活用できそうか具体的に検討してみてください。
失業中の生活を支える「基本手当(失業保険)」
退職後の生活を支える最も中心的で重要な制度が、一般的に失業保険と呼ばれる「基本手当」です。
これは、失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探すことに専念するための支援となります。
受給するには、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上、働く意思と能力があるけれど職業に就けない状態なことが主な条件です。
基本手当はいくらもらえる?具体的な計算方法とモデルケースを紹介
もらえる金額(基本手当日額)は、退職前の賃金によって決まりますが、計算方法は少し複雑です。ここでは、その計算ステップと具体例を見ていきましょう。
- 【STEP1】賃金日額を計算する
- 【STEP2】基本手当日額を計算する
まず、離職直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って「賃金日額」を算出します。賞与は含みません。
計算式:離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180 = 賃金日額
次に、算出した賃金日額に、年齢や賃金に応じた給付率(約50〜80%)を掛けて「基本手当日額」を求めます。賃金が低い人ほど給付率は高くなります。
計算式:賃金日額 × 給付率(50~80%) = 基本手当日額
【モデルケース】月収25万円・30歳の場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃金日額 | (25万円 × 6か月)÷ 180 = 約8,333円 |
| 基本手当日額 | 約5,000円~6,115円 |
| 給付率の目安 | 約60%〜73%(賃金水準により変動) |
もらえる総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。
所定給付日数は年齢、雇用保険の加入期間、退職理由によって90日~360日の間で決まります。
たとえば、上記のモデルケースの方が自己都合で退職し、雇用保険の加入期間が10年未満の場合、給付日数は90日となります。
この場合の総額の目安は以下の通りです。
計算式:基本手当日額 約5,000円 × 90日 = 約450,000円
なお、基本手当日額には以下の通り年齢別の上限額が定められています。(2025年8月1日現在)
| 年齢 | 上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30歳~44歳 | 8,055円 |
| 45歳~59歳 | 8,870円 |
| 60歳~64歳 | 7,623円 |
参照元:厚生労働省
早期の再就職を祝う「再就職手当」
早期に安定した職業に就いた場合、お祝い金として「再就職手当」を受け取れる可能性があります。
これは、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどを条件に支給される制度です。
早く再就職するほど給付率が高くなるため、転職活動の大きなモチベーションになるでしょう。
参照元:厚生労働省「再就職手当のご案内」
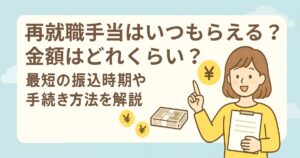
再就職後の賃金低下を補う「就業促進定着手当」
再就職手当を受給後、再就職先で6ヶ月以上働き続け、再就職後の賃金が離職前の賃金より低くなった場合に受け取れるのが「就業促進定着手当」です。
これは、再就職後の定着を支援するための制度です。
遠方での就職活動を支援する「広域求職活動費」
失業保険の受給中に、ハローワークの紹介で遠方の求人に応募し、面接に行く場合に、交通費や宿泊費の一部が支給されるのが「広域求職活動費」です。
希望する仕事が地元にない場合でも、活動範囲を広げて就職活動をおこなうことができます。
参照元:厚生労働省「広域求職活動費」 と 「移転費」 のご案内
病気やケガで働けない時の「傷病手当」
退職後にハローワークへ求職の申し込みをし、病気やケガが原因で15日以上続けて働くことができなくなった場合に、受け取れるのが「傷病手当」です。
受給額は基本手当と同額です。なお、健康保険から支給される「傷病手当金」とは別の制度であり、両方を同時に受け取ることはできません。
参照元:ハローワークインターネットサービス「傷病手当について」
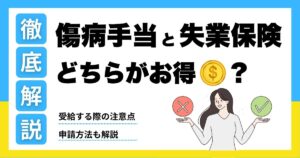
60歳以降も働く場合の「高年齢雇用継続給付」
60歳〜65歳未満の方が退職せずに働き続ける際、賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下したときに支給されるのが「高年齢雇用継続給付」です。
低下した賃金の最大15%が支給されます。定年後再雇用などで給与が下がった場合に活用できる重要な給付金です。
参照元:ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
スキルアップを支援する「教育訓練給付金」
退職を機に新しいスキルを身につけて、キャリアアップを目指したいと考える方には「教育訓練給付金」がおすすめです。
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
専門的な講座では、受講費用の最大80%が支給される可能性があります。
参照元:厚生労働省「教育訓練給付金」
短期・季節の仕事をする方向けの「特例一時金」
「特例一時金」は季節的に雇用される方や、短期の雇用を繰り返す方が失業した場合に支給される手当です。
基本手当とは異なり、一時金として一括で支払われます。
原則として、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あることなどが条件となります。
参照元:厚生労働省「離職されたみなさまへ <特例一時金のご案内>」
雇用保険に入れない方向けのセーフティネット「求職者支援制度」
雇用保険の適用がなかった方や、加入期間が足りず失業保険を受けられない方などが対象の制度です。
無料の職業訓練を受けられ、一定の要件を満たせば訓練期間中に月額10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
スキルを身につけて早期の就職を目指すための重要なセーフティネットです。
会社が倒産したときの「未払賃金立替払制度」
勤務先の会社が倒産したことにより、給料や退職金が支払われないまま退職した場合に利用できる制度です。
国が会社に代わって、未払い賃金の一部を立て替えて支払ってくれます。
万が一の事態に備えて、このような制度があることを知っておくのは重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【状況別】あなたはいくらもらえる?退職給付金シミュレーション
かんたん受給額シミュレーター
あなたが受け取れる給付金の総額目安は…
約 0 円
※このシミュレーション結果は、2025年8月1日施行の法改正に基づいた概算値です。
※実際の受給額は、離職前6ヶ月の賃金総額や年齢、退職理由などによって変動します。
※正確な金額については、必ずお住まいの地域のハローワークまたは専門家にご確認ください。
このように、あなたの状況によって最適な申請プランは大きく異なります。
どの制度をどのように組み合わせればよいか、専門家と一緒に最適なプランを立てませんか?
ここまでは、退職後にもらえる給付金の種類を個別に解説してきました。
しかし、「結局、自分の場合はどれが使えて、どう組み合わせればいいの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
本章では、具体的な2つのケースをもとに、どのような制度を活用し、どのくらいの金額を受け取れる可能性があるのかをシミュレーションします。
これはあくまで一例ですが、自身の状況と照らし合わせれば、具体的な退職後の生活をイメージできるようになるでしょう。
ケース1:心身の限界で、すぐにでも退職したい場合
- 30代・勤続5年・月収30万円
- 上司からのパワハラが原因で心身ともに疲弊。医師から「適応障害」の診断を受け、休職も検討している。
- 貯蓄に余裕がなく、すぐにでも退職したいが、収入が途絶えるのが不安で踏み切れない。
【最適な受給プランの提案】
このケースでは、まず心身の回復を最優先に考え、収入の空白期間を作らないことが重要です。
そこで、「傷病手当金(健康保険)」と「基本手当(失業保険)」を切れ目なく連携させるプランを検討します。
- 退職前医師の診断書をもとに「傷病手当金」を申請
- 体調が回復し働ける状態になったらハローワークで失業保険の手続き
在職中に申請準備を進められれば、退職後でも最長1年6か月、給与のおおよそ3分の2が支給され、安心して療養に専念できます。
そして体調が回復したら、ハローワークで失業保険の手続きをおこないましょう。
手続きの際に医師の診断書を提出し、パワハラが退職の原因であるのを証明できれば特定理由離職者に認定され、有利な条件で基本手当を受けられます。
【受給額の目安】
- 傷病手当金: 約20万円/月 × 最長1年6ヶ月
- 基本手当(失業保険): 総額 約60万円~(給付日数120日の場合)
このように制度を正しく組み合わせれば、収入の不安を解消し、心と体の回復、その後の転職活動に十分な時間を確保できます。
ケース2:キャリアアップのため、転職活動に専念したい場合
- 40代・勤続15年・月収40万円
- 現在の業務に不満はないが、より専門性を高めるために、一度退職して学習と転職活動に集中したい。
- 自己都合での退職となるため、給付金の受け取りが遅れることを懸念している。
【最適な受給プランの提案】
このケースでは、学習期間の生活を支えつつ、早期に再就職を決めることでインセンティブ(お祝い金)を得るプランが有効です。
「教育訓練給付金」と「基本手当」、そして「再就職手当」の活用を考えます。
- 退職後すぐにハローワークで失業保険の手続き
- 給付制限期間中から「専門実践教育訓練」の受講を開始
- 失業保険の受給中に転職活動をおこない早期の再就職
自己都合退職のため、7日間の待期期間+原則1か月の給付制限期間が発生します。
給付制限期間に専門実践教育訓練を受講すれば、教育訓練給付金の対象となり、受講費用の最大70%(年間上限56万円)が支給されます。
また、一定の条件を満たせば失業保険とは別に、教育訓練支援給付金も受給できる可能性があるため、自身が対象となるか確認してください。
さらに、失業保険給付日数の3分の1以上を残して再就職が決まれば、再就職手当金が支給されるため、早期の転職を目指すのがおすすめです。
【受給額の目安】
- 基本手当(失業保険): 総額 約50万円~(給付日数50日分の場合)
- 教育訓練給付金: 受講費用の最大70%
- 再就職手当: 総額 約50万円~
計画的に制度を活用すれば、キャリアアップのための学習と生活費を両立させ、さらに転職活動へのモチベーションを高められます。
【実践編】失業保険(基本手当)の申請から受給までの5ステップ
会社から必要書類を受け取る
退職後、会社から「離職票」と「雇用保険被保険者証」を受け取ります。特に離職票の退職理由は重要なので必ず確認しましょう。
ハローワークで手続き
必要書類を持参し、住所を管轄するハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定手続きを行います。
雇用保険受給者初回説明会に参加
指定された日時に説明会へ参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」などが渡され、第一回目の失業認定日が決まります。
失業認定日にハローワークへ行く
原則4週間に1度、ハローワークへ行き、求職活動の実績を報告して「失業の認定」を受けます。
給付金の受け取り(振込)
失業認定日から通常5営業日ほどで、指定した口座に基本手当(失業保険)が振り込まれます。
退職後にもらえるお金の知識を得たら、次はいよいよ具体的な行動に移る段階です。
ここでは、最も基本的な「基本手当(失業保険)」を例に、申請から実際に給付金を受け取るまでの流れを5つのステップに分けて解説します。
一つひとつのステップを順番に確認していけば、複雑に思える手続きもスムーズに進めることができるでしょう。
STEP1:会社から必要書類を受け取る
失業保険の申請を始めるには、まず勤務していた会社から必要な書類を受け取る必要があります。
最も重要な書類は「雇用保険被保険者離職票」、通称「離職票」です。
これは、退職理由や退職前の賃金が記載された、手続きに不可欠な書類となります。
通常、退職後10日ほどで自宅に郵送されてきます。あわせて「雇用保険被保険者証」も手元にあるか確認しておきましょう。
万が一、会社からこれらの書類が交付されない場合は、自身の住所を管轄するハローワークに相談することが可能です。
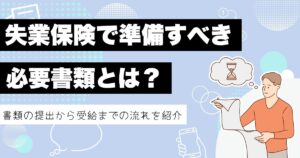
STEP2:ハローワークで求職の申し込みと受給資格の決定
必要書類が揃ったら、自身の住所を管轄するハローワークへ行き、手続きを行います。
主な持ち物
- 雇用保険被保険者離職票(1と2)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 身元確認書類(運転免許証など)
- 証明写真2枚
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
窓口で「求職の申し込み」をおこない、持参した書類を提出しましょう。
その後、職員との面談を経て、失業保険の「受給資格の決定」がおこなわれます。
この日が、受給資格者として認定される重要な日となります。
STEP3:雇用保険受給者初回説明会に参加する
受給資格が決定すると、後日開催される「雇用保険受給者初回説明会」の日時が指定されますので、必ず参加する必要があります。
この説明会では、失業保険制度の詳しい内容や、今後の手続きの流れについて重要な説明があります。
また、この場で「雇用保険受給資格者証」と、第一回目の失業認定日に提出する「失業認定申告書」が渡されます。
今後の手続きで必須となる大切な書類ですので、なくさないように保管しましょう。
第一回目の「失業認定日」もこの時に知らされることになります。
STEP4:失業の認定日にハローワークへ行く
失業保険を受給するためには、原則として4週間に1度、指定された失業認定日にハローワークへ行き、「失業状態」の認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、前回の認定日から今回までの間に、原則として2回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動とは、求人への応募やハローワークでの職業相談、許可されたセミナーへの参加などが該当します。
これらの活動内容を「失業認定申告書」に記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出することで、失業の認定がおこなわれます。
STEP5:給付金の受け取り(振込)
失業認定日に無事、失業の認定がおこなわれると、通常、認定日から5営業日ほどで指定した金融機関の口座に基本手当が振り込まれます。
これで、一連のサイクルの手続きは完了です。
ただし、自己都合で退職した場合は、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月間の給付制限期間があります。この期間中は給付金が支給されないため注意が必要です。
再就職が決まるまでは、この「求職活動」と「失業認定」のプロセスを繰り返していくことになります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
複雑な手続きは専門家に相談を。「退職バンク」で給付金を最速・最大化する選択肢
ここまで解説してきたように、退職給付金の手続きは複雑で、多くの時間と労力がかかるでしょう。
もし「手続きが難しそう」「自分で正しく申請できるか不安」と感じているなら、専門家のサポートを活用する賢い選択肢があります。
失業保険申請サポートサービス「退職バンク」は、そのような不安を解消し、より有利な条件で給付金を受け取るためのお手伝いをします。
なぜ専門家のサポートが必要なのか?申請主義の落とし穴
日本の公的制度は、自ら声を上げ、正しく申請しなければ何も受け取れない「申請主義」が原則です。
制度を知らなかった、手続きを間違えたなどの理由で、本来受け取れるはずだった数十万円〜百万円以上のお金を失うケースは決して珍しくありません。
特に、退職理由は給付内容を大きく左右しますが、専門知識がなければ自身の状況が有利な条件に該当するかどうかを判断することすら困難です。
「退職バンク」では、社会保険の専門家である社会保険労務士が監修し、状況を丁寧にヒアリングした上で、最適な申請方法をサポートします。
専門家が後ろ盾となることで、手続きの煩わしさや「損をしてしまうかもしれない」などの不安から解放され、安心して次のステップに集中できます。
実績が示す価値!退職バンクで受給額が最大200万円になるケースも
「退職バンク」を利用する最大のメリットは、受給額の最大化と受給開始の迅速化です。
専門家のノウハウにより、退職理由の見直しや各種手当の最適な組み合わせを提案して、受給額の最大化を目指します。
通常、自己都合退職では申請から受給開始まで2ヶ月以上かかるところを、最短1ヶ月に短縮できるケースもあります。
実際に、サービスを利用した30代の女性が180万円、50代の男性が198万円の給付金を受け取った実績もあり、その価値は明らかです。
全国どこでもOK!LINEで完結する手軽な申請サポート
「退職バンク」のサポートは、全国どこにお住まいでも利用できるオンライン完結型です。
ハローワークに何度も足を運ぶ時間が取れない方や、地方にお住まいで専門家へのアクセスが難しい方でも、気軽にサービスを受けられます。
主なやり取りはLINEのチャットやオンライン面談で行われるため、自身の都合の良い時間に相談を進められます。
一人で悩みがちな手続きの過程で、「いつでも何度でも専門家に相談できる」環境は、精神的な負担を大きく和らげてくれる頼もしい存在となるでしょう。
まずは無料でチェック!あなたの受給額をLINEで診断してみよう
「専門家のサポートは気になるけれど、まずは自分がいくらくらいもらえるのか知りたい」と考えるのは当然のことです。
そんな方のために、「退職バンク」ではLINEを使った無料の受給額診断を実施しています。
いくつかの簡単な質問に答えるだけで、受け取れる給付金の目安額をすぐに確認できます。
もちろん、診断や相談は無料です。無料診断や相談が、自身の退職後の生活を安心と希望に満ちたものに変えるかもしれません。
自身の可能性を確かめるために、まずは気軽に無料診断を試してみてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【Q&A】退職給付金に関するよくある質問

ここまで退職後にもらえるお金について解説してきましたが、まだ個別具体的な疑問が残っている方もいるでしょう。
ここでは、多くの方が疑問に思う点について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
自己都合退職だと給付金はもらえないのですか?
自己都合での退職であっても、受給条件を満たしていれば失業保険(基本手当)を受け取れます。
ただし、会社の倒産や解雇といった会社都合退職の場合と比較すると、いくつか不利になる点があります。
具体的には、7日間の待期期間の後、さらに原則1ヶ月間の「給付制限期間」が設けられ、この間は給付金が支給されません。
また、給付を受けられる日数「所定給付日数」も、会社都合の場合より短くなることが一般的です。
しかし、パワハラなど正当な理由がある場合は自己都合でも会社都合と同様の扱いになる可能性があります。
これまで、自己都合で退職した場合の給付制限期間は原則2ヶ月(5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月)でした。
しかし、令和7年(2025年)4月1日以降に離職する方については、この給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されます。
ただし、5年間で3回以上自己都合退職をした場合は、引き続き3ヶ月の給付制限となります。
この改正により、自己都合で退職した方でも、より早く生活の安定を図りながら転職活動に専念できるようになります。
参考:厚生労働省
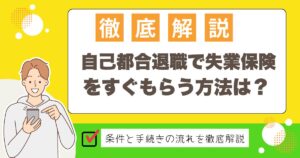
アルバイトをしながら失業保険をもらうことはできますか?
失業保険の受給中にアルバイトをすることは、一定の条件のもとで可能です。
ただし、いくつかの重要なルールを守る必要があります。
まず、申請後の7日間の待期期間中は、原則としてアルバイトはできません。
給付制限期間中や受給期間中のアルバイトは、1週間の労働時間が20時間未満であることなど、時間や収入に制限があります。
そして最も重要なのは、アルバイトをした事実を必ず失業認定申告書で正直に申告することです。
この申告を怠ると不正受給とみなされ、厳しい罰則が科されるため注意が必要です。

退職金の金額は給付金の額に影響しますか?
原則として、退職金の有無やその金額が、失業保険(基本手当)の受給額に直接影響することはありません。
この二つは全く別の制度だからです。
退職金は、あくまで勤務していた会社が独自の規定に基づいて支払う「給与の後払い」的な性質のものです。
一方、失業保険は、国が管理する雇用保険制度に基づいて支払われる公的な給付です。
財源も根拠となる法律も異なるため、高額な退職金を受け取ったからといって、失業保険が減額される心配はありません。
給付金に税金はかかりますか?
雇用保険から支給される失業保険(基本手当)や再就職手当などの給付金は、失業中の生活保障という目的のため、非課税です。
所得税や住民税はかからず、確定申告の必要もありません。
一方、会社から支払われる「退職金」は所得の一種とみなされるため、課税対象となります。
ただし、退職金には大きな控除(退職所得控除)が適用されるため、税負担は他の所得に比べて軽減される場合が多い傾向があります。
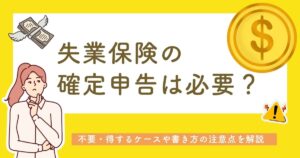
退職後の社会保険料(健康保険・年金)はどうなりますか?
退職すると、これまで会社経由で支払っていた社会保険料を自分で支払う必要があります。
手続き方法を以下の表にまとめたので、参考にしてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
健康保険 | ・以下のいずれかを選択 ①任意継続 ②国民健康保険加入 ③家族の扶養に入る ・保険料の減免制度がある場合もあるため市区町村に確認 |
年金 | ・厚生年金から国民年金への切り替えが必要 ・保険料の免除や猶予制度あり ・年金事務所へ相談を推奨 |
申請に期限はありますか?
失業保険の申請には明確な期限があります。給付金を受け取ることができる期間、すなわち受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
この1年の間に、定められた日数の給付金をすべて受け取り終える必要があります。
そのため、退職後はなるべく早くハローワークで手続きを始めることが重要です。
手続きが遅れると、所定の給付日数が残っていても、1年の期限を過ぎた分は受け取れなくなってしまいます。
ただし、病気や妊娠・出産などで長期間働けない場合は、申請すれば受給期間を最大3年間延長できる特例があります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /

まとめ:正しい知識と専門家のサポートで安心の退職後を迎えよう
この記事では、退職後にもらえる給付金の種類一覧から、具体的な受給額の計算方法、それぞれの条件、そして申請ステップまでを網羅的に解説しました。
退職後の生活を支える公的な支援制度は多様ですが、その内容は複雑です。
しかし、自分がいくらもらえるのか、どのような制度が使えるのかを正しく知ることが、もらい漏れを防ぎ、経済的な不安を解消する最も確実な方法です。
一人で手続きを進めるのが不安な場合は、「退職バンク」のような専門家のサポートを頼るのも賢明な選択といえます。
今回の内容を参考に、自身の状況に合った制度を最大限に活用し、安心して新しいキャリアへの一歩を踏み出してください。
もう一人で悩まない!
退職給付金のことはプロにお任せください
ここまで読んで「やっぱり複雑で難しそう…」と感じたあなたへ。
一番の近道は、専門家に相談することです。
専門家が
徹底サポート
面倒な手続きの
時間を節約
受給額の
最大化を支援
診断・相談は一切無料。無理な勧誘はありません。