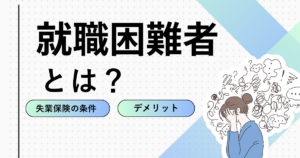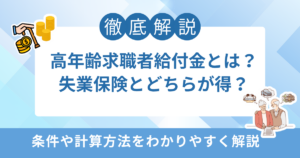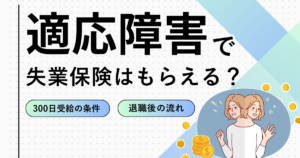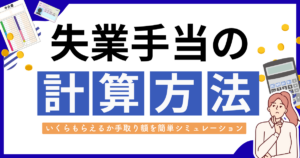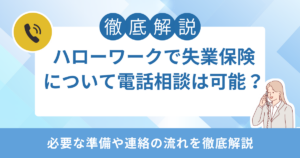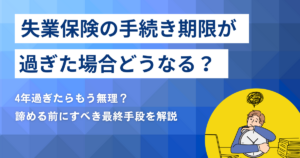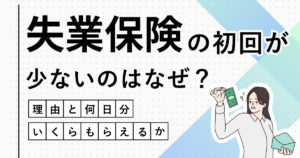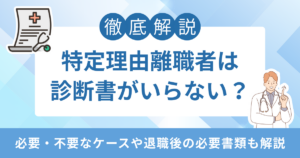休職したら終わりではない!突然でも給料や転職の不安をなくす方法
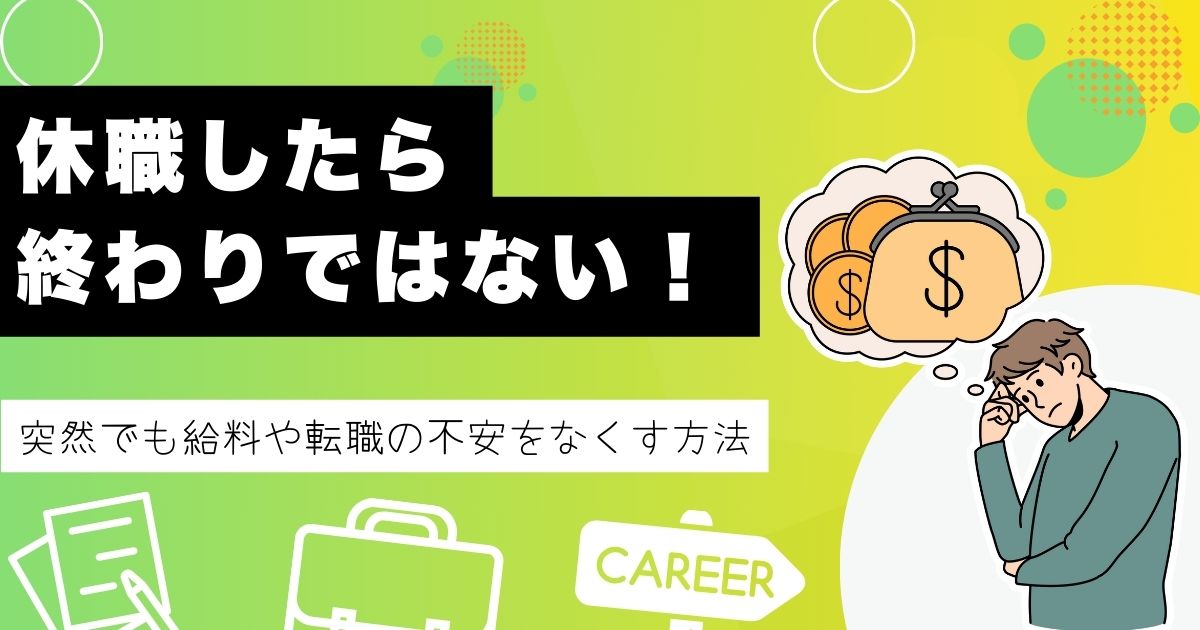
休職は、心身の健康を守りキャリアを継続するための正当な権利です。
しかし、「休職したらキャリアも人生も終わりではないか」「突然休むことで収入や転職活動にどう影響するのか」といった不安を抱く方もいるはずです。
結論として、休職は終わりではなく、正しい知識を持つことで次のステップに向けた戦略的な準備期間となります。
本記事では、「休職したら終わり」と感じる理由を整理し、傷病手当金や失業保険などの公的制度を活用して経済的な不安を解消する方法を解説します。
読み終える頃には、休職後の復職や転職などの具体的な選択肢と、自身が取るべき行動が明確になります。
休職を検討している方、すでに休職中で将来に悩んでいる方は記事を参考に手続きを進めてみてください。
今後の働き方に悩んでいませんか?
あなたに合う選択肢を簡単診断!
2つの質問に答えるだけで、今のあなたに合った行動のヒントが見つかります。
Q1. 今の職場に復帰したいと
強く思いますか?
診断結果
あなたは…復職準備タイプ
まずは心身の回復を最優先に。復職に向けて、会社と業務内容や環境の調整について相談を始めましょう。公的制度をうまく活用して、焦らず準備を進めることが大切です。
復職成功のポイントを見る診断結果
あなたは…転職検討タイプ
無理な復職は再発のリスクも。休職期間をキャリアを見つめ直す好機と捉え、新しい環境への転職を視野に入れてみましょう。経済的な基盤を固めることが、納得のいく転職活動の鍵です。
転職成功のポイントを見る診断結果
あなたは…戦略的退職タイプ
今の環境から一度離れ、心と体をしっかり休ませることが最優先かもしれません。公的制度を最大限活用し、経済的な安心を得ながら、次のステップをじっくり考える「戦略的退職」が有効な選択肢です。
専門家に無料相談してみるこの記事でわかること
【結論】休職は終わりではない!キャリアを見つめ直すための戦略的な期間

「休職したら、もうキャリアは終わりかもしれない」と、強い不安を感じている方もいるでしょう。
しかし、結論からお伝えすると、休職は決して終わりではありません。
むしろ、自身のキャリアや働き方をじっくりと見つめ直すための、大切な準備期間となります。
ここでは、「休職が終わりではない」と断言できる理由について、次の4つの視点から詳しく解説します。
- 「休職したら終わり」と感じる主な3つの理由
- 職場への罪悪感を和らげるための考え方
- 休職がキャリアの終わりではない客観的な事実
- 休職期間を未来への準備期間に変える考え方
ここからは、各項目について詳しく解説します。
休職期間を有効活用するために、まず経済的な見通しを立てることが重要です。
あなたが「いくらもらえるのか」を把握することから始めましょう。
「休職したら終わり」と感じる3つの理由
多くの方が「休職したら終わり」と感じてしまう背景には、主に3つの大きな不安が存在します。
1つ目は、キャリアが中断すると焦る気持ちです。
休んでいる間に同僚に遅れを取るのではないか、これまでの努力が無駄になるのではないか、と不安に感じます。
2つ目は、収入が途絶えることへの経済的な恐怖です。
休職中の給与がどうなるのかわからず、生活が困窮するのではないかと心配になるでしょう。
そして3つ目は、職場への罪悪感や人間関係への懸念です。
突然休むことで周囲に迷惑をかけるのではないか、復帰しても自身の居場所はないのではないか、と不安になります。
これらの不安が重なることで、「もう終わりだ」と思って追い詰められてしまいます。
職場への罪悪感を和らげるための考え方
休職して「職場に迷惑をかけてしまう」と罪悪感を抱く必要はありません。
休職は心身の健康を守るための正当な権利であると理解しましょう。
自身が健やかに働き続けることこそが、会社にとっても長期的にはプラスになります。
また、周囲への伝え方を工夫すれば心理的な負担は軽減できます。
直属の上司や人事担当者には正直に医師の診断結果を伝え、感謝の気持ちを簡潔に伝えることで、円滑なコミュニケーションが取りやすくなるでしょう。
休職を経験してもキャリアを再構築は可能
休職したからといって、キャリアが終わるわけではありません。
実際に、多くの方が休職を経て職場に復帰し、キャリアを再構築しています。
厚生労働省が公表している手引きなどにも、休職者の職場復帰を支援するための情報がまとめられており、国としても労働者の復帰を後押ししています。
また、仮に元の職場に戻らない選択をしたとしても、転職に成功しているケースは多数存在します。
大切なのは、休職した事実そのものではありません。
休職期間をどのように過ごし、心身を回復させたうえで、次のステップに向けて何を準備できたかを説明できることです。
休職は、キャリアの終わりではなく、新たな始まりのきっかけにもなり得ます。
参照元:厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
休職期間を次への準備期間として有効活用しよう
休職期間は、次のキャリアへ進むための大切な準備期間と捉えることが重要です。
まず最優先すべきは、心身を十分に休めて、回復に専念することです。十分な休養が未来へ進むためのエネルギーとなるでしょう。
そして、少しずつ心身が回復してきたら、自身のキャリアプランや理想の働き方について、客観的に見つめ直すよい機会となります。
在職中は忙しくて考えられなかった選択肢を、焦らずにじっくりと検討する時間になります。
すぐに答えを出す必要はありません。信頼できる情報源を参考にしたり、専門家に相談したりしながら、自身のペースで将来の働き方を考えていくことが大切です。
休職中の経済的な不安は公的制度の活用で解消できる

休職を考えるうえで、最も大きな障壁の1つが経済的な不安でしょう。
しかし、日本には万が一の際に生活を支えてくれる公的なセーフティーネットが用意されています。
ここでは、休職中やその後の生活を支える、次の大切な公的制度について解説します。
- 休職中に利用できる「傷病手当金」の概要
- 退職後に利用できる「失業保険(雇用保険)」の概要
- 傷病手当金から失業保険へスムーズに移行する専門的な方法
それぞれの制度について具体的に解説します。
公的制度は複雑で、一人で手続きすると本来もらえる額より損をしてしまうことも。
専門家の知識を活用して、受け取れる金額を最大化しませんか?
まずは健康保険の「傷病手当金」で生活を支えよう
傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
手当金は、いくつかの条件を満たせば、加入している健康保険から支給されます。
支給額の目安は、給与の3分の2程度で、支給期間は最長で1年6か月となります。
申請手続きは、まず全国健康保険協会(協会けんぽ)のWebサイトや勤務先の人事部などから申請書を入手します。
その後、自身で記入する部分に加え、医師と会社にそれぞれ必要な証明を記入してもらい、健康保険組合へ提出しましょう。
制度を活用すれば、休職中の収入の不安を大幅に軽減できるでしょう。
参照元:全国健康保険協会 傷病手当金
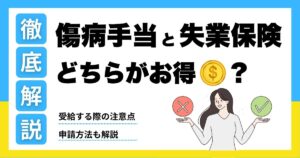
退職後の生活は「失業保険(雇用保険)」で守られる
失業保険は雇用保険の基本手当のことで、会社を退職した後の生活を心配せずに新しい仕事を探し、できる限り早く再就職できるよう支援するための制度です。
原則として、離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることなどが受給の条件となります。
自己都合で退職した場合と、会社の倒産や解雇といった会社都合で退職した場合では、給付金を受け取れるまでの期間や日数が異なります。
また、病気やケガなどですぐに働けない場合は、ハローワークで手続きをすれば、本来1年である受給期間を最大4年まで延長が可能です。
なお、2025年4月1日からは法改正により、自己都合退職者の給付制限期間が一部緩和される点も知っておくとよいでしょう。
参照元:厚生労働省 雇用保険制度
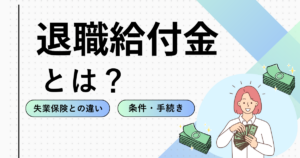
【専門家が解説】傷病手当金から失業保険への最適な移行戦略
傷病手当金と失業保険は、どちらも大切な公的制度ですが、両方を同時に受け取ることはできません。
そのため、制度をスムーズに切り替えるための正しい知識が重要になります。
基本的な流れは、まず在職中または退職直後から傷病手当金を受給し、療養に専念します。
そして、働ける状態まで回復した時点で、ハローワークにて失業保険の受給手続きに切り替えましょう。
療養に専念
在職中または退職後、まずは傷病手当金を受給し、心身の回復に専念します。
受給期間延長の手続き
退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に、ハローワークで失業保険の受給期間延長を申請します。(最重要ポイント!)
回復後に手続き切り替え
働ける状態まで回復したら、傷病手当金の受給を終了し、ハローワークで失業保険の受給手続きを開始します。
失業保険を受給開始
経済的な安心を得ながら、ご自身のペースで再就職活動を進めることができます。
とくに注意すべきなのは失業保険の受給期間延長手続きです。
退職後、病気やケガですぐに働けない場合は、原則として離職日の翌日から30日を過ぎてから早期に自身の住所を管轄するハローワークで延長申請をおこなう必要があります。
手続きを忘れてしまうと、本来受け取れるはずの失業保険が受け取れなくなる可能性があるため、専門家へ相談しましょう。
参照元:厚生労働省 離職されたみなさまへ
休職後の選択肢は復職だけではない

休職後の道は、必ずしも元の職場への復帰のみが正解とは限りません。
自身の心身の状態や職場環境によっては、復職以外の選択肢を検討すれば、よりよい未来につながる場合もあります。
ここでは、無理な復職がもたらすリスクや、新しいキャリアを築くためのポイント、そして具体的なキャリア事例について解説します。
- 無理な復職が再発のリスクを高めるケース
- 休職後の転職活動を成功させるポイント
- 経済的余裕を持つ「戦略的退職」
自身の可能性を広げるために、ぜひ参考にしてください。
無理に復職すると症状が悪化するリスクがある
休職からの復職は、慎重に判断する必要があります。
なぜなら、無理な復職は症状の再発や悪化につながるリスクがあるからです。
とくに、休職の原因となった職場の人間関係や長時間労働といった環境が全く改善されていない場合、復帰しても再び同じ問題に直面し、体調を崩す可能性が高いでしょう。
また、自身の体調が万全でないまま復職すると、以前のようなパフォーマンスを発揮できず、かえって社内での評価が下がる可能性もあります。
復職を判断する前には、必ず主治医や会社の産業医といった専門家と客観的な状況についてよく相談し、本当に働ける状態にあるかを見極めることが大切です。
休職後の転職活動を不利にしないための2つのポイント
休職後の転職活動に、不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、ポイントを押さえれば、休職経験を不利にせず、むしろ前向きなステップになります。
1つ目のポイントは、休職理由をポジティブに説明できるように準備することです。
休職期間を単に休んでいたわけではなく、自己分析やキャリアの見直し、あるいは資格の勉強など、次へのステップに向けて準備していたと伝えられるように考えを整理しましょう。
2つ目のポイントは、経済的な余裕を持つことです。
収入がない状態で転職活動をすると「早く決めなければ」と焦ってしまい、結果として自身に合わない職場を選んでしまう原因になります。
公的制度などを十分に活用し、生活基盤を安定させることが、納得のいく転職を成功させる鍵となります。
経済的な安心を得て次に進む「戦略的退職」も有効
復職が難しいと感じるなら、無理に職場へ戻るのではなく、「戦略的退職」を検討しましょう。
これは、傷病手当金や失業保険といった公的制度の活用を前提に退職し、経済的な安心を確保したうえで、十分な療養と次のキャリアへの準備に時間を充てる考え方です。
専門家のサポートを受けることで、失業保険の受給額を最大化し、お金の心配をせずに、自身のペースで転職活動に専念できるメリットがあります。
これは決して逃げや「終わり」ではありません。
自身の心と体を守り、よりよい未来を築くための、前向きで戦略的な選択といえるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
経済的な不安なく次の一歩へ進むなら「退職バンク」がおすすめ
休職や退職後の経済的な不安を解消し、安心して次の一歩を踏み出すためには、専門家の知識とサポートが不可欠です。
退職給付金申請サポートサービス「退職バンク」は、そのような方の心強い味方となります。
「退職バンク」には、主に3つの大きな特徴があります。
- 専門家による退職給付金申請のフルサポート
- オンライン完結で全国どこからでも相談可能
- 無料の受給額診断
それぞれの特徴について、詳しく解説します。
専門家が失業保険の複雑な申請手続きを徹底サポート
「退職バンク」では、社会保険労務士をはじめとする専門家チームが、自身の状況に合わせた最適な申請プランを提案します。
失業保険の申請手続きは複雑で、一人で進めるためには多くの時間と労力がかかります。
ハローワークでは教えてもらえない、受給額や受給期間を最大化するための専門的なノウハウを提供し、退職後の生活をサポートします。
また、申請準備中に不明な点や不安なことがあれば、チャットを通じていつでも何度でも専門アドバイザーに相談できるため、知識がない方でも安心して手続きを進められます。
全国対応のオンライン相談で場所を問わず利用可能
「退職バンク」のサービスは、すべてオンラインで完結するため、全国どこにお住まいの方でも利用が可能です。
専門家との個別面談から、具体的な書類準備のサポートまで、自宅にいながら進められます。
そのため、地方にお住まいで近くに相談できる場所がない方や、体調面で外出が難しい方でも、安心して質の高いサポートを受けられるメリットがあります。
サービス利用の基本的な流れは、まず無料相談から始まり、Webでの個別面談、契約、そして専門家によるサポート開始の順序で進みます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
LINEで受給額がいくらになるか無料診断できる
「自身が失業保険をいくらもらえるのか、まずは目安を知りたい」と考える方も多いでしょう。
「退職バンク」では、公式LINEアカウントを友だち追加し、簡単な質問に答えると受給できる失業保険の想定額を無料で診断できます。
詳細な個人情報を入力する必要はなく、どなたでも気軽に試すことが可能です。
無料診断の結果をもとに、さらに詳しい話を聞きたいと感じた場合は、そのまま専門家との個別相談を予約できます。
自身の状況を好転させる第一歩として、無料の受給額診断からはじめることをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
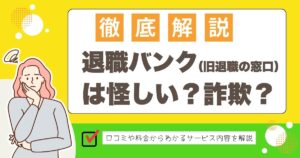
休職や退職に関するよくある質問

ここでは、休職や退職を検討している方から寄せられることの多い、よくある質問とその回答を紹介します。
- 1か月だけの短期休職は可能ですか
- 休職の理由は正直に話すべきですか
- 復職した月の給料はどうなりますか
- 退職代行サービスとの違いは何ですか
自身の疑問や不安の解消のための参考にしてみてください。
1か月だけの短期休職は可能ですか?
1か月だけの短期休職が可能かどうかは、勤務先の就業規則によって決まります。
まずは、自身の会社の就業規則に休職に関する規定があるかの確認が第一歩です。
規定がある場合でも、病気やケガを理由とする休職には医師の診断書が必要になることが一般的です。
また、注意点として、傷病手当金は連続する3日間の待期期間を経て、4日目以降の休業に対して支給されるため、休職期間や出勤日によっては対象とならないケースもあります。
短期の休職を希望する場合は、人事部や労務担当者に就業規則の内容を確認してみましょう。
休職の理由は正直に話すべきですか?
休職の理由を会社に伝える際は、原則として正直に話しましょう。
とくに医師の診断に基づいて休職する場合は、その事実を正確に伝えなければ、傷病手当金の申請に必要な会社の証明を得られない可能性があります。
また、「私用」といった曖昧な理由では、そもそも休職が認められないことも考えられます。
ただし、プライバシーに深く関わる内容など、詳細まで話すことに抵抗がある場合は、相談する相手を選ぶことが重要です。
まずは信頼できる上司や、守秘義務のある産業医、人事担当者などに相談しましょう。
復職した月の給料はどうなりますか?
月の途中で復職した場合、その月の給料は出勤日数に応じて日割りで計算されます。
ただし、会社の給与計算の締め日によっては、注意が必要です。
たとえば、月末締め・翌月25日払いの会社で、締め日以降に復職した場合、その月の給与が支払われるのは翌々月になるケースもあります。
復職直後は、経済的に不安定になりがちなため、事前に人事部や経理担当者に給与の支払日について確認すると安心です。
また、復職後しばらくは時短勤務となる場合も多いため、その分給与額が少なくなる可能性も考慮しましょう。
退職代行サービスとの違いは何ですか?
退職代行サービスと「退職バンク」は、目的が異なる全く別のサービスです。
退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを円満かつ確実に代行することを目的としています。
精神的な負担が大きく、自身で退職を切り出せない方にとって頼りになるサービスです。
一方、「退職バンク」は、退職後の経済的な安定を目的とし、失業保険などの給付金を最大限受け取れるよう、専門家が申請をサポートするサービスです。
すでに退職の意思が固まっている方であれば、両方のサービスを検討すれば、よりスムーズで安心して退職できるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ

本記事では、「休職したら終わり」と感じる不安の内容や休職がキャリアに与える影響と、経済的な不安を乗り越えるための公的制度について解説しました。
休職は決してキャリアの終わりではありません。
傷病手当金や失業保険といった制度を正しく理解し、戦略的に活用すれば、心身の回復に専念しながら、復職や転職といった次のステップへ向けた準備期間になります。
休職後の選択肢で重要なのは、一人で抱え込まず、正確な情報に基づいて判断しましょう。
給付金制度の複雑な手続きや最適な選択については、記事を参考に、自身にとって最良の道筋を検討してください。
より具体的なサポートや個別の受給額診断が必要な場合は「退職バンク」で検索し、無料相談を活用してみてください。
もう一人で悩まない!
経済的な不安なく、次の一歩へ。
複雑な給付金申請は専門家にお任せください。
「退職バンク」があなたの再スタートを力強くサポートします。
専門家が
徹底サポート
面倒な手続きの
時間を節約
受給額の
最大化を支援
参考記事)