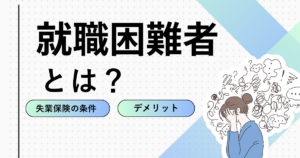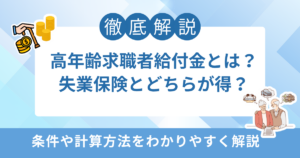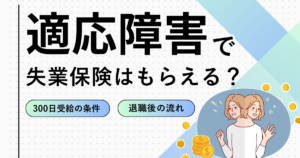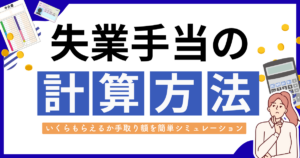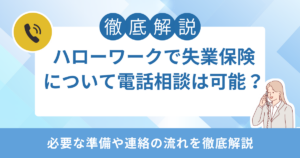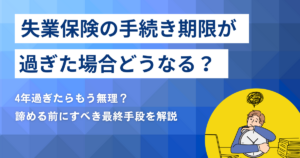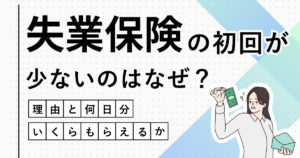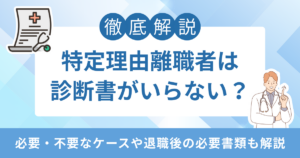失業保険の不正受給がバレる理由は?バレたらどうなるかやペナルティを具体例で解説
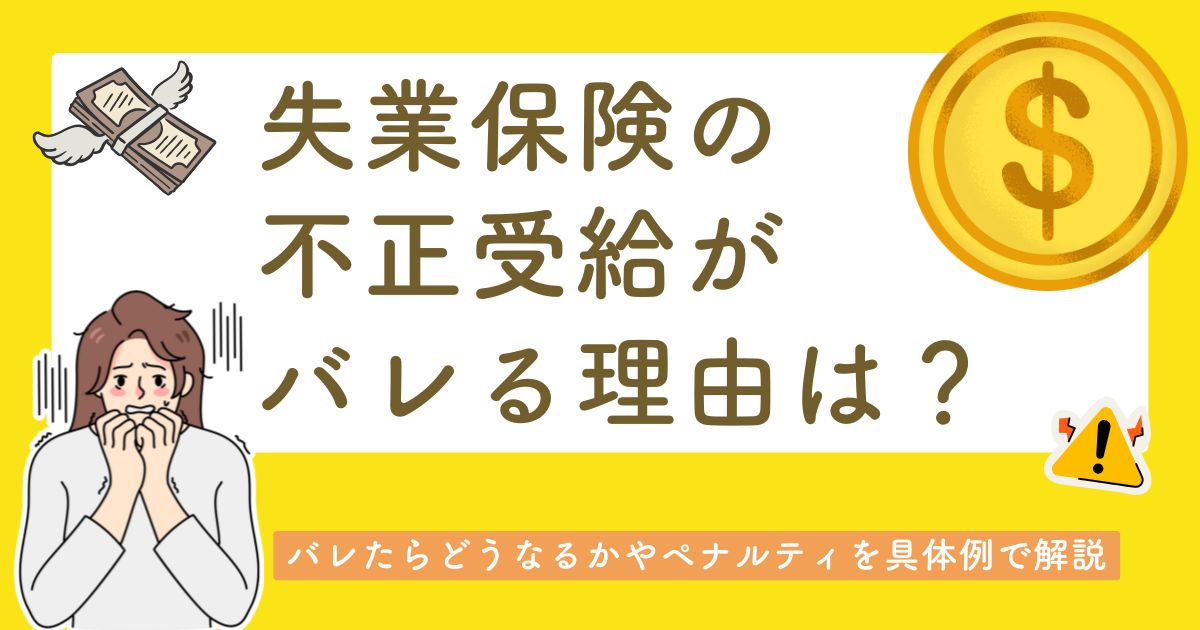
失業保険を受給中に「少しだけならアルバイトしてもバレないだろうか」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
軽い気持ちで得た収入が、後々「不正受給」として深刻な事態を招く可能性があります。
結論として、現代の調査体制では不正受給が発覚する可能性は非常に高く、その代償は決して小さくありません。
本記事では、不正受給がなぜバレるのかという具体的な理由から、発覚した場合に科される重いペナルティ、そしてどのような行為が不正にあたるのかまで詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、安心して失業保険を受給するために、ぜひ参考にしてください。
【結論】失業保険の不正受給は高い確率でバレる

少しだけならバレないだろうという軽い気持ちが、あとで大きな問題に発展する可能性があります。
現代では調査技術が向上し、さまざまな情報が連携されているため、不正受給が発覚しやすくなっているのが実情です。
本記事では、不正受給がなぜバレるのか、その主な理由とリスク、そして正しい知識を持って安心して失業保険を受給する方法について詳しく解説します。
なぜ「バレないだろう」は通用しないのか
少額だから、短期のアルバイトだからといった考えは、もはや通用しないと認識することが大切です。
現在、ハローワークの調査能力は年々向上しています。
とくに、マイナンバー制度が導入されたことにより、国は個人の収入状況を以前よりもはるかに正確に、そして簡単に把握できるようになりました。
このため、申告していない収入が発覚する可能性は格段に高まっています。
軽い気持ちでおこなった行為が、あとで深刻な事態を招くことにならないよう、正しい知識を身につけておくことが重要です。
「バレなかった人」の話を信じてはいけない理由
インターネット上では不正受給をしたがバレなかったといった体験談を見かけることがあるかもしれません。
しかし、こうした匿名の書き込みは証明が不可能であり、信憑性は極めて低いといわざるを得ません。
今は発覚していなくても、数年後に調査が入り、厳しいペナルティを受ける可能性は十分にあります。
他人の無責任な話に惑わされるのは非常に危険です。
失業保険という公的な制度を利用する以上、公式に定められたルールに基づいて行動することが、自身の未来を守る上で最も大切なこととなります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険の不正受給がバレる5つの主な理由

失業保険の不正受給は、さまざまな経路から発覚します。
代表的なものとして、マイナンバーによる所得情報の照合や、新しい勤務先での雇用保険加入履歴が挙げられます。
また、元勤務先や知人といった第三者からの通報も少なくありません。
ここでは、不正受給が発覚する5つの主な理由について、一つひとつ具体的に解説します。
理由1:マイナンバーによる所得情報の照合
現在、ハローワークはマイナンバー制度を活用して、他の行政機関と情報を連携させることが可能です。
具体的には、税務署や市区町村が把握している個人の所得情報を照会できる仕組みです。
そのため、アルバイト先から給与をもらうと、会社が税務署へ提出する支払調書などを通じて収入の事実が記録されます。
この記録とハローワークへの申告内容に食い違いがあれば、不正受給の疑いを持たれる大きな原因となるでしょう。
マイナンバーによって、収入をごまかすことは極めて難しくなっています。
理由2:雇用保険の加入履歴による就労事実の発覚
失業保険の受給中に再就職し、新しい勤務先で雇用保険の加入手続きをおこなうと、その情報はハローワークに必ず通知されます。
この仕組みによって、いつからはじめたかという就労の事実が正確に把握されることになります。
短時間のアルバイトであっても、週の所定労働時間が20時間以上など、一定の条件を満たす場合は雇用保険への加入が義務付けられています。
したがって、雇用保険の履歴を通じて就労の事実を隠し通すことは、事実上不可能であると理解しておきましょう。

理由3:第三者からの通報や密告
不正受給が発覚するきっかけとして、非常に多いのが第三者からの通報です。
これは元勤務先の同僚や上司、あるいは友人や知人など、自身の状況を知る人物からの情報提供によるものです。
たとえば、退職理由に不満を持つ元同僚や、自身の言動を快く思わない人物がハローワークへ連絡するケースが考えられます。
また、SNSに失業保険をもらいながらバイトしているといった内容を不用意に投稿した結果、それを見た誰かが通報するという危険性もあります。
人の口や目は、予想以上に厳しい監視の一因です。
理由4:税務署や市区町村との情報連携
ハローワークは、マイナンバーだけでなく、他の方法でも税務署や市区町村と情報を連携しています。
たとえば、アルバイトなどで得た収入を確定申告した場合や、会社からの給与支払報告書が市区町村に提出された場合、その情報は行政機関の間で共有される可能性があります。
住民税の申告情報などから、ハローワークに申告していない収入があることが発覚するケースも少なくありません。
このように、行政機関は多角的に情報を照合しており、申告漏れを見逃さない体制を整えています。
理由5:ハローワークによる調査や呼び出し
ハローワークは、不正受給を防止するために、定期・不定期にさまざまな調査を実施しています。
不正受給の疑いがある受給者に対しては、まず電話で事実確認がおこなわれることがあります。
さらに疑いが深まると、予告なく自宅へ訪問調査に来たり、ハローワークへの来所を求めて直接面談をおこなったりする場合も考えられます。
失業認定日に、普段より詳しく就労状況について質問されることも調査の一環です。
これらの調査によって、申告内容と実態が異なると判断されれば、不正受給として扱われることになります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
これも対象?不正受給とみなされる具体的なケース

どのような行為が不正受給にあたるのか、その判断に迷う方もいるのではないでしょうか。
たとえ1日だけの短期アルバイトであっても、申告を怠れば不正受給となります。
また、友人からの謝礼や在宅ワークでの収入も対象となる場合があります。
ここでは、不正受給とみなされる具体的なケースについて詳しく解説します。
短期・単発アルバイトやパート
失業保険の受給期間中に、たとえ1日だけの単発アルバイトや、数時間のパートタイマーとして働いた場合でも、その事実を申告しなければ不正受給となります。
金額の大小や労働時間の長短は関係ありません。
最近利用者が増えているタイミーのような、スマートフォンのアプリを通じたスキマバイトも同様です。
働いて収入を得たという事実がある以上、必ず失業認定申告書に記載し、ハローワークに届け出る必要があります。
これくらいなら大丈夫だろうという自己判断が、最も危険な落とし穴となることを覚えておきましょう。
友人・知人の仕事の手伝いと謝礼
友人や知人が経営するお店の繁忙期に少しだけ手伝った、といったケースも注意が必要です。
たとえ善意の手伝いであっても、その対価として現金や品物などの謝礼を受け取った場合、それは就労とみなされ、収入として申告する義務が発生します。
もし金銭の授受が一切ない完全なボランティア活動であれば、通常は就労にあたりません。
しかし、少しでも報酬が発生した場合は、その金額にかかわらず申告が必要です。
人間関係が絡むため判断が難しいかもしれませんが、報酬の有無が重要な判断基準となります。
内職・在宅ワーク・フリマアプリでの収入
内職や、クラウドソーシングサイトなどを利用した在宅ワークで得た収入も、もちろん申告の対象となります。
パソコン一台でできる仕事は、つい申告を忘れがちになるかもしれませんが、これも立派な就労にあたるため注意が必要です。
また、フリマアプリでの収入も判断に迷うポイントでしょう。
基本的には、自宅にある不用品を売却して得た収入は申告の必要はありません。
しかし、利益を得る目的で商品を安く仕入れて高く売るなど、事業性があると判断されるような継続的な活動の場合は、収入として申告しなければならない可能性があります。
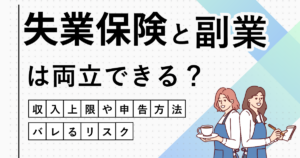
求職活動に関する虚偽の申告
失業保険を受給するためには、原則として月に2回以上の求職活動実績が必要です。
この実績を報告するために、失業認定日に失業認定申告書を提出します。
この申告書に、実際にはおこなっていない求職活動を記載する行為は、虚偽の申告であり不正受給にあたります。
たとえば、応募していない企業に応募したと偽ったり、架空の面接をでっち上げたりするケースがこれに該当します。
求職活動の実績がないにもかかわらず給付金をもらうことは、制度の趣旨に反する重大な不正行為となることを理解してください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
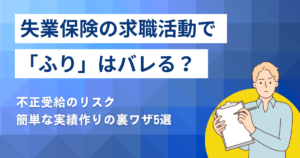
バレたらどうなる?不正受給に科される想像以上に重い3つのペナルティ
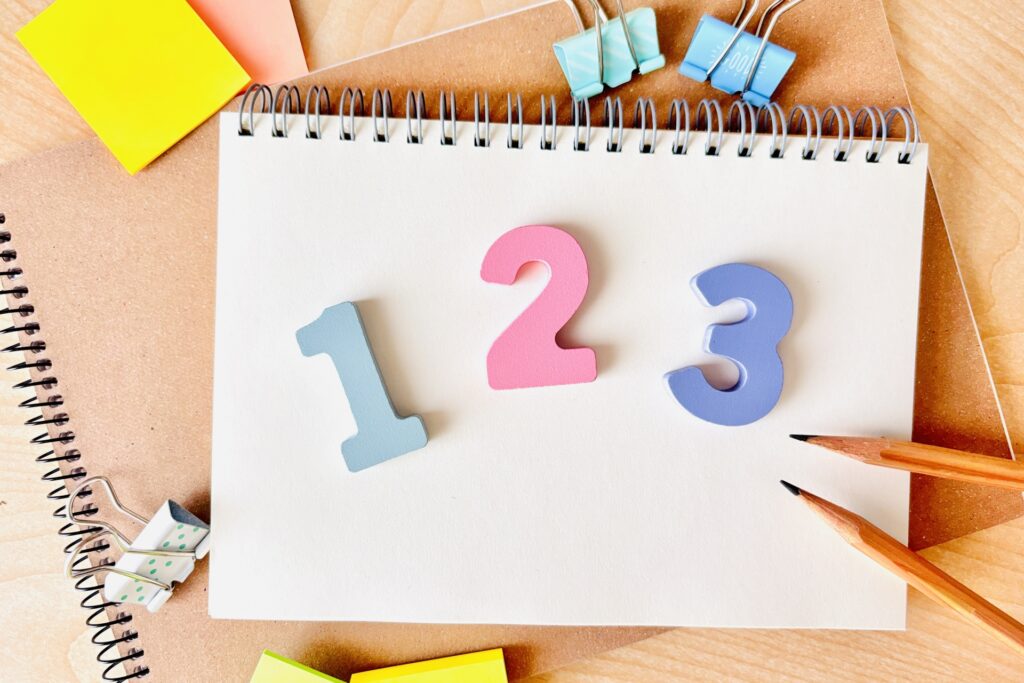
万が一、不正受給が発覚した場合、待っているのは非常に厳しいペナルティです。
もらいすぎた分を返せば終わりというわけではありません。
不正に受給した額の最大3倍の金額を返還する3倍返しや、返還が終わるまでかかり続ける延滞金など、経済的に大きな打撃を受けることになります。
ペナルティ1:給付金の全額返還と最大2倍の追徴金(3倍返し)
不正受給が発覚すると、まず不正に受給した期間に受け取った給付金のすべてを返還するよう命じられます。これを返還命令といいます。
さらに、ペナルティとして、不正に受給した金額の最大2倍にあたる金額の納付が命じられることがあります。これが納付命令です。
つまり、返還分と納付分をあわせると、不正に受け取った額の最大3倍の金額を支払わなければならないことになります。
これが、一般に3倍返しとよばれる厳しい処分です。
軽い気持ちでおこなった不正が、将来の生活を圧迫するほどの大きな金額となって返ってくるのです。
ペナルティ2:返還が完了するまで続く延滞金
返還命令や納付命令で指定された金額を、期限までに支払わなかった場合、さらに延滞金が発生します。
令和6年時点の法令では、この延滞金の利率は年5%と定められています。
この延滞金は、返還が完了する日まで毎日加算されていきます。
つまり、支払いが遅れれば遅れるほど、負担は雪だるま式に膨らんでいくことになるのです。
一度ペナルティを課されると、経済的な負担からなかなか抜け出せなくなる危険性があります。
なお、この利率は将来的に法改正によって変動する可能性もありますので注意が必要です。
ペナルティ3:悪質な場合は詐欺罪として刑事告発も
不正受給の金額が大きい、期間が長い、手口が計画的であるなど、とくに悪質だとハローワークが判断した場合には、単なる行政処分では済みません。
詐欺罪として警察に刑事告発される可能性があります。
詐欺罪で有罪となれば、10年以下の懲役という重い刑罰が科される恐れがあります。
失業保険の不正受給は、知らなかったでは済まされない重大な犯罪行為であるということを、決して忘れてはいけません。
社会的信用を失い、前科がつくという取り返しのつかない事態を招くリスクがあるのです。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【退職バンク】不安な手続きは専門家に相談するのが最も確実で安心
ここまで解説してきたように、失業保険の手続きは複雑で、知らずに不正受給となってしまうリスクも潜んでいます。
もし手続きに少しでも不安や疑問を感じるなら、一人で抱え込まずに専門家に相談するのが最も確実で安心な方法です。
退職後の生活を支える大切な給付金を、正しく有利に受給するために、頼れるサービスを活用することを検討しましょう。
専門家のサポートで知らなかったを防ぎ安心して受給できる
退職バンクのような専門サービスを利用する最大のメリットは、社会保険労務士などの専門家から直接サポートを受けられる点です。
専門家は、個々の状況を丁寧にヒアリングした上で、個々にあわせた最適な申請方法をアドバイスします。
不正受給とならないための注意点はもちろん、どのような申告が必要かについても分かりやすく教えてもらえるため、手続きに関する不安を解消することが可能です。
複雑な制度を前にして一人で悩む必要はなく、安心して大切な給付金をもらうことだけに集中できるでしょう。
LINEで簡単!まずは自身がいくらもらえるか無料診断してみよう
専門家に相談するのは少しハードルが高いと感じる方もいるかもしれません。
そのようなときに便利なのが、退職バンクが提供しているLINEでの無料診断サービスです。
このサービスを利用すれば、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、自身が失業保険をいくらもらえる可能性があるのか、その目安を手軽に知ることができます。
サービスを利用するかどうかを本格的に検討する前に、まずは自身の受給額を把握することからはじめてみてください。
この診断は無料なので、気軽に試せるのが嬉しいポイントです。
全国対応のオンライン面談で時間や場所を選ばず相談できる
退職バンクは、オンラインでの面談とチャットツールを活用しているため、日本全国どこに住んでいる方でもサービスを利用することが可能です。
地方に住んでいる方や、日中は忙しくてハローワークに行く時間が取れないという方でも、自身の都合のよい時間に専門家へ相談できるのは大きなメリットといえるでしょう。
わざわざ特定の場所へ足を運ぶ必要がなく、自宅にいながら専門的なサポートを受けられる手軽さと利便性が、多くの方に選ばれている理由の一つです。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険の不正受給に関するよくある質問

ここでは、失業保険の不正受給に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。
「バレなかった人はいるの?」「時効はあるの?」といった、気になるけれど人には聞きにくい質問にも、分かりやすく解説します。
不正受給が疑われたらどのような流れで調査が進みますか?
もし不正受給が疑われた場合、一般的に以下の流れで調査が進められます。
まず、電話や郵便でハローワークから連絡があり、指定された日時への来所を求められます。
次に、ハローワークの担当者による面談形式での事情聴取がおこなわれます。
その際、疑いのある期間の給与明細や銀行の通帳など、収入を証明する資料の提出を求められることがあります。
提出された資料や事情聴取の内容に基づき、ハローワークが不正受給の事実を認定します。
不正が確定した場合、あとで返還命令通知書などの処分内容が記載された書類が郵送で届きます。
突然の連絡に慌てないためにも、正直に申告することが何より大切です。
不正受給がバレなかった人は本当にいますか?
結論からいうと、ゼロだとは断言できませんが、その可能性は極めて低いと考えるべきです。
現在、マイナンバー制度の活用や行政機関同士の情報連携が強化され、不正受給が発覚するリスクは年々高まっています。
インターネット上にはバレなかったという書き込みがあるかもしれませんが、それは単にまだバレていないだけかもしれません。
数年後に過去の不正が発覚し、厳しいペナルティを科されるケースも実際にあります。
他人の無責任な話を信じるのではなく、自身の未来を守るために、ルールに従って正しく受給することが最も賢明です。
不正受給に時効はありますか?
不正受給には法律上の時効が存在します。
具体的には、不正に受給した給付金の返還を求める権利の時効は2年、そして追徴金などの納付を命じる権利の時効は5年と定められています。
しかし、時効が来れば逃げ切れると考えるのは大きな間違いです。
ハローワークが自身に対して返還を求める通知書を送付した時点で、時効のカウントはリセットされます。これを時効の更新といいます。
そのため、ハローワークが調査を続けている限り、事実上、時効が成立することは極めて困難であると理解しておきましょう。
もし不正受給してしまったら自首すればペナルティは軽くなりますか?
ペナルティが軽くなる可能性があります。
もし、ハローワークによる調査がはじまる前に、自ら不正の事実を正直に申告した場合、いわゆる3倍返しのうち、最大2倍分にあたる追徴金が免除されることがあります。
もちろん、不正に受給した給付金そのものはすべて返還する必要があります。
しかし、追加のペナルティが免除されるのは非常に大きな違いです。
バレるかもしれないと不安な日々を過ごすよりも、不正に気づいた時点で、できるだけ早く勇気を出してハローワークに相談することが、結果的に自身の受けるダメージを最小限に抑える唯一の方法です。
会社の役員になっていると失業保険はもらえませんか?
原則として、株式会社の取締役といった会社の役員は労働者ではなく経営者という立場とみなされるため、雇用保険の被保険者になることができず、失業保険も受給できません。
たとえ名義だけの役員で給与(役員報酬)が支払われていない場合でも、この原則は変わりません。
ただし、例外として、部長などの従業員としての身分も併せ持つ使用人兼務役員で、雇用実態が明確であり、一定の要件を満たす場合には、労働者として扱われ受給できる可能性があります。
この判断は非常に複雑なため、自身のケースが該当するか不安な場合は、専門家へ相談することをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
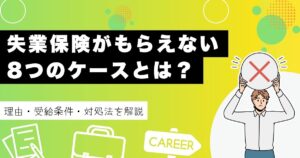
まとめ:不正受給のリスクを理解し専門家のサポートで安心して失業保険を受給しよう

本記事では、失業保険の不正受給がバレる理由と、発覚した場合の重いペナルティについて詳しく解説しました。
マイナンバーによる情報連携や第三者からの通報など、不正が発覚する経路は多岐にわたり、バレないだろうという安易な考えは非常に危険です。
万が一不正受給が発覚すれば、受給額の最大3倍の返還や刑事罰といった、その後の人生を大きく左右する事態になりかねません。
失業保険は、次のステップにすすむための大切な制度です。
もし手続きに少しでも不安がある場合は、一人で抱え込まずに専門家へ相談することが、安心して給付金をもらうための最も確実な方法です。
退職給付金申請サポートサービスの退職バンクでは、専門家が個々の状況にあわせて丁寧にサポートします。
まずは無料診断から、自身の状況を確認してみてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /