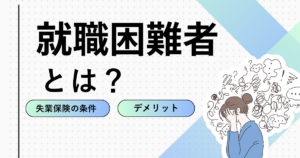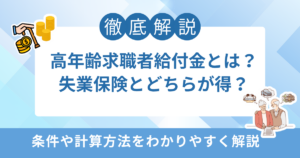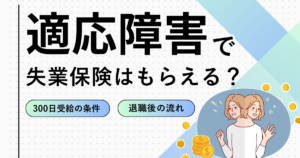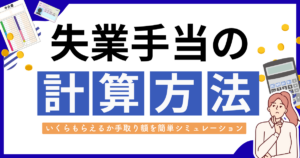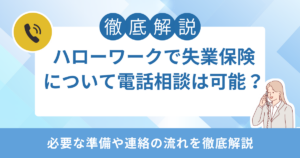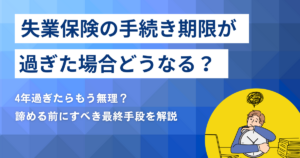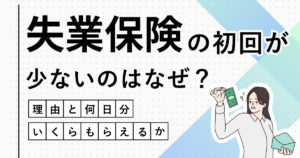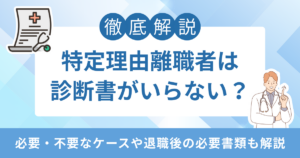退職後のやることリスト一覧!手続きの順番と必要書類を徹底解説

退職後は、失業保険の手続き、健康保険や年金の切り替え、税金の対応など、さまざまな手続きが必要になります。
「何から手をつければよいのだろうか」「手続きの順番や期限はいつまでなのだろうか」と、はじめての退職や久しぶりの退職で戸惑いや不安を感じている方もいるでしょう。
この記事では、そのような方々に向けて、退職後にやるべきことの全体像を「やることリスト」として整理し、必要な手続きの正しい順番、期限、必要書類などを網羅的に解説します。
この記事を読むことで、退職後の手続きに関する疑問や不安が解消され、安心して新しい生活の準備を進めることができるようになります。ぜひ参考にしてください。
退職後にやるべきことの全体像:手続きの順番とやることリストで不安を解消
退職後は、失業保険の手続き、健康保険や年金の切り替え、税金の対応など、さまざまな手続きが必要になります。
「何から手をつければいいの?」「期限はいつまで?」と不安に感じる方も多いでしょう。
ここでは、退職後にやるべきことの全体像を把握し、安心して手続きを進めるためのポイントを解説します。
はじめに、手続きを網羅した「やることリスト」の重要性から説明します。
退職後の手続きを網羅した「やることリスト」で抜け漏れを防ぐ
退職後に必要な手続きは、失業保険の申請、健康保険や国民年金の切り替え、場合によっては確定申告など、多岐にわたります。
これらの手続きにはそれぞれ期限が設けられており、一つでも忘れると不利益を被る可能性も否定できません。
そこで役立つのが、やるべきことを一覧化した「やることリスト」です。
リストを作成し活用することで、手続きの抜け漏れを防ぎ、効率的に進めることができるため、精神的な安心にもつながるでしょう。
リストには、手続きの名称、申請場所、期限、必要書類などを記載しておくことをおすすめします。
これで安心!退職後の手続き「基本の順番」と「期限の目安」
退職後の手続きをスムーズに進めるためには、基本的な順番とそれぞれの期限を把握しておくことが大切です。
一般的には、まず会社から必要な書類をもらい、その後、失業保険の手続き、健康保険や年金の切り替え手続きへと進むのが効率的です。
たとえば、健康保険や国民年金の手続きは、退職日の翌日から14日以内におこなう必要があります。
また、失業保険の手続きは、離職票が届き次第、なるべく早くハローワークでおこなうのがよいでしょう。
これらの手続きを適切な順番で、期限内におこなうことで、二度手間を防ぎ、給付金の受給や新しい保険への加入がスムーズになります。
自身の状況にあわせて、計画的に手続きを進めていくことが重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【一覧表】退職後にやるべきことチェックリスト:期限と窓口も確認
退職後に必要な手続きは多岐にわたるため、ここで一度チェックリスト形式で整理してみましょう。
このリストを確認することで、やるべきことの全体像が明確になり、「自分にもできるかも!」と前向きな気持ちで手続きに取り組めるはずです。
| 手続きの種類 | 主な内容 | 期限の目安 | 主な窓口 | 必要なもの(代表例) |
|---|---|---|---|---|
| 会社から書類受領 | 離職票、源泉徴収票など必要書類の受け取り | 退職後速やかに (会社規定による) | 退職した会社 | – |
| 健康保険の手続き | 国民健康保険への加入、または任意継続、家族の扶養に入る | 【国保・年金】退職日の翌日から14日以内 【任意継続】20日以内 | お住まいの市区町村役場、健康保険組合、扶養者の勤務先 | ・健康保険資格喪失証明書 ・マイナンバーカード ・印鑑など |
| 年金の手続き | 国民年金への切り替え(第1号被保険者)、または家族の扶養に入る | 退職日の翌日から14日以内 | お住まいの市区町村役場、年金事務所 | ・年金手帳または基礎年金番号通知書 ・離職票など |
| 失業保険の手続き | 求職の申し込み、基本手当の受給申請 | 離職票到着後、できるだけ速やかに | お住まいの地域を管轄するハローワーク | ・離職票 ・マイナンバーカード ・写真 ・印鑑 ・預金通帳など |
| 税金の手続き | 住民税の支払い方法変更、所得税の確定申告(必要な場合) | 退職時期や再就職状況による | お住まいの市区町村役場、税務署 | ・源泉徴収票 ・各種控除証明書など |
| その他 | 退職金の確認、財形貯蓄の手続きなど | 会社規定や状況による | 退職した会社、金融機関など | 状況により異なる |
上記は一般的な例です。自身の状況によって必要な手続きや書類、期限が異なる場合があるため、必ず関係各所に確認してください。
このリストを参考に、自身の「やることリスト」を作成し、一つずつ着実に進めていきましょう。
そうすれば、スムーズに退職後の生活をスタートできます。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【最優先】退職後すぐにおこなうべき手続き:期限と必要書類を確認
退職したら、まず取り掛かるべき優先度の高い手続きがいくつかあります。とくに健康保険や年金の切り替えは、期限が短いものもあるため注意が必要です。
ここでは、会社からもらうべき書類の確認と保管、そして健康保険と国民年金の手続きについて、それぞれ必要な書類や期限などを具体的に解説していきます。
これらの手続きを確実におこなうことで、退職後の生活を安心してスタートさせることができるでしょう。
退職時に会社からもらう重要書類:失くさず確認!手続きの基本
退職時には、会社からいくつかの重要な書類が交付されます。
これらの書類は、その後の失業保険の申請、健康保険や年金の切り替え、確定申告など、さまざまな手続きに必要となるため、もらったら内容を確認し、紛失しないように大切に保管しましょう。
【主な必要書類】
- 離職票(1および2)
└失業保険の申請に必須 - 雇用保険被保険者証
└雇用保険に加入していた証明 - 健康保険資格喪失証明書
└国民健康保険への加入や健康保険の任意継続手続きに必要 - 源泉徴収票
└その年に退職した場合確定申告や転職先での年末調整に必要 - 年金手帳または基礎年金番号通知書
└国民年金への切り替え手続きなどで必要
これらの書類が揃っているか、記載内容に誤りがないかを必ず確認してください。
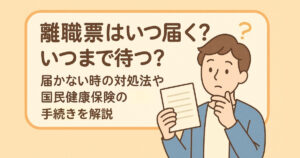
健康保険の切り替え手続き:退職日の翌日から14日以内に対応
退職すると、それまで加入していた会社の健康保険の資格を失うため、速やかに新しい健康保険への加入手続きが必要です。
主な選択肢としては、住まいの市区町村が運営する国民健康保険に加入する、会社の健康保険を任意継続する、または家族の健康保険の扶養に入る、という3つが挙げられます。
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に住まいの市区町村役場の窓口でおこないます。
健康保険資格喪失証明書や本人確認書類などが必要です。
任意継続は、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があるなどの条件を満たせば、最長2年間、退職した会社の健康保険に引き続き加入できる制度で、退職日の翌日から20日以内に申請します。
いずれの手続きも期限が重要なため、早めの対応を心がけましょう。
国民健康保険と任意継続:どちらを選ぶ?メリット・デメリットと保険料の考え方
退職後の健康保険選びで悩むのが、「国民健康保険」と「任意継続」のどちらを選ぶかという点です。
国民健康保険とは、主にお住まいの市区町村が運営する公的な医療保険制度で、自営業の方や退職された方などが加入します。
一方、任意継続被保険者制度(任意継続)とは、退職後も一定の条件を満たせば、それまで加入していた会社の健康保険に最長2年間引き続き加入できる制度です。
それぞれにメリット・デメリットがあり、保険料の計算方法も異なります。
自身の状況に合わせて最適な選択ができるよう、ここで比較してみましょう。
| 比較項目 | 国民健康保険 | 任意継続被保険者制度 |
|---|---|---|
| 主なメリット | ・前年の所得によっては保険料が任意継続より安くなる場合がある ・保険料の減免制度が利用できる場合がある ・扶養という概念がないため家族それぞれが被保険者となる | ・在職中とほぼ同等の給付内容を継続できる ・扶養家族がいる場合追加の保険料なしで扶養を継続できることが多い ・退職時の標準報酬月額に基づいて保険料が決まるため収入が不安定な退職直後でも保険料の見通しが立てやすい |
| 主なデメリット | ・前年の所得が高いと保険料が高額になる場合がある ・自治体によって保険料率や計算方法が異なる ・傷病手当金や出産手当金がない | ・保険料は全額自己負担となる ・原則として2年間継続となり途中で国民健康保険に切り替えることは特別な理由がない限り難しい場合がある ・国民健康保険のような保険料の減免制度は基本的にない。 |
上記を比較すると、一概にどちらが良いとは言えません。以下の点を考慮して、自身で比較検討することが大切です。
- 前年の所得: 国民健康保険料に大きく影響
- 扶養家族の有無: 任意継続の場合扶養家族の保険料負担がないメリットあり
- 必要な保障内容: 傷病手当金などの給付が必要かどうか
- 保険料の比較: 必ず両方の保険料を試算し比較
市区町村役場や加入していた健康保険組合に問い合わせて、具体的な保険料や給付内容を確認し、自身のライフプランや経済状況に合った選択をしてください。
国民年金への切り替え手続き:退職後14日以内に種別変更が必要
会社員や公務員の方は厚生年金に加入していますが、退職して自営業者になる場合や無職になる場合は、国民年金への切り替え手続きが必要となります。
具体的には、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きです。
この手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住まいの市区町村役場の年金担当窓口でおこないます。
手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類(離職票や健康保険資格喪失証明書など)、本人確認書類などが必要です。
また、配偶者の扶養に入る場合は、国民年金第3号被保険者としての手続きを配偶者の勤務先を通じておこないます。
手続きを忘れると、将来もらう年金額に影響が出たり、未納期間が発生したりする可能性があるので注意しましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険(雇用保険の基本手当)の手続き:受給資格から申請方法までわかりやすく解説
退職後の生活を支える上で重要な役割を果たすのが、失業保険、正しくは雇用保険の基本手当です。
これは、働く意思と能力のある方が、次の仕事を見つけるまでの間、安心して求職活動に専念できるよう支援する制度です。
ここでは、失業保険の受給資格や必要な書類、ハローワークでの申請手続きの流れ、そして気になる受給額や期間について、わかりやすく解説していきます。
自身が対象となるか、どのような準備が必要かを確認しましょう。
失業保険(基本手当)をもらうための条件:対象かまずは確認
失業保険(基本手当)をもらうためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間、つまり雇用保険に加入して働いていた期間が12か月以上あることが原則です。
ただし、倒産や解雇など会社都合による離職の場合や、正当な理由のある自己都合退職の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あればよいとされています。
加えて、働く意思と能力があり、積極的に求職活動をおこなっているにもかかわらず、就職できない状態であることが必要です。
病気やケガですぐに働けない場合や、学業に専念する場合などは対象となりません。
自身の状況がこれらの条件にあてはまるか、まずは確認することが大切です。
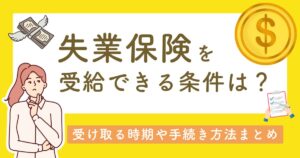
失業保険の申請に必要な書類:事前に準備してスムーズな手続きを
失業保険の申請手続きをスムーズに進めるためには、事前に必要な書類をしっかりと準備しておくことが重要です。
ハローワークで手続きをおこなう際に、不備がないように確認しましょう。
【主な必要書類】
- 離職票(1および2)
└退職した会社から交付 - マイナンバーカード
└個人番号を確認できる書類として必要 - 写真
└最近撮影した正面上半身のもの(縦3.0cm×横2.5cm)を2枚 - 印鑑
└認印でOK - 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
└基本手当の振込先として指定する口座のもの
これら以外にも、状況によってハローワークから追加の書類提出を求められる場合があります。
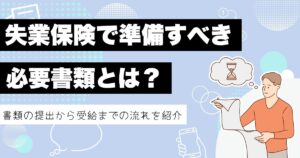
ハローワークでの失業保険申請手続き:全体の流れとポイント
失業保険の申請手続きは、住まいの地域を管轄するハローワークでおこないます。
まず、求職の申し込みをおこない、持参した書類を提出して受給資格の決定を受けましょう。
その後、指定された日時に開催される雇用保険説明会に参加し、失業保険制度についての説明を受け、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらいます。
受給資格が決定すると、原則として4週間に一度、失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書に求職活動の状況などを記入して提出し、失業の認定を受けます。
この認定を経て、基本手当が指定した口座に振り込まれるという流れです。
求職活動を誠実におこなっていることが認定の前提となるため、ハローワークの指示に従って活動を進めましょう。
失業保険はいつから・いくらもらえるか:待機期間・給付制限・給付日数を理解
失業保険が実際にいつから、どのくらいの期間、いくらくらいもらえるのかは、多くの方が気になるところでしょう。
まず、受給資格決定日から7日間は「待機期間」とされ、この期間は基本手当が支給されません。
自己都合退職や懲戒解雇などの場合は、この待機期間満了後、さらに1か月または3か月の「給付制限期間」が設けられることがあります。
1日あたりの支給額である「基本手当日額」は、離職時の賃金日額に基づいて計算されます。
また、基本手当が支給される日数である「所定給付日数」は、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって90日から360日の間で決まります。
自身の状況によってこれらの条件は異なるため、ハローワークで十分に確認することが大切です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
税金に関する手続き:住民税・所得税や退職後の対応を知る
退職後には、健康保険や年金だけでなく、税金に関する手続きも忘れずにおこなう必要があります。
とくに住民税と所得税については、支払い方法の変更や、場合によっては確定申告が必要になることがあるでしょう。
ここでは、退職後の住民税の取り扱いと、所得税の精算(年末調整または確定申告)について、それぞれどのような対応が必要になるのかを解説します。
あとで慌てないように、事前に確認しておきましょう。
退職後の住民税:支払い方法が変わるので注意が必要
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納める仕組みになっています。
在職中は毎月の給与から天引き、つまり特別徴収されている方がほとんどですが、退職するとこの特別徴収ができなくなるため、支払い方法の変更手続きが必要です。
退職時期によって対応が異なり、たとえば1月1日から5月31日までに退職した場合は、最後の給与や退職金から5月までの住民税が一括で徴収されることが一般的です。
6月1日から12月31日までに退職した場合は、市区町村から送られてくる納付書を使って自身で納付する普通徴収に切り替わるか、希望すれば最後の給与や退職金から翌年5月分までを一括徴収してもらうことも可能でしょう。
転職先が決まっている場合は、手続きをすれば引き続き特別徴収を継続できます。
所得税の精算:年末調整と確定申告どちらが必要か
所得税は、毎月の給与から源泉徴収という形で天引きされていますが、これはあくまで概算の金額です。
そのため、年末に正しい所得税額を計算し、過不足を調整する年末調整がおこなわれます。
年内に再就職した場合は、新しい勤務先で年末調整がおこなわれるため、前職の源泉徴収票を提出すれば、自身で特別な手続きをする必要はありません。
しかし、年内に再就職しなかった場合や、医療費控除など年末調整では対応できない控除を受けたい場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間に、自身で確定申告をおこなう必要があります。
確定申告をおこなうことで、払い過ぎた所得税が還付されることもあるため、該当する方は忘れずに手続きをおこないましょう。
確定申告には、退職した会社から交付される源泉徴収票などが必要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【専門家監修】退職後の手続きをスムーズに進めるなら「退職バンク」へ相談
退職後の手続きは種類が多く、期限も細かく決まっているため、一人ですべてを完璧にこなすのは大変だと感じる方もいるでしょう。
そのようなとき、専門家のサポートがあれば心強いものです。
「退職バンク」では、社会保険労務士という専門家が、失業保険やその他給付金の申請をスムーズに進めるためのお手伝いをしています。
ここでは、「退職バンク」が提供するサービス内容や、専門家のサポートを受けるメリットについて紹介します。
「退職バンク」のサポート内容:複雑な手続きも専門家がしっかりお手伝い
「退職バンク」では、社会保険労務士という国の認可を受けた専門家が、退職後の失業保険やその他の社会保険給付金の申請に関するサポートを提供しているサービスです。
具体的には、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、どの給付金がもらえる可能性があるのか、そのためにはどのような手続きを、いつまでにおこなう必要があるのかといった点をわかりやすくアドバイスします。
また、申請に必要な書類の作成サポートや内容の確認、手続き全体の流れの個別案内などもおこないます。
ここで大切なのは、「退職バンク」は退職代行サービスではないという点です。
あくまで、退職後の各種給付金申請を円滑に進めるための「申請サポート」に特化しており、お客様一人ひとりの状況にあわせた最適な受給プランの提案を心がけています。
なぜ専門家のサポートが必要か:メリットを具体的に解説
退職後の手続きは、法律や制度がかかわるため、専門知識がないと理解が難しかったり、最新の情報を把握しきれなかったりすることがあります。
社会保険労務士のような専門家は、これらの制度に精通しており、法改正にも迅速に対応しています。
そのため、専門家のサポートを受けることで、申請漏れや書類の不備といったミスを防ぎ、給付金のもらいが遅れたり、最悪の場合もらえなくなったりするリスクを大幅に減らすことができるでしょう。
また、自身では気づきにくい、より有利な制度の活用方法についてアドバイスをもらえる可能性もあります。
何より、複雑で手間のかかる手続きを専門家に任せることで、時間的・精神的な負担が軽減され、安心して新しい生活の準備や求職活動に集中できるという大きなメリットがあるでしょう。
「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫かな」といった不安も、専門家になら気軽に相談できます。
「退職バンク」を利用するメリット:LINE無料診断や無料相談も
「退職バンク」を利用することで、多くのメリットを実感できます。
まず、社会保険労務士という国家資格を持つ専門家による、質の高いサポートが受けられる点が最大の強みです。
複雑な制度内容も、お客様の状況にあわせてわかりやすく説明し、最適なアドバイスを提供します。
また、相談は全国どこからでもオンラインで可能なため、住まいの地域にかかわらずサポートを受けられるでしょう。
さらに、「退職バンク」では、LINEを通じて、自身がもらえる可能性のある給付金の想定額を無料で診断するサービスも提供しています。
まずは手軽に試してみたいという方におすすめです。初回の相談料は無料なため、退職後の手続きに少しでも不安や疑問がある方は、お気軽に現状をお話しください。
専門家の力を借りて、煩雑な手続きから解放され、スムーズな次のステップへと進みましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
退職後の手続きに関するよくある質問
退職後の手続きを進める中で、さまざまな疑問や不安が出てくることでしょう。ここでは、多くの方が抱きやすい質問とその回答をまとめました。
「期限を過ぎてしまったら」「会社が書類を出してくれない」「失業保険をもらいながら働けるの」など、具体的なケースについて解説します。
これらを参考に、疑問を解消し、安心して手続きを進めてください。
退職してから14日を過ぎてしまった手続きはどうすればよい?
健康保険や国民年金の手続きなど、退職後の手続きの中には「退職日の翌日から14日以内」といった期限が設けられているものがあります。
この期限の重要性を認識しておくことは大切です。もし、うっかり期限を過ぎてしまった場合は、放置せずに、まずは速やかに住まいの市区町村役場の担当窓口や年金事務所に相談しましょう。
期限を過ぎたからといって、直ちに手続きができなくなるわけではありませんが、状況によっては何らかのペナルティが発生する可能性も考慮しなければなりません。
たとえば、健康保険の手続きが遅れると、保険料を遡って支払う必要が出たり、一時的に医療費を全額自己負担しなければならない無保険期間が生じたりするリスクがあります。
正直に状況を説明し、指示を仰ぐことが重要です。

会社がなかなか離職票を発行してくれない場合はどうすればよい?
失業保険の申請に不可欠な離職票ですが、退職した会社からなかなか発行されないというケースも残念ながらあるようです。
会社は、従業員が退職した場合、原則として退職日の翌日から10日以内にハローワークへ離職証明書を提出し、ハローワークから交付された離職票を退職者に渡す義務があります。
まずは、退職した会社の人事担当者などに、丁寧かつ明確に離職票の発行を依頼しましょう。
それでも対応してもらえない、あるいは連絡が取れないといった場合は、住まいの地域を管轄するハローワークに相談することをおすすめします。
ハローワークから会社へ発行を促してくれる場合があります。
離職票の発行が遅れると、失業保険のもらい開始も遅れてしまう可能性があるため、早めの対応が肝心です。
失業保険の受給中にアルバイトやパートはできる?
失業保険の受給中に、生活費の足しにするためや、社会とのつながりを保つためにアルバイトやパートをしたいと考える方もいるでしょう。
原則として、失業保険の受給中にアルバイトやパートをすることは可能ですが、いくつかの注意点があります。
まず最も重要なのは、アルバイトやパートをした場合は、必ず失業認定申告書にその事実を正直に申告することです。
収入額や労働時間によっては、基本手当が減額されたり、支給が先送りになったりする場合があります。
具体的には、1日の労働時間が4時間以上の場合や、週の労働時間が20時間以上で雇用保険の加入対象となるような働き方をした場合は、就職したとみなされることがあります。
ハローワークの指示に従い、不正受給とならないよう十分に注意しましょう。

家族の扶養に入りたいのだがどのような手続きが必要?
退職後、収入が一定額以下になるなどの条件を満たせば、家族の健康保険や年金の扶養に入ることができます。
健康保険の被扶養者になるためには、主に年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることなどが一般的な条件です。
年金の場合は、国民年金第3号被保険者として、保険料を自身で納める必要がなくなります。
手続きは、扶養者である家族が勤務している会社の健康保険組合や、年金事務所を通じておこないます。
必要な書類としては、自身の収入を証明する書類(退職証明書や課税証明書など)や、続柄を確認できる書類(住民票など)が求められるのが一般的です。
詳細は扶養者の勤務先や加入している健康保険組合に確認しましょう。
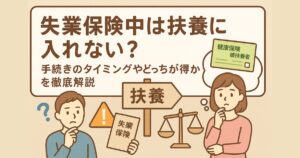
退職金はいつ頃もらえる?
退職金の支給時期は、法律で明確に定められているわけではなく、会社の就業規則や退職金規程によって異なります。
一般的には、退職後1か月から2か月程度で支払われることが多いようですが、事前に会社の担当部署に確認しておくのが確実です。
退職金には所得税と住民税がかかりますが、他の所得とは分離して計算され、「退職所得控除」という大きな控除があるため、税負担が軽減される仕組みになっています。
税金の計算を適切におこなってもらうためには、退職時に会社から渡される「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することが重要です。
これを提出しないと、一律20.42%の所得税が源泉徴収され、あとで自身で確定申告をして精算する必要が出てくる場合があります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ:退職後の手続きは「やることリスト」で計画的に
この記事では、退職後に必要な手続きの全体像、正しい順番、そして各手続きに必要な書類について詳しく解説しました。
失業保険、健康保険、年金、税金といった主要な手続きは、それぞれ期限や窓口が異なるため、事前に「やることリスト」を作成し、計画的に進めることが非常に重要です。
手続きの漏れや遅延は、経済的な不利益や生活への支障につながる可能性があります。
本記事で紹介した情報を参考に、自身の状況にあわせて必要な手続きを確実に進め、安心して新しい生活をスタートさせてください。
もし手続きに不安がある場合は、専門家への相談も検討し、円滑な移行を目指しましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /