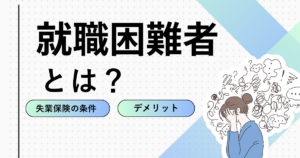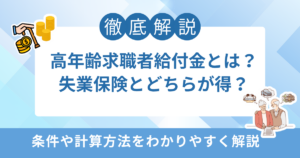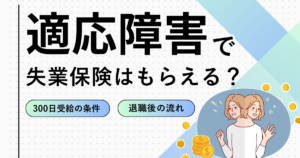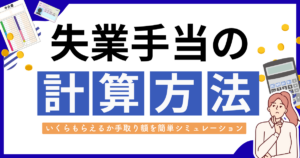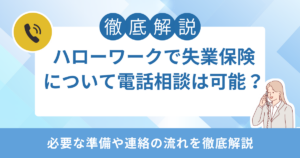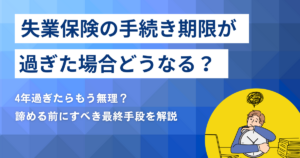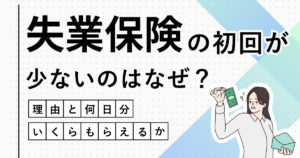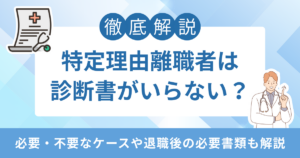失業保険中は扶養に入れない?手続きのタイミングやどっちが得かを徹底解説
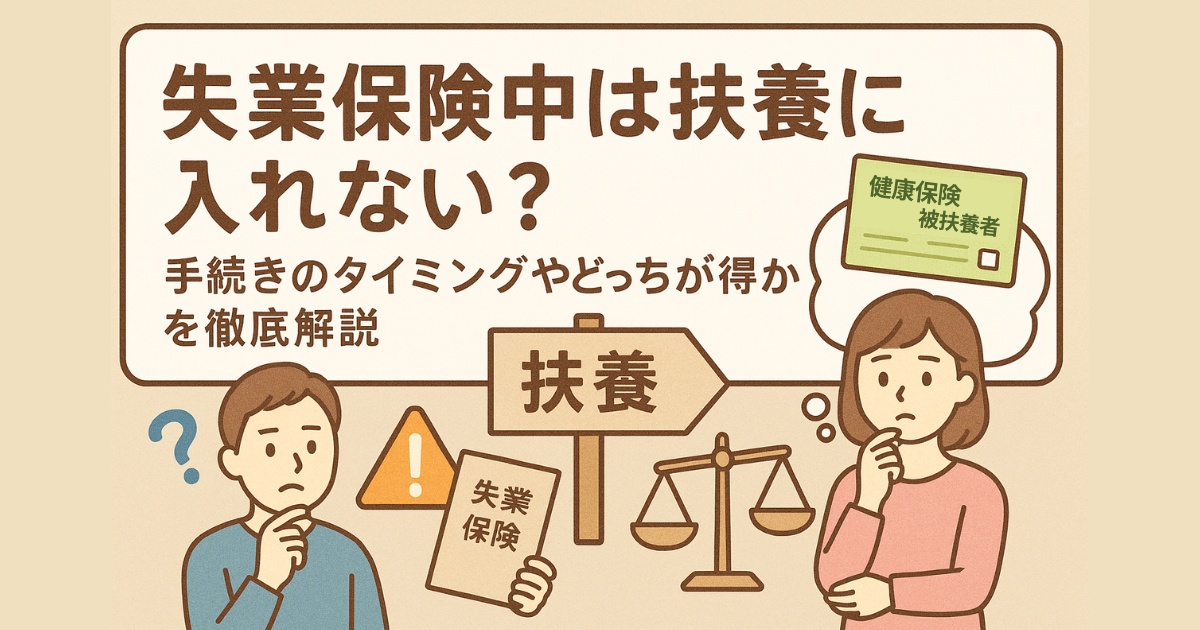
退職後、「失業保険を受け取りながら配偶者の扶養に入れるのか」「失業保険と扶養、結局どっちが得なんだろう」と悩んでいませんか。
また、複雑な手続きに不安を感じたり、もし間違えたらどうしようと心配になったりする方もいるでしょう。
結論として、失業保険の受給中は、収入基準(特に日額)により原則として扶養に入ることはできません。
この記事では、扶養に入れない理由、失業保険と扶養の損得比較、正しい手続きのタイミングと方法、そして手続きを誤った場合のリスクと対処法まで、網羅的に解説します。
ぜひ最後までお読みください。
【結論】失業保険の受給中は原則として扶養に入れない
退職後、失業保険を受け取りながら配偶者などの扶養に入れるのか、多くの方が疑問に思う点でしょう。
結論からお伝えすると、失業保険の基本手当を受給している期間は、原則として健康保険や年金の扶養に入ることはできません。
これは、失業保険が生活保障を目的とした収入とみなされるためです。
ここでは、なぜ扶養に入れないのか、その判断基準となる収入の考え方、そして例外的に扶養に入れるケースについて詳しく解説します。
失業保険(基本手当)受給中は原則扶養外となる理由
健康保険における被扶養者とは、主に被保険者によって生計を維持されている方を指します。
失業保険の基本手当は、失業中の生活を支えるための給付金であり、これを受け取っている間は一定の収入があるとみなされ、自立して生計を立てることが可能と判断されるのが一般的です。
そのため、多くの場合、基本手当の受給額が健康保険組合などが定める被扶養者の収入基準を超えてしまい、扶養の対象から外れることになります。
被扶養者の認定基準は、加入している健康保険によって細部が異なる場合もありますが、基本手当が収入と見なされる点は共通しています。
なぜ扶養に入れない?健康保険法上の考え方
健康保険法では、被扶養者となるための要件の一つに、被保険者によって生計が維持されていることを挙げています。
失業保険の基本手当は、再就職までの生活を保障するための所得と解釈されるため、受給中は生計を維持されている状態とは認められにくいのです。
ただし、具体的な扶養の認定基準や運用は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業の健康保険組合によって異なる部分もあります。
そのため、最終的な判断については、自身が加入している、あるいは加入を検討している健康保険組合に確認することが最も確実な方法といえるでしょう。
扶養に入れるかの判断基準は「日額」で判断
扶養に入れるかどうかの収入基準として「年収130万円未満」という数字を聞いたことがある方も多いでしょう。
しかし、失業保険の基本手当を受給する場合、判断基準は年収ではなく「日額」で見るのが一般的です。
具体的には、基本手当の日額が3,612円未満(60歳以上または障害者の場合は日額5,000円未満)であることが、多くの健康保険組合で目安とされています。
これは、失業保険が将来にわたって継続する収入ではないため、受給期間中の収入見込みを日額で判断するためです。
自身の基本手当日額は、ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」で確認できます。この日額が基準を超える場合は、原則として扶養には入れません。
例外:待機期間や給付制限期間中は扶養に入れる場合がある
失業保険の基本手当を受給している間は原則扶養に入れませんが、例外となる期間があります。
それは、失業保険の申請手続き後、給付が開始されるまでの「待機期間(7日間)」と、自己都合退職などの場合に設けられる「給付制限期間(通常1か月または3か月)」です。
これらの期間中は、失業保険からの給付、つまり収入がない状態となるため、扶養の収入基準を満たす可能性があります。
もしこの期間中に扶養に入った場合は、給付が開始された時点で速やかに扶養から外れる手続きが必要になります。
タイミングを間違えないよう、手続きの流れを事前に把握しておきましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険と扶養 | 自身にとって「どっちが得か」を比較検討しよう
失業保険を受給するか、それとも扶養に入るか。退職後の生活設計において、どちらが経済的に有利なのかは非常に重要なポイントです。
「どっちが得か」は、個々の状況によって異なります。
ここでは、それぞれの選択肢におけるメリット・デメリットを整理し、どのような場合にどちらが得になりやすいのか、パターン別に解説します。
自身の状況を当てはめながら、最適な選択をするためのヒントを見つけていきましょう。
後悔のない選択をするために、じっくり比較検討することが大切です。
失業保険を受給するメリット・デメリット
| メリット | ・まとまった給付金を受け取れる ・求職活動に専念するための経済的な基盤となる ・条件を満たせば再就職手当など他の手当を受けられる可能性もある |
|---|---|
| デメリット | ・国民健康保険料・国民年金保険料を自身で負担する必要がある ・ハローワークでの求職活動や失業認定など所定の手続きが必要となる ・受給期間や金額には上限がある |
失業保険を受給する最大のメリットは、やはり経済的な支援を受けられる点です。
一方で、社会保険料の自己負担が発生する点は考慮すべきでしょう。手続きの手間もデメリットと感じる方がいるかもしれません。
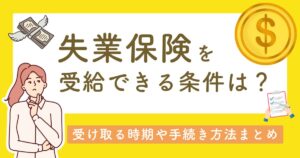
扶養に入るメリット・デメリット
| メリット | ・健康保険料や国民年金保険料(第3号被保険者となる場合)の自己負担がなくなる ・被保険者(配偶者など)の税負担が軽減される場合がある (所得税の配偶者控除・扶養控除とは別の、社会保険料控除) ・健康保険の給付(医療費の自己負担割合など)は被保険者本人と同等に受けられる |
|---|---|
| デメリット | ・失業保険の基本手当は原則として受け取れない ・将来の年金受給額が、自身で国民年金保険料を納付した場合と比べて少なくなる可能性がある ・パートなどで働く場合に、収入制限(年収の壁)を意識する必要が出てくる |
扶養に入る最大のメリットは、社会保険料の負担がなくなることです。
ただし、失業保険は受け取れなくなるため、どちらの経済的メリットが大きいかを比較検討する必要があります。
【パターン別】失業保険と扶養:どちらが得になりやすいか
失業保険と扶養、どちらが得かは一概にはいえませんが、判断の目安となるポイントがあります。
まず、失業保険の基本手当日額が扶養の収入基準(日額3,612円未満など)を大きく超える場合は、失業保険を受給した方が手取り収入は多くなる可能性が高いでしょう。
反対に、日額が基準に近いか下回る場合は、失業保険の受給総額と、扶養に入らなかった場合に自己負担する国民健康保険・国民年金保険料の総額を比較する必要があります。
たとえば、「受給総額 > 保険料負担額」なら失業保険受給が、「受給総額 < 保険料負担額」なら扶養に入る方が、短期的には経済的メリットが大きいと考えられます。
自身の受給額と保険料を試算し、自身はどちらに当てはまるか考えてみることが、納得のいく選択への第一歩です。
判断のヒント:再就職の意欲や家計状況も考慮しよう
経済的な比較だけでなく、自身の状況や考え方も判断材料になります。
たとえば、すぐにでも再就職したいと考えているか、少し休養期間を設けたいかによっても選択は変わってくるでしょう。
積極的に求職活動をするなら、失業保険を受けながら活動する方がメリットは大きいかもしれません。
また、世帯全体の収入や貯蓄状況も重要です。当面の生活費に余裕があるか、社会保険料の負担は家計にとってどれくらいのインパクトがあるか、などを考慮しましょう。
手続きの手間をどれだけ負担に感じるかも人それぞれです。
長期的な視点、たとえば将来の年金受給額への影響なども僅かながらありますが、まずは目の前の生活安定と自身の意向を優先して考えるのがよいでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
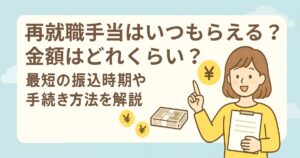
【手続き】失業保険と扶養の切り替えは正しいタイミングでおこなう
失業保険の受給や扶養への加入・脱退には、それぞれ決められた手続きが必要です。
とくに、扶養に入るタイミングと外れるタイミングを間違えると、あとで面倒なことになる可能性もあります。
ここでは、失業保険の申請から受給までの基本的な流れと、扶養に関する手続きをいつ、どのように行えばよいのかを解説します。
手続きを忘れた場合のリスクや、パート・アルバイトの方がとくに注意すべき点も確認し、スムーズな切り替えを目指しましょう。
失業保険の申請手続き:退職後の流れを確認
手続きの流れ
- 退職:会社から「離職票」など必要書類をもらう
- ハローワークへ:「求職の申込み」と「離職票」の提出
- 受給資格の決定:失業保険を受けられるかどうかが決まる
- 待機期間(7日間):この期間は給付されない
- 雇用保険説明会:受給に関する説明を受ける
- (自己都合退職等の場合)給付制限期間
- 失業の認定:ハローワークで求職活動状況などを報告し、認定を受ける
- 受給:認定後、指定口座に基本手当が振り込まれる
まず、退職時に会社から「雇用保険被保険者離職票(離職票-1、離職票-2)」を必ずもらいましょう。
その後、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申込みをおこない、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。
手続きには、離職票のほか、マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)、印鑑、写真、本人名義の預金通帳などが必要です。

扶養に入る・外れる手続き:いつ何をすべきか
扶養に関する手続きは、タイミングが非常に重要です。
まず【扶養から外れるタイミング】は、基本手当の日額が扶養の収入基準を超える場合、「失業保険の受給開始日」となります。
待機期間や給付制限期間中に一時的に扶養に入っていた場合は、給付が始まる前に扶養から外れる手続きが必要です。
反対に【扶養に入るタイミング】は、主に「退職後すぐ(失業保険の待機期間や給付制限期間中)」か、「失業保険の受給が終了した後」です。
手続きは、原則として被保険者(配偶者など)が自身の勤務先を通じておこないます。
必要書類は健康保険組合によって異なりますが、一般的に「健康保険被扶養者(異動)届」や、収入状況を確認するための書類(離職票のコピー、雇用保険受給資格者証のコピーなど)の提出が求められます。
このタイミングでこのように動けば大丈夫、と事前に流れを把握しておけば安心です。
要注意:扶養から外れる手続きを忘れた場合のリスク
もし、失業保険を受給しはじめたにもかかわらず、扶養から外れる手続きを忘れてしまった場合、さまざまなリスクが生じます。
最も注意すべきは、扶養に入っていた期間について、あとから遡って扶養資格が取り消される可能性があることです。
資格が取り消されると、その期間中に健康保険証を使って支払った医療費の保険給付分(通常7割)を返還するよう求められる場合があります。
さらに、本来加入すべきだった国民健康保険や国民年金の保険料も、遡って納付しなければならなくなる可能性もあるでしょう。
場合によっては遅延金などが加算されるケースも考えられます。
「知らなかった」では済まされないこともありますので、手続きは必ず期限内におこないましょう。
パート・アルバイトの方が退職した場合の注意点
パートやアルバイトとして働いていた方が退職する場合、まず自身が雇用保険の加入条件を満たしているかを確認しましょう。
加入条件は、所定労働時間が週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることです。
この条件を満たしていなければ、そもそも失業保険の受給資格がありません。
受給資格がある場合、次に重要なのが基本手当の日額です。
パート・アルバイトの方は比較的収入が低いケースも多く、日額が扶養の収入基準内(3,612円未満など)に収まる可能性も考えられます。
その場合は、失業保険を受給しながら扶養に入り続けることも可能です。
ただし、扶養内で働くことを希望して退職した場合などは、失業保険の受給自体が適切かどうかも含めて慎重に判断する必要があるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【トラブル回避】扶養に入ったまま失業保険を受け取ってしまったら?
「もしかしたら、扶養に入ったまま失業保険を受け取っていたかもしれない…」そう気づいたとき、大きな不安を感じる方もいるでしょう。
ルールを知らなかった、手続きをうっかり忘れていた、などの理由であっても、これは非常にデリケートな問題です。
ここでは、なぜこれが問題になるのか、いわゆる発覚する可能性はあるのか、そして万が一発覚した場合にどのようなペナルティがあるのかを解説します。
失業保険と扶養の同時受給が不正受給と見なされる理由
失業保険の基本手当の日額が扶養の収入基準を超えているにもかかわらず、扶養に入ったまま給付金を受け取ることは、本来受給資格がない状態で給付を受けていることになり、「不正受給」とみなされる可能性があります。
これは、意図的であったかどうかにかかわらず、結果としてルール違反の状態になっているためです。
近年は、マイナンバー制度の導入などにより、行政機関間での情報連携が進んでいます。
健康保険組合とハローワークの間で所得情報などが共有される可能性も考えられ、以前よりもこうした状況が発覚しやすくなっているといえるでしょう。
バレない?発覚する可能性と仕組み
「扶養に入ったまま失業保険をもらっても、黙っていれば発覚しないのでは?」と考えるのは非常に危険です。発覚する可能性は決して低くありません。
主な発覚経路としては、健康保険組合が定期的に行う被扶養者の収入状況調査(検認)や、医療機関を受診した際のデータ照会などが挙げられます。
また、マイナンバーを通じて所得情報が連携され、矛盾が判明するケースも考えられます。
さらに、稀なケースではありますが、第三者からの通報(密告)などによって発覚することもあるでしょう。
軽い気持ちでルール違反を続けることは、あとで大きな問題につながるリスクを常に抱えている状態といえます。
不正受給が発覚した場合の厳しいペナルティ
もし不正受給が発覚した場合、非常に厳しいペナルティが科される可能性があります。
まず、不正に受給した失業保険の全額について、返還を命じられます。
さらに、悪質性が高いと判断された場合には、返還額に加え、不正に受給した額の最大2倍に相当する金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命じられることもあるでしょう。
これらに加えて、延滞金が発生する場合もあります。最悪の場合、詐欺罪として刑事告発される可能性もゼロではありません。
軽い気持ちや手続きの怠りが、予想以上に深刻な事態を招く可能性があることを、十分に認識しておく必要があります。
気づいたら正直に申告!相談先と手続き
過去に扶養に入ったまま失業保険を受け取ってしまったかもしれない、と気づいた場合は、決して放置せず、できるだけ早く正直に申告・相談することが重要です。
まずは、自身が加入している(または加入していた)健康保険組合、あるいは配偶者などの被保険者の勤務先に状況を説明し、相談しましょう。
同時に、失業保険を受給したハローワークにも連絡し、事実関係を報告して指示を仰ぐ必要があります。
その後、指示に従って扶養資格の削除手続きや、必要であれば給付金の返還手続きなどを進めることになります。
早めに誠実な対応をとることで、ペナルティが軽減される可能性もあるでしょう。
不安な気持ちはよくわかりますが、問題を解決するためには、気づいた今が行動するときです。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【専門家監修】複雑な手続きや判断はプロに相談するのも有効な選択肢
退職後の手続きは失業保険や扶養だけでなく、税金なども絡み合い、非常に複雑です。
すべてを正確に理解し、自身にとってベストな選択をするのは、なかなか難しいと感じる方も少なくないでしょう。
もし手続きに不安を感じたり、自身で判断するのが難しいと感じたりした場合は、専門家への相談も有効な手段です。
ここでは、専門家に相談するメリットや、退職後の手続きをサポートしてくれるサービスについて紹介します。
専門家(社会保険労務士など)に相談するメリット
社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談することには、多くのメリットがあります。
まず、個別の状況、たとえば収入状況、家族構成、今後の働き方の希望などを詳しくヒアリングした上で、最も適した選択肢や手続きについて、的確なアドバイスをもらうことができます。
また、専門家は常に最新の法改正や制度の変更点を把握しているため、常に正確な情報に基づいて判断してもらえるでしょう。
さらに、複雑な書類作成や申請手続きの代行・サポートをお願いできる場合もあり、時間と手間を大幅に削減できます。
何より、専門家がサポートしてくれることで、「これで大丈夫」という大きな安心感を得られることが、一番のメリットかもしれません。
専門家の力を借りれば、もっとスムーズに、そして有利に手続きを進められる可能性が高まります。
「退職バンク」なら退職後の手続きをサポート
退職後の複雑な手続き、とくに失業保険や各種給付金の申請について、専門家のサポートを受けたいと考えている方におすすめなのが「退職バンク」です。
このサービスは、退職後の失業保険や社会保険給付金の申請手続きに特化したサポートを提供しています。
社会保険労務士をはじめとする専門家が、状況に合わせて、受け取れる可能性のある給付金の種類や金額、複雑な申請手続きを丁寧にサポートします。
オンラインでの相談に対応しているため、全国どこに在住でも利用可能です。
面倒でわかりにくい手続きはプロに任せることで、自身は安心して次のステップ、たとえば再就職活動や新しい生活の準備に集中できるでしょう。
これは、時間的にも精神的にも大きなメリットとなるはずです。
まずは無料診断から!LINEで受給額の目安を確認
「専門家に相談するのは少しハードルが高いかも…」と感じる方や、「そもそも自身がどれくらい給付金を受け取れるのか知りたい」という方は、まず「退職バンク」が提供している無料のLINE診断を試してみましょう。
簡単な質問に答えるだけで、受け取れる可能性のある失業保険の受給額の目安を、気軽に知ることができます。
もちろん、診断後の相談も無料でおこなっていますので、診断結果を見てから、さらに詳しい話を聞きたいと思った場合も安心です。
※実際に申請サポートサービスを利用する際には、別途所定の手数料が発生します
まずは第一歩として、この無料診断を活用し、自身の可能性を探ってみてください。
『無料で試せるなら、やってみようかな』、そのような軽い気持ちで大丈夫です。不安解消と次の行動へのきっかけになるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【Q&A】失業保険と扶養に関するよくある質問
ここでは、多くの方が疑問に思いがちな点について、Q&A形式で具体的にお答えします。
受給終了後の扶養加入タイミング、扶養に入らない場合の保険料、再就職までの保険の扱い、収入基準に含まれるものなど、細かいけれど知っておきたい情報をまとめました。
疑問を解消し、より安心して手続きに進めるようにしましょう。
失業保険の受給期間が終わったら、いつから扶養に入れる?
失業保険の基本手当の受給がすべて終了した場合、その翌日から扶養に入ることが可能です。
たとえば、最後の失業認定日に受け取る「雇用保険受給資格者証」に記載された支給終了年月日を確認し、その次の日から扶養の資格が発生すると考えられます。
手続きには、被保険者(配偶者など)の勤務先を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」などを提出する必要があります。
その際、失業保険の受給が終了したことを証明する書類として、「雇用保険受給資格者証」のコピーなどの提出を求められることが一般的です。
受給が終わったら、速やかに手続きを進めましょう。
扶養に入らない場合、国民健康保険・国民年金の保険料は?
失業保険を受給するなどの理由で扶養に入らない場合、原則として自身で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
国民健康保険料は、お住まいの市区町村や前年の所得によって金額が大きく変動します。正確な金額は、市区町村の窓口に問い合わせるのが確実です。
一方、国民年金保険料は、所得にかかわらず原則定額で、令和6年度(2024年度)は月額16,980円です。
ただし、失業などを理由とする保険料の減免制度(特例免除など)が利用できる場合もありますので、こちらも市区町村の年金窓口や年金事務所で相談してみましょう。
配偶者の扶養から外れた後、再就職までの保険はどうなる?
失業保険の受給開始などに伴い配偶者の扶養から外れた場合、次の就職先で社会保険に加入するまでの間は、公的な医療保険と年金制度に自身で加入する必要があります。
選択肢としては、主にお住まいの市区町村で「国民健康保険」と「国民年金」に加入する方法です。
もう一つの選択肢として、退職した会社の健康保険を「任意継続」する方法もあります。
任意継続は、退職後2年間、それまでの会社の健康保険に引き続き加入できる制度ですが、保険料は全額自己負担となります。
どちらがよいかは状況によりますので、保険料や保障内容を比較検討して決めましょう。
扶養の収入基準に交通費は含まれる?
健康保険の扶養認定における収入基準(年収130万円未満、失業保険の場合は日額3,612円未満など)を計算する際、交通費(通勤手当など)も原則として収入に含まれます。
これは、税法上は非課税となる通勤手当であっても、健康保険においては収入として扱われるのが一般的だからです。
給与明細などで交通費が別途支給されている場合、それも含めた総支給額で収入基準を満たすかどうかを判断する必要があります。
ただし、収入の範囲や計算方法の細かなルールは、加入している健康保険組合によって異なる場合もあるでしょう。
不明な点があれば、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ:失業保険と扶養の疑問を解消し専門家への相談も検討しよう
この記事では、失業保険と扶養の関係について、基本的なルールから手続き、注意点まで詳しく解説しました。
重要なポイントは以下の通りです。
- 失業保険受給中は原則扶養に入れない(収入基準あり)
- 失業保険と扶養どちらが得かは受給額と保険料負担を比較して判断
- 扶養手続きは正しいタイミングで行い手続き忘れのリスクを避ける
- 扶養に入ったまま受給した場合速やかに申告・相談が必要
これらの知識を基に、自身の状況に合わせて最適な選択をし、必要な手続きを計画的に進めてください。
もし、手続きに不安がある、判断に迷うといった場合は、一人で抱え込まず、「退職バンク」のような専門家への相談も有効な手段です。
正しい知識と適切な対応で、退職後の不安を解消し、安心して次のステップへ進みましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /