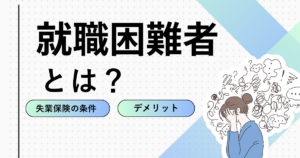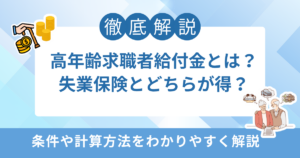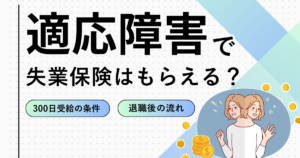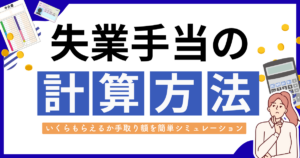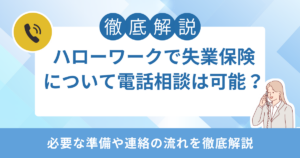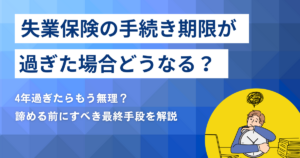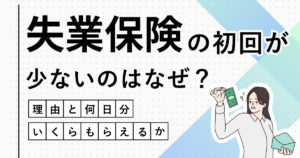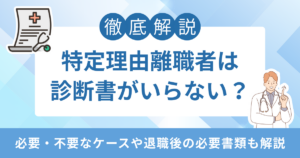【失業保険】早期退職でもらえる金額は?会社都合と自己都合の差を解説
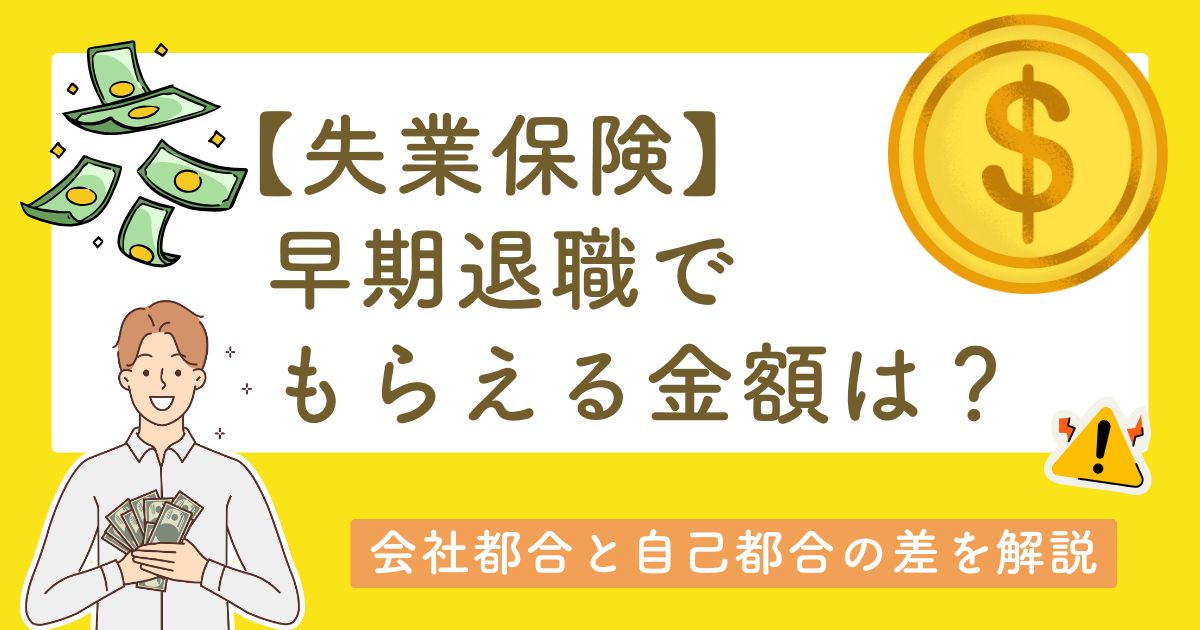
早期退職を検討する際、退職後の生活費への不安はつきものです。
その大きな支えとなる失業保険ですが、退職理由が「会社都合」か「自己都合」かで、もらえる金額や期間が大きく変わることをご存じでしょうか。
「自身のケースはどちらになるのか」「損をしないためにはどうすればよいのか」と悩む方も多いでしょう。
結論として、失業保険は会社都合で退職する方が圧倒的に有利な条件で受給できます。
本記事では、会社都合と自己都合の具体的な違い、自身がどちらに該当するかの判断ポイント、そして手続きの流れまでを詳しく解説します。
本記事を参考に、安心して次のステップへ進むための準備を始めましょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【結論】早期退職の失業保険は退職理由で決まる|会社都合が断然有利

早期退職を考えたとき、多くの方が不安に感じるのが退職後の生活費ではないでしょうか。
結論からいうと、失業保険は「会社都合」で退職した方が「自己都合」よりも圧倒的に有利な条件で受給できます。
自身の状況がどちらに該当するのかを正しく理解し、損のない選択をすることが、安心して次のステップへ進むための第一歩となります。
これから、その具体的な違いや自身がどちらに当てはまるのかの判断ポイント、そして2025年4月から変わった新しいルールについて、詳しく解説します。
会社都合と自己都合の大きな違い
失業保険における「会社都合退職」と「自己都合退職」の最大の違いは、退職後の生活を支える給付内容にあります。
具体的には、失業保険をもらい始めるまでの期間、もらえる日数の上限、そして総額に大きな差が生まれます。
なぜこのような違いがあるかというと、会社都合退職は、倒産や解雇など、労働者が予測しなかった形で職を失うケースを想定しているためです。
そのため、より手厚い保護を受けられる仕組みです。
自身の退職がどちらに該当するのかを正しく知ることは、退職後の生活設計を立てる上で非常に重要です。
損をして後悔しないためにも、まずはこの基本的な違いを十分に理解しておきましょう。
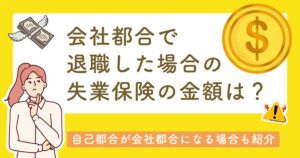
早期退職がどちらに該当するかの判断が重要
「早期退職優遇制度」を利用した場合、その扱いが会社都合になるか、自己都合になるかは非常に重要なポイントです。
一般的に、自らの意思で応募する「希望退職」は自己都合と見なされがちですが、必ずしもそうとは限りません。
たとえば、実質的には人員整理の一環であったり、上司から退職を促される「退職勧奨」があったりした場合は、会社都合として認められる可能性があります。
最終的な判断はハローワークがおこないますが、その際に最も重視されるのが、会社から発行される「離職票」に記載された離職理由です。
そのため、退職時にはこの離職票の内容を十分に確認することが、自身の権利を守る上で極めて重要になります。
会社都合退職の大きなメリット
会社都合で退職する最大のメリットは、経済的な不安を早期に解消できる点にあります。
まず、自己都合退職の場合に課される給付制限期間がありません。そのため、7日間の待機期間が終われば、すぐに失業保険の受給を開始できます。
さらに、受け取れる期間、すなわち所定給付日数が自己都合退職の場合よりも長く設定されています。
これは、受け取れる総額が多くなることを意味し、安心して再就職活動に専念できる期間が長くなることにつなげることが可能です。
また、見落としがちですが、会社都合で離職した方は、国民健康保険料が大幅に軽減される制度の対象となる場合があります。
これも退職後の生活を支える大きな金銭的メリットといえるでしょう。
自己都合でも2025年4月から給付制限が緩和
法改正により、2025年4月1日から自己都合で退職した場合の給付制限期間が、これまでの原則2か月から1か月に短縮されます。
これにより、自己都合で会社を辞めた方も、より早く失業保険をもらえるようになり、退職後の経済的な負担が少し緩和されるでしょう。
ただし、注意点もあります。
自身の責任による重大な理由で解雇された場合や、5年間で3回以上自己都合による離職を繰り返している場合は、給付制限期間が3か月となるため、この緩和措置の対象外です。
この改正は自己都合で退職する方にとって朗報ですが、給付日数や保険料の軽減措置などを考慮すると、依然として会社都合退職の方が有利であることに変わりはありません。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
失業保険の受給額と期間はこう変わる|会社都合と自己都合の徹底比較

退職理由によって失業保険の条件がどう変わるのか、ここでは「もらえる金額」「もらえる期間」「もらえる時期」そして「保険料」という4つの具体的なポイントに絞って、会社都合と自己都合の違いを詳しく比較していきます。
自身の状況を当てはめてみることで、退職後の生活設計がより明確になるはずです。
それぞれの項目でどれだけの差が生まれるのか、一つひとつ確認していきましょう。
1. 受給額の計算方法|基本手当日額の仕組み
失業保険で1日あたりにもらえる金額を「基本手当日額」と呼びます。
この金額は、退職する直前6か月間の給与総額を180で割って算出した「賃金日額」を基に計算されます。
具体的には、その賃金日額に45%から80%の給付率を掛けるかたちです。
この給付率は、賃金日額が低いほど給付率は80%に近くなり、反対に賃金日額が高いほど45%に近づく仕組みです。
ただし、基本手当日額には年齢ごとに上限額が定められており、それを超えることはありません。
まずは、自身の給与から賃金日額を計算し、おおよその受給額を把握することからはじめましょう。
2. 【期間】会社都合は自己都合より最大240日長い
失業保険をもらえる日数を「所定給付日数」といいます。
この日数は、退職理由、年齢、そして雇用保険の被保険者であった期間によって決まりますが、会社都合と自己都合では大きな差が生まれます。
退職理由別 所定給付日数の比較例
| 年齢 | 被保険者期間 | 自己都合 | 会社都合 |
|---|---|---|---|
| 45歳〜59歳 | 20年以上 | 150日 | 330日 |
| 35歳〜44歳 | 10年〜19年 | 120日 | 240日 |
たとえば、45歳以上60歳未満の方が20年以上勤務していた場合、自己都合では150日ですが、会社都合であれば330日と、その差は180日にもなります。
これは、約半年分も受給期間が長くなる計算です。
このように、退職理由が所定給付日数に与える影響は非常に大きいといえるでしょう。
3. 【時期】会社都合なら給付制限なしで受給開始
失業保険の申請後、実際に給付金が振り込まれるまでのスピードも、会社都合と自己都合では大きく異なります。
まず、申請後の7日間は「待機期間」とされ、この期間はどちらの理由であっても給付はおこなわれません。
問題となるのはその後の期間です。会社都合退職の場合は、この待機期間が終わればすぐに受給が始まります。
一方、自己都合退職の場合は、待機期間に加えて原則1か月の「給付制限期間」が設けられています。
この差は、退職後の生活の安心感に直結する重要なポイントといえるでしょう。
4. 【保険料】会社都合なら国民健康保険料の軽減措置も
退職後、多くの方は国民健康保険に加入することになりますが、この保険料は前年の所得を基に計算されるため、高額になるケースが少なくありません。
しかし、ここにも会社都合退職のメリットがあります。
倒産や解雇といった会社都合によって離職した方は、「非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減措置」という制度の対象となります。
この制度が適用されると、保険料の計算に使用される前年の給与所得を、本来の金額の30/100として計算してもらえます。
これにより、年間の保険料負担を大幅に抑えることが可能です。
失業保険の給付だけでなく、このような支出面でのメリットも、会社都合退職の大きな利点です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【要注意】あなたの早期退職はどちら?会社都合になるかの判断ポイント

「自身のケースは会社都合になるのだろうか?」これは、早期退職を考える上で誰もが抱く疑問です。
ここでは、早期退職優遇制度がどのように扱われるのか、そしてどのようなケースが会社都合と判断されやすいのか、具体的なポイントを解説します。
自身の状況と照らし合わせながら、会社都合として認められる可能性を探っていきましょう。
原則は自己都合|早期退職優遇制度の基本的な扱い
会社の「早期退職優遇制度」は、従業員が自らの意思で退職を希望し、応募するという形式をとることが一般的です。
そのため、原則としては「自己都合退職」として扱われるケースが多くなります。
しかし、これはあくまでも原則論です。
その制度が設けられた背景、たとえば業績不振による人員整理が目的である場合や、応募しなければ不利益な扱いを受けるような状況があった場合など、個別の事情によっては会社都合と判断される可能性も十分にあります。
そのため、「希望退職だから自己都合だ」と安易に諦めてしまう必要はありません。
自身の置かれた状況を客観的に見極めることが大切です。
会社都合と判断されやすい3つのケース
判断されやすいケース
- ケース1:退職勧奨があった場合
- ケース2:事業所の縮小・廃止など事業内容に大きな変化があった場合
- ケース3:ハラスメントなど会社側に原因がある場合
早期退職であっても、会社都合と判断されやすいケースにはいくつかのパターンがあります。
一つ目は、上司との面談などで明確に退職を勧められる「退職勧奨」があった場合です。
応募しなければ不利益な配置転換を示唆されるなど、事実上、退職せざるを得ない状況もこれに含まれる可能性があります。
二つ目は、会社の事業所が大幅に縮小されたり、移転・廃止されたりするなど、人員整理の一環として募集がおこなわれていることが明らかな場合です。
三つ目として、上司からのハラスメントが原因で退職に至ったケースなども該当しますが、こちらは証明が難しい側面もあります。
いずれにせよ、形式上は希望退職でも、実態として会社側の都合が強く影響しているかどうかが判断の分かれ目となります。
【最重要】離職票の離職理由を必ず確認する
ハローワークが自身の退職理由を「会社都合」か「自己都合」か判断する上で、最も重要な証拠となるのが、退職時に会社から交付される「離職票」です。
この書類に記載されている離職理由が、最終的な判断に大きな影響を与えます。
そのため、離職票を受け取ったら、必ず「離職理由」の欄に書かれている内容を確認してください。
もし、自身の認識と会社側の記載内容に食い違いがある場合は、安易に署名・捺印をしてはいけません。
内容に納得がいかない場合は、離職票の「具体的事情記載欄(本人用)」に異議がある旨を記入し、ハローワークの窓口で相談することが可能です。
この一手間が、自身の権利を守るために非常に重要になります。
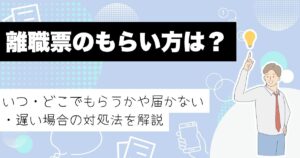
失業保険をもらうための具体的な手続きと流れを4ステップで解説

失業保険の制度を理解したら、次はいよいよ具体的な手続きです。
その前に、そもそも失業保険を受給できるかどうかの大前提となる基本条件を確認しておきましょう。
失業保険を受け取るためには、以下の基本条件を満たしている必要があります。
- 原則として、退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が通算して12ヶ月以上あること。
- ただし、倒産・解雇といった会社都合で退職した場合(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、この条件が緩和されます。具体的には、退職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
ご自身の被保険者期間が分からない場合は、ハローワークで確認することができます。
全体の流れを把握しておくことで、書類の準備やハローワークでの手続きをスムーズにおこなうことができますので、十分に確認しておきましょう。
ステップ1:退職前に準備・確認すること
失業保険の申請をスムーズにおこなうためには、退職前の準備が大切です。
まず、退職時に会社から受け取る必要のある書類を確認しましょう。
必要書類
- 離職票(会社から受け取る)
- 雇用保険被保険者証(会社から受け取る)
- マイナンバーカードまたは運転免許証などの本人確認書類
- 証明写真(2枚)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(給付金の振込先)
とくに重要なのは「離職票」と「雇用保険被保険者証」の2つです。これらは申請に必須の書類となります。
離職票は、通常、退職日から10日前後で会社から交付されます。
もし、なかなか届かない場合は、会社の人事や総務部門に問い合わせて、発行を依頼するようにしてください。
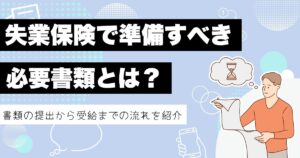
ステップ2:退職後にハローワークで求職申し込み
退職して必要な書類が揃ったら、自身の住所を管轄するハローワークへ行き、手続きを開始します。
窓口で「仕事を探しに来ました」と伝え、「求職の申し込み」をおこなうことからはじまります。
その後、失業保険の受給手続きの窓口に案内されますので、持参した書類を提出してください。
ここで書類の内容が確認され、問題がなければ失業保険の「受給資格が決定」されます。
この際、職員から離職した理由について質問されます。
自身の状況を正確に伝えることが、適切な受給資格の判断につなげることが可能なため、事実をありのままに話すことが重要です。
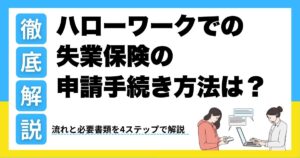
ステップ3:雇用保険説明会と待機期間
受給資格が決定すると、後日開催される「雇用保険説明会」への参加が指示されます。
この説明会は、失業保険の制度や今後の手続きについて理解を深めるためのもので、参加が義務付けられています。
説明会では、「雇用保険受給資格者証」と、失業の状態を申告するための「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
また、失業保険の申請手続きをおこなった日から通算して7日間は「待機期間」と呼ばれ、この期間は会社都合・自己都合にかかわらず、すべての方が失業保険を受け取ることができません。
この期間が満了してはじめて、給付の対象期間がスタートします。
ステップ4:失業認定と受給開始
失業保険を受給するためには、原則として4週間に1度、指定された「失業認定日」にハローワークへ行く必要があります。
そして、「失業認定申告書」を提出し、失業状態にあることの認定を受けなければなりません。
この「失業の認定」を受けるためには、前回の認定日から今回までの間に、原則として2回以上の求職活動をおこなった実績が必要です。
求職活動とは、求人への応募やハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などを指します。
無事に失業の認定を受けると、通常5営業日ほどで、指定した自身の銀行口座に失業保険が振り込まれます。
この流れを、所定給付日数が終了するまで繰り返すことになります。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【専門家がサポート】失業保険の申請で損をしないための退職バンク活用術
ここまで失業保険の制度について解説してきましたが、「手続きが複雑そう」「会社との交渉は気が重い」と感じた方もいるのではないでしょうか。
そのようなときに頼りになるのが、専門家によるサポートです。
ここでは、退職後の経済的な不安を解消し、損をしないための選択肢として、退職給付金申請サポートサービス「退職バンク」を紹介します。
退職給付金申請サポート「退職バンク」とは
「退職バンク」は、複雑で分かりにくい失業保険の申請手続きを、社会保険労務士などの専門家が徹底的にサポートするサービスです。
公的な窓口であるハローワークでは教えてくれないような、一人ひとりの状況に合わせた最適な申請方法を提案するのが大きな特徴です。
実際に「退職バンク」のサポートを利用することで、受給開始までの期間を最短1か月に短縮したり、受給額を最大200万円まで増やしたりした実績が数多くあります。
「本来もらえるはずだった給付金をもらい損ねる」といった事態を防ぎ、自身の権利を最大限に活用するためのお手伝いをします。
複雑な制度や会社との交渉も専門家がいるから安心
早期退職において最も頭を悩ませるのが、「離職理由をどう判断されるか」という点ではないでしょうか。
「退職バンク」では、社会保険労務士などの専門家が自身の状況を詳しくヒアリングし、会社都合として認められる可能性があるかなどを的確にアドバイスします。
知識が不足していることで、会社側の言い分を鵜呑みにしてしまい、不利な条件で退職してしまうリスクを回避できます。
専門家が後ろ盾となることで、会社とのやり取りに対する心理的な負担も大きく軽減されるでしょう。
「ややこしい国の申請方法もアドバイザーのサポートでサクッと解決」できる手軽さと、専門家ならではの安心感が、「退職バンク」の強みです。
オンラインで全国対応!まずはLINEで無料相談から
「退職バンク」のサポートは、オンライン面談とチャットツールを活用しておこなわれるため、住まいの地域にかかわらず、全国どこからでも利用することが可能です。
サービス利用までの流れは、まず無料相談からはじまります。
その後、WEBでの個別面談を経て、サポート内容に納得いただけたら契約へと進みます。
「自身が一体いくらもらえるのか気になる」という方は、まずはLINEから申し込める無料の受給額診断を試してみてはどうでしょうか。
専門家への相談が、自身の不安を解消する第一歩となるはずです。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
早期退職と失業保険に関するよくある質問(Q&A)
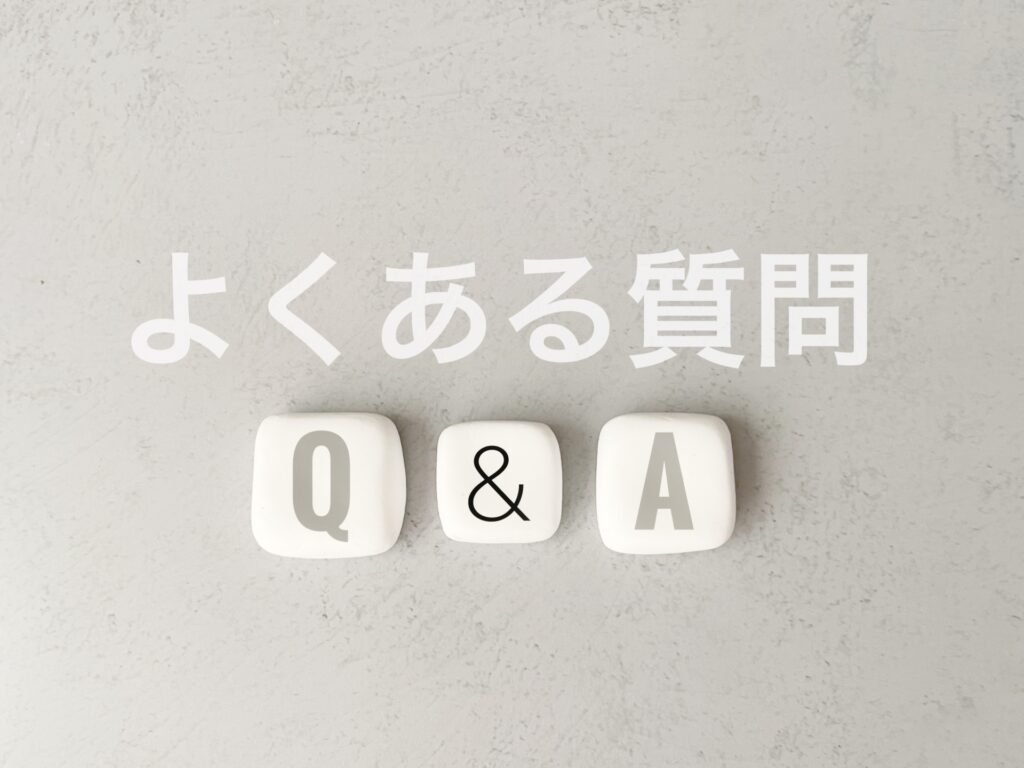
ここでは、早期退職と失業保険について、多くの方が抱く疑問に回答していきます。
退職金との関係や、受給中のアルバイト、再就職が決まった場合の手当など、知っておくと役立つ情報ばかりです。
2025年4月から施行される法改正の内容についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
より有利に受給するために退職のタイミングは関係ありますか?
退職のタイミングが、失業保険の受給額に影響する可能性はあります。
なぜなら、1日あたりの受給額である「基本手当日額」は、退職前6か月間の給与総額を基に計算されるためです。
たとえば、会社の規定で賞与(ボーナス)がこの給与総額に含まれる場合、賞与が支給された直後の月に退職すると、計算の基礎となる賃金日額が高くなります。
その結果、基本手当日額も上がり、受給できる総額が増えるケースが考えられます。
ただし、賞与の扱いは会社の就業規則によって異なりますので、事前に確認しておくことが大切です。
失業保険の受給中に注意すべきことはありますか?
失業保険の受給中は、いくつかの点に注意が必要です。
最も重要なのは、次の仕事を見つけるための「求職活動」を継続的におこなう義務があることです。
原則として、4週間に1度の失業認定日までに2回以上の活動実績がなければ、失業保険は支給されません。
また、失業期間は経歴上の空白期間、いわゆるブランクとなります。
再就職の面接でこの期間について質問される可能性も念頭に置き、どう過ごしていたかを説明できるよう準備しておくとよいでしょう。
そして、アルバイト収入などを得た場合は、必ず正直に申告することが大切です。
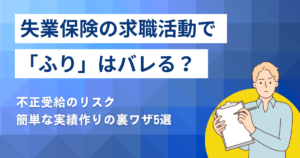
退職金をもらうと、失業保険は減らされる?
結論からいうと、退職金を受け取ったこと自体を理由に、失業保険の給付額が減額されることはありません。
退職金はこれまでの労働に対する対価であり、失業保険は次の仕事を見つけるまでの生活を支えるための給付金なので、それぞれ別の制度として扱われます。
ただし、自己都合で退職した場合、ハローワークでの求職申し込みより前に退職金の支給が決定していると、失業保険の給付開始時期が遅れるケースがあります。
具体的には、待機期間満了後、給付制限期間がさらに最大で1か月延長される可能性がありますので、注意が必要です。
失業保険の受給中にアルバイトはできますか?
失業保険の受給中に、一時的にアルバイトやパートタイマーとして働くことは可能です。
ただし、いくつかのルールを守る必要があります。
最も重要なのは、1週間の労働時間が20時間未満であることです。
これを超えてしまうと「就職した」と見なされ、失業保険の給付が停止されます。
また、申請後の7日間の待機期間中は、原則として働くことはできません。
アルバイトなどで収入を得た場合は、必ず失業認定申告書に正直に申告してください。
申告を怠ると不正受給と見なされ、厳しいペナルティが課されるため、十分に注意しましょう。

再就職が決まったらもらえる手当はありますか?
失業保険の受給資格がある方が、給付日数を一定以上残して安定した職業に再就職した場合、「再就職手当」というお祝い金のような一時金を受け取ることができます。
この手当は、早く再就職できたことへのインセンティブとなる制度です。
もらえる金額は、失業保険の支給残日数によって決まります。
具体的には、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合は「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上を残した場合は「基本手当日額×支給残日数×60%」が支給されます。
早期の再就職は、生活の安定だけでなく、このような金銭的なメリットにもつなげることが可能です。
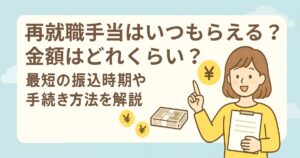
2025年4月から失業保険はどう変わるの?
2025年4月1日から、雇用保険制度がいくつか改正されます。
本記事でも触れましたが、最も大きな変更点の一つが、自己都合で退職した方の給付制限期間が、原則2か月から1か月に短縮されることです。
また、離職期間中に自ら専門的な教育訓練をおこなった場合には、この給付制限が解除されるという要件緩和もおこなわれます。
これは、労働者の主体的な学び直しやスキルアップを後押しするものです。
このほか、子育て世代を支援するため、「出生後休業支援給付」や「育児時短就業給付」といった新しい給付金も創設されます。
これらの改正は、働き方が多様化する現代社会に対応するためのものといえるでしょう。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ:早期退職の不安は正しい知識と準備で解消できる

本記事では、早期退職における失業保険の重要なポイントについて解説しました。
失業保険で損をしないための最重要ポイントは「退職理由」であり、会社都合が自己都合よりも給付期間や開始時期で有利になることをご理解いただけたかと思います。
自身の状況がどちらに該当する可能性があるのか、そして、もらえる金額や期間の見通しを立てることが、経済的な不安を解消し、安心して次のキャリアステージへと進むための鍵となります。
複雑な手続きや会社との交渉に少しでも不安を感じるなら、一人で抱え込まず専門家の力を借りるのが賢明です。
退職後の大切な生活資金を十分に確保するために、まずは「退職バンク」の無料診断で自身の可能性を確認してみてください。
参考記事)
再就職手当もらってすぐ退職しても失業保険はもらえる!ネットにない豆知識|退職の手続き
\ 申請サポートの無料相談はこちら /