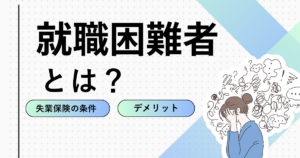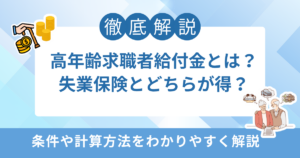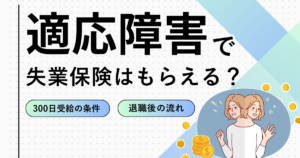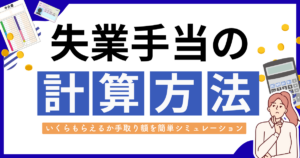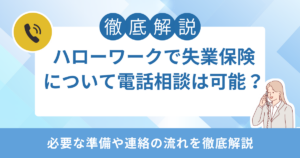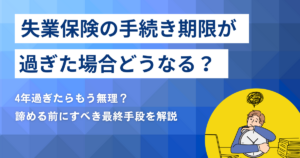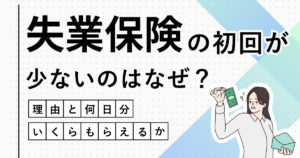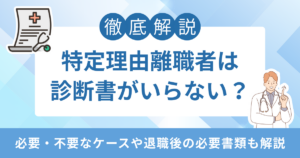失業保険の確定申告は必要?不要・得するケースや書き方の注意点を解説
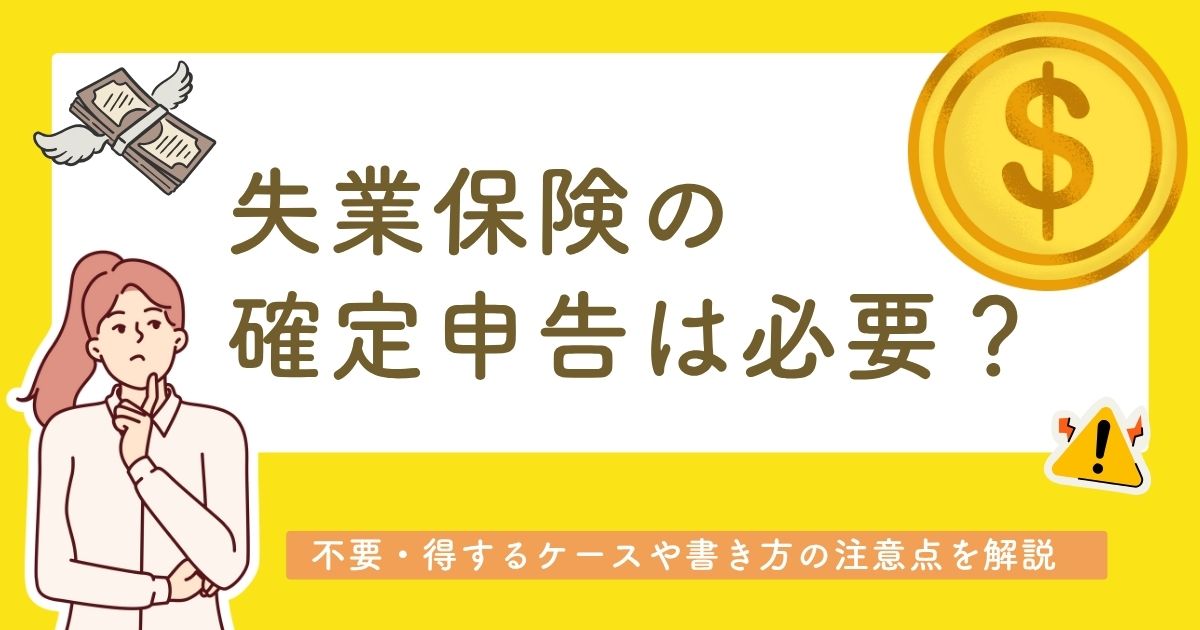
退職して失業保険を受け取ることになり、確定申告は必要なのだろうかと不安に感じている方も多いでしょう。
会社員時代は年末調整で済んでいたため、初めての手続きに戸惑うのは当然です。
結論からいうと、失業保険は非課税のため確定申告は原則不要ですが、申告すれば払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
この記事では、失業保険と確定申告の関係について、申告が「不要なケース」「した方が得なケース」「必要なケース」の3パターンに分けて詳しく解説します。
本記事を読み進めれば、自身の状況にあわせて何をすべきかが明確になり、損やペナルティを回避するための知識が得られます。
ぜひ参考にして、退職後の手続きへの不安を解消してください。
【結論】失業保険の確定申告は原則不要!ただし申告で税金が戻るケースも

失業保険をもらったら確定申告は必要なのだろうかと悩んでいる方も多いでしょう。
結論からいうと、失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税所得のため、原則として確定申告は不要です。
しかし、状況によっては確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
大切なのは、自身が「不要な方」「した方が得な方」「必要な方」のどのパターンにあてはまるかを知ることです。
これから、それぞれのケースについて詳しく解説します。
失業保険は非課税所得なので申告義務はない
失業保険は、雇用保険法という法律に基づき、課税の対象外と定められています。
これは、失業中の生活を支えるための大切な給付金であり、所得税や住民税がかからない仕組みです。
そのため、失業保険の収入のみを理由として確定申告をおこなう義務は一切ありません。
よく年収の計算で混同されがちですが、この失業保険の給付は税法上の所得には含まれないと覚えておくとよいでしょう。
確定申告書にも、失業保険で受け取った金額を記入する必要はないのです。
この基本ルールをまず理解しておくと、今後の手続きに対する不安が少し和らぐでしょう。
確定申告で払いすぎた税金が戻る可能性がある
確定申告は義務ではないものの、申告することで払いすぎた税金が戻ってくる「還付」を受けられる可能性があります。
とくに、年の途中で退職した方は、会社で年末調整がおこなわれないため、税金を納めすぎているケースが少なくありません。
会社員は毎月の給与から所得税が天引き、つまり源泉徴収されていますが、これは年間の所得を仮定した金額です。
年の途中で退職すると、本来の年収より高い税率で計算されたままになっていることがあります。
そこで確定申告をすれば、正しい税額で再計算され、差額が戻ってくるのです。これは義務ではなく、権利としておこなえる手続きになります。
【補足】年末調整と確定申告の違い
ここで、多くの方が混同しがちな「年末調整」と「確定申告」の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 誰がやるか | 会社(勤務先) | 自分自身 |
| 対象者 | 主に会社員(給与所得者) | 全ての所得者(個人事業主、退職者など) |
| 時期 | 年末(11月~12月頃) | 翌年の2月16日~3月15日 |
| 目的 | 給与に対する所得税の過不足を精算する | 1年間の全ての所得と控除を計算し納税額を確定・申告する |
このように、年末調整は会社が代行しておこなう簡易的な手続きです。
年の途中で退職するとこの手続きがおこなわれないため、自身で確定申告をする必要がある、と理解するとわかりやすいです。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
退職後に確定申告すべき?3つのパターンを解説

自身の状況が「確定申告が不要な方」「した方が得な方」「必要な方」のどれにあてはまるのか、迷う方もいるでしょう。ここでは、それぞれの具体的な条件を解説します。
フローチャートを参考に、自身がどのパターンに該当するのかを確認することで、とるべき対応が明確になります。
自身の状況と照らしあわせながら読み進めてみてください。
パターン1:確定申告が不要な方
確定申告が基本的に不要となるのは、退職後の状況が特定の条件にあてはまる場合です。
たとえば、年の途中で退職したものの、その年内に再就職はせず、失業保険以外の収入が全くなかった方が該当します。
より具体的には、アルバイトなど他の所得が、すべての人が受けられる基礎控除額の48万円以下であれば、申告の義務はありません。
また、退職金を受け取った際に会社で年末調整が完了しており、他に申告すべき所得がない場合も同様です。
このパターンにあてはまる方は、税務手続きに関してとくに何かをする必要はなく、その点は安心できるでしょう。
パターン2:確定申告をすると得する可能性が高い方
確定申告をすると得をする可能性が高いのは、主に年の途中で退職し、年末調整を受けずにその年を終えた方です。
この場合、給与から天引きされていた源泉徴収税額が、本来納めるべき年間の税額より多くなっていることが大半です。
還付の可能性が高いかどうかは、退職した会社から受け取る「源泉徴収票」で確認できます。
「源泉徴収税額」の欄に金額の記載があれば、その一部または全額が戻ってくる可能性があります。
また、年間に支払った医療費が高額だった場合の医療費控除など、年末調整では申告できない控除を利用したい方も、還付申告をすることでメリットを受けられるでしょう。
パターン3:確定申告が必要な方
確定申告が義務となるケースも存在します。
最も多いのが、失業保険を受け取りながら、アルバイトや副業によって年間で20万円を超える所得を得た場合です。
この「20万円」という金額は、給与所得者向けのルールであり、超えると申告の義務が発生します。
その他にも、個人事業主として事業所得があった方や、2か所以上の会社から給与を受け取っていて年末調整がされなかった方も対象となります。
申告義務があるにもかかわらず、手続きを怠ると、あとから無申告加算税などのペナルティが課される可能性があるでしょう。
自身がこのパターンに該当するかどうか、収入状況を十分に確認することが重要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
確定申告の書き方と提出までのステップを分かりやすく解説

確定申告が必要、または還付を受けたいと判断した場合、次に気になるのは具体的な手続きでしょう。
初めての方でもスムーズに進められるよう、準備から提出までの流れを3つのステップに分けて解説します。
最近では、国税庁のWebサイトを利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンから簡単に申告書を作成できます。
一つひとつのステップを確認しながら、着実に進めていきましょう。
ステップ1:必要な書類を準備する
準備する主な書類
- 源泉徴収票
- 各種控除証明書(生命保険料、地震保険料など)
- マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)
- 還付金振込先の口座情報がわかるもの
確定申告をはじめる前に、まずは必要な書類を手元に揃えましょう。
最も重要なのが、退職した会社から発行される「源泉徴収票」です。ここには、支払われた給与額や所得税額が記載されています。
もし手元にない、または紛失してしまった場合は、速やかに元の勤務先に連絡し、再発行を依頼してください。
その他、生命保険料控除などを受けたい場合は、保険会社から送られてくる控除証明書も必要になります。
ステップ2:確定申告書を作成する【源泉徴収票の転記がポイント】
確定申告書の作成は、国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利でおすすめです。
画面の指示に従って入力していくだけで、自動的に税額が計算され、申告書が完成します。
ここでつまずかないための最も重要なポイントは、手元にある「源泉徴収票」の数字を、申告書の対応する項目に正しく転記することです。
| 源泉徴収票の項目 | 申告書で入力する欄 | 備考 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 収入金額等(給与) | |
| 給与所得控除後の金額 | 所得金額等(給与) | |
| 所得控除の額の合計額 | ― | 個別項目(社会保険料等)を入力する |
| 社会保険料等の金額 | 社会保険料控除 | |
| 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
これらの項目を画面の案内に沿って入力すれば、納めすぎた税金が自動で計算され、還付金額が算出されます。
とくに「源泉徴収税額」の入力漏れは還付を受けられない原因になるため、忘れずに入力しましょう。
なお、繰り返しになりますが、失業保険の受給額は非課税のため、収入として記入する必要は一切ありません。
ステップ3:確定申告書を税務署へ提出する
完成した確定申告書は、税務署へ提出します。提出方法には主に3つの選択肢があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| e-Tax (電子申告) | ・マイナンバーカードと対応スマホがあればオンラインで完結 ・手軽で便利 |
| 税務署へ持参 | 管轄の税務署の窓口に直接提出 |
| 郵送 | 申告書と添付書類を印刷し税務署に郵送 |
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。
ただし、税金が戻ってくる還付申告の場合は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
早めに手続きを済ませたい方は、1月中に提出することも可能です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
確定申告しないとバレる?知っておくべきペナルティと注意点

もし申告義務があるのに手続きをしなかったらどうなるのだろうか、という不安を抱く方もいるでしょう。
ここでは、無申告のリスクや、失業保険の受給に関する別の注意点について解説します。
ルールを知らなかったでは済まされないケースもありますので、ペナルティの内容を正しく理解し、適切な対応を心がけることが大切です。
申告義務があるのに放置するとペナルティの対象になる
少しの所得だからバレることはないだろうと安易に考えるのは危険です。
税務署は、企業から提出される「支払調書」という書類を通じて、誰にいくら支払ったかを把握しています。
そのため、申告すべき所得があるのに無申告でいると、発覚する可能性は高いといえるでしょう。
もし申告漏れが発覚した場合、本来納めるべきだった税金に加えて、「無申告加算税」や、納付が遅れた日数分の「延滞税」といったペナルティが課せられます。
これらは金銭的な負担を大きくするだけでなく、精神的なストレスにもなります。申告義務がある場合は、必ず期限内に手続きを済ませることが重要です。
失業保険の不正受給にも注意が必要
確定申告の義務とは別に、失業保険の受給中にアルバイトなどで収入を得た場合は、ハローワークへ正直に申告する義務があります。
これは、失業状態にあるかを確認するための重要なルールです。
この申告を怠ってしまうと、不正受給とみなされる可能性があります。
不正受給のペナルティは非常に厳しく、支給が停止されるだけでなく、受け取った金額の2倍に相当する額、合計で3倍の額を返還しなければならないケースもあります。
税務署への確定申告と、ハローワークへの収入申告は全く別の手続きです。両方のルールを正しく理解し、誠実に対応することが求められます。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
退職後の手続きが不安なら「退職バンク」の無料相談がおすすめ
ここまで失業保険と確定申告について解説してきましたが、やはり手続きが複雑で不安、そもそも失業中の生活費が心配と感じている方も多いでしょう。
そのような退職後のさまざまな不安を、専門家の視点からトータルでサポートするのが「退職バンク」です。
複雑な手続きは専門家に任せ、自身は安心して次のステップへの準備に専念できます。
退職バンクは退職者の経済的・精神的な不安を解消するサービス
「退職バンク」は、社会保険労務士などの専門家が、複雑でわかりにくい失業保険の申請を徹底的にサポートし、受けられる給付を最大化することを目指すサービスです。
退職は、経済的な不安だけでなく、孤独感や将来への焦りといった精神的な負担も伴います。
退職バンクは、そうした退職者一人ひとりの状況に寄り添い、経済的な基盤を安定させることで、心に余裕を持って新しいスタートを切るためのお手伝いをします。
ハローワークでは教えてくれないような専門的なノウハウを活用できるのが、大きな特徴です。
通常より早く多く失業保険がもらえる可能性がある
退職バンクを利用する最大のメリットは、失業保険を通常より早く、そして多く受け取れる可能性がある点です。
通常、自己都合で退職した場合、失業保険の受給開始までには約1か月から3か月の給付制限期間があります。
しかし、退職バンクのサポートを活用することで、この期間をなくし「最短1か月」で受給をはじめることができるケースがあるでしょう。
さらに、専門家のノウハウによって、受給額も一般的なケースに比べて大幅に増額できる可能性があります。
経済的な空白期間を最小限に抑え、十分な生活資金を確保できることは、焦らずに自身にあった再就職先を探すうえで、非常に大きな安心材料となるでしょう。
LINEの無料診断で受給額を確認する
サービスに興味はあるけれど、本当に自身も対象になるのかわからないという方のために、退職バンクではLINEを使った「無料診断」を用意しています。
いくつかの簡単な質問に答えるだけで、自身がいくら失業保険をもらえる可能性があるのか、手軽にシミュレーションすることが可能です。
相談料は無料で、サービスを利用するまでは一切費用はかかりません。
また、相談はオンラインで完結するため、全国どこにお住まいの方でも利用できます。
まずはこの無料診断で自身の可能性を確認し、安心できる退職後の生活に向けた第一歩を踏み出してみてください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
【Q&A】失業保険と確定申告に関するよくある質問

最後に、失業保険と確定申告について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。自身の状況と照らしあわせながら、最終確認の参考にしてください。
源泉徴収票がもらえない場合はどうすればよいか?
まずは、退職した元の勤務先に連絡し、源泉徴収票の発行を依頼するのが基本です。
会社には、退職後1か月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。
もし、何度依頼しても会社が応じてくれない場合は、最終手段として税務署に相談してみましょう。
お近くの税務署へ行き、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を提出することで、税務署から会社へ指導がおこなわれる場合があります。
給与明細など、給与額がわかる書類を持参すると手続きがスムーズに進みます。諦めずに、まずは行動してみることが大切です。
確定申告をしたら扶養から外れることはあるか?
「扶養」には、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があり、それぞれ基準が異なるため注意が必要です。
確定申告をしても、税法上の扶養から外れることは基本的にありません。
なぜなら、失業保険は非課税所得であり、扶養を判定する際の合計所得金額に含まれないからです。
一方で、社会保険の扶養については、失業保険が「収入」とみなされます。多くの健康保険組合では、年収130万円未満であることが扶養の条件です。
失業保険の日額が3,612円以上になると、この基準を超える可能性があるため、扶養から外れて自身で国民健康保険に加入する手続きが必要になる場合があります。
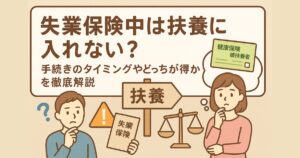
確定申告の還付金はいつもらえるか?
還付金が振り込まれるまでの期間は、申告方法によって異なります。
最も早いのはe-Tax(電子申告)で、申告から約2〜3週間が目安です。
一方、紙の申告書を郵送または持参した場合は、処理に時間がかかるため、約1か月から1か月半ほど見ておくとよいでしょう。
早く還付を受けたい場合は、e-Taxでの申告がおすすめです。
去年の確定申告を忘れていたが今からでもできるか?
税金を納めすぎた場合に還付を受けるための「還付申告」は、その年の翌年1月1日から5年間おこなうことが可能です。
たとえば、2023年分の申告であれば、2028年の年末まで手続きができます。
「もう期間が過ぎてしまった」と諦めずに、すぐに準備をはじめましょう。
ただし、納税義務がある申告を忘れていた場合は、期限後申告となりペナルティが発生する可能性があるので注意が必要です。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /
まとめ:失業保険の確定申告は不要な場合も!正しい知識で損なく手続きを

この記事では、失業保険と確定申告の関係について、申告が「不要なケース」「した方が得なケース」「必要なケース」の3つのパターンに分けて詳しく解説しました。
失業保険は非課税のため、原則として確定申告の義務はありません。
しかし、年の途中で退職した方などは、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
一方で、副業などで一定以上の所得がある場合は申告が義務となりますので注意が必要です。
もし手続きに不安を感じたり、より有利な条件で失業保険を受給したいと考えたりした場合は、「退職バンク」のような専門サービスに相談するのも一つの有効な手段です。
今回の内容を参考に、自身の状況を正しく判断し、損のない最適な行動を選択してください。
\ 申請サポートの無料相談はこちら /